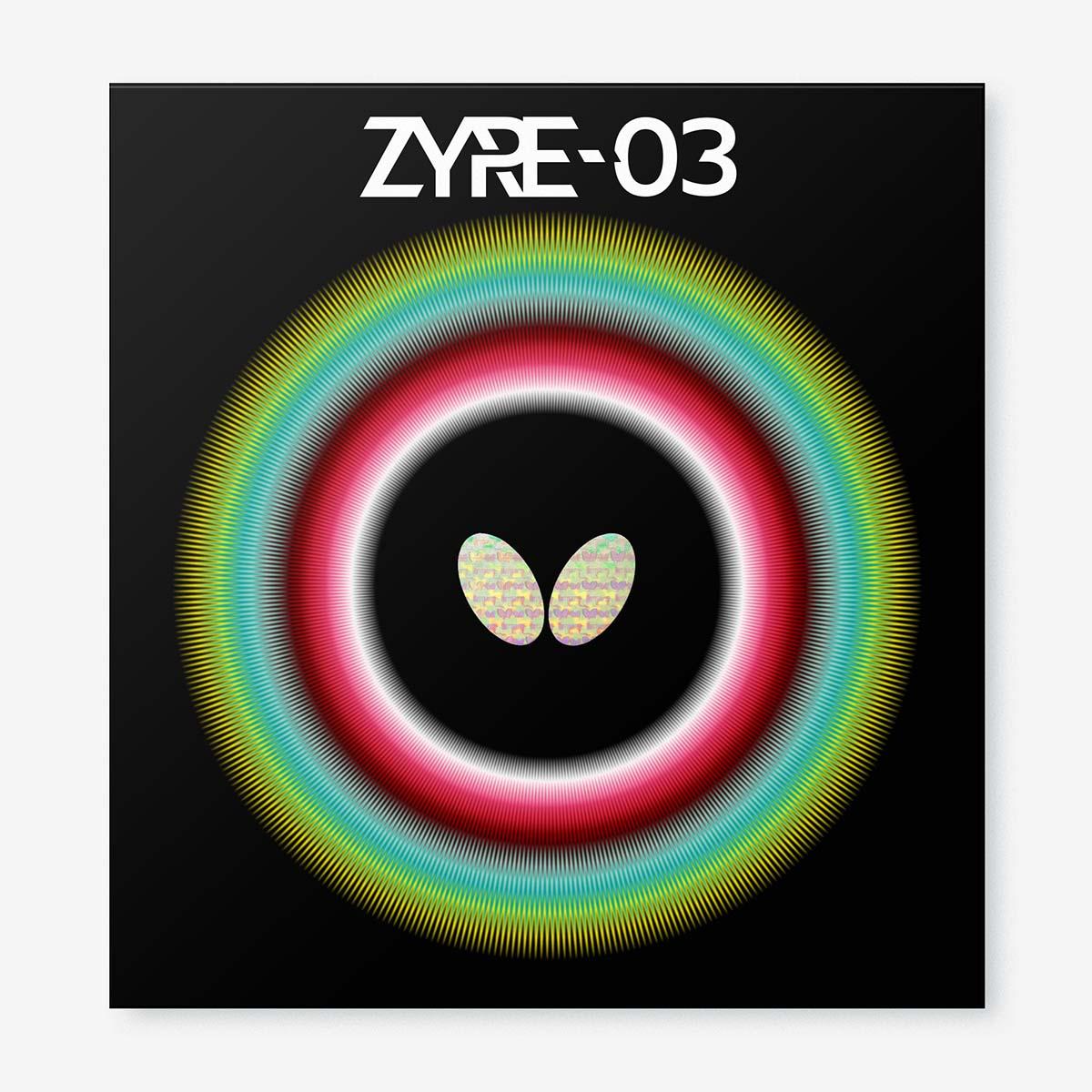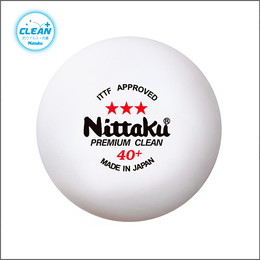前回は気配りシニアの方についてお話ししました。
今回ご登場いただくのも巷の愛好家の方ですが、やや厳しい頑固オヤジ的な人です。
──────────────────────
集中するのはラブオールから
──────────────────────
町田さん(仮名)は50代くらいの男性です。
休憩ベンチに座ってお話をうかがっていると、しきりに「考えろ」という点を強調されていました。
試合の際、ラブオール直後だからといって漫然とその後の成り行きに従って試合内容を組み立てていくのはよくないという忠告から始まりました。
世間には分析的ではなく情緒的な方も大勢いらっしゃいます。
「ゲームオールのジュースのあの1本は大きかった」などと言う人を町田さんは手厳しく批判します。
漫画やドラマを見ているなら、そういった演出に感動するのは構いません。
でも現実においては全くのナンセンスです。
試合が始まった最初の1本と最終ゲームジュースの1本は同じ価値です。
感情は捨てて考えろというその言葉に、私も深くうなづけました。
ただそれとは逆に、時間的に先行して得点することは大切だと力説していました。
同じ勝ちでもドラマチックな逆転勝利より、先行逃げ切り、最善なのは一方的なぶっちぎり勝利です。
スコアが7-1くらいだと、リスクが高めの攻めを1~2回は試してみることができます。
もちろん1点の重みはそこでも同じという認識です。
しかし取れる選択肢の幅が増え、心理的な負担も少なくなるスタートダッシュを、1ゲーム目の0-0から狙う心構えで臨むべきとのことです。
私は適宜相槌を打ちながら傾聴していると、町田さんのお話に込める熱量が徐々に上昇していく感じが伝わってきました。
今回ご登場いただくのも巷の愛好家の方ですが、やや厳しい頑固オヤジ的な人です。
──────────────────────
集中するのはラブオールから
──────────────────────
町田さん(仮名)は50代くらいの男性です。
休憩ベンチに座ってお話をうかがっていると、しきりに「考えろ」という点を強調されていました。
試合の際、ラブオール直後だからといって漫然とその後の成り行きに従って試合内容を組み立てていくのはよくないという忠告から始まりました。
世間には分析的ではなく情緒的な方も大勢いらっしゃいます。
「ゲームオールのジュースのあの1本は大きかった」などと言う人を町田さんは手厳しく批判します。
漫画やドラマを見ているなら、そういった演出に感動するのは構いません。
でも現実においては全くのナンセンスです。
試合が始まった最初の1本と最終ゲームジュースの1本は同じ価値です。
感情は捨てて考えろというその言葉に、私も深くうなづけました。
ただそれとは逆に、時間的に先行して得点することは大切だと力説していました。
同じ勝ちでもドラマチックな逆転勝利より、先行逃げ切り、最善なのは一方的なぶっちぎり勝利です。
スコアが7-1くらいだと、リスクが高めの攻めを1~2回は試してみることができます。
もちろん1点の重みはそこでも同じという認識です。
しかし取れる選択肢の幅が増え、心理的な負担も少なくなるスタートダッシュを、1ゲーム目の0-0から狙う心構えで臨むべきとのことです。
私は適宜相槌を打ちながら傾聴していると、町田さんのお話に込める熱量が徐々に上昇していく感じが伝わってきました。
今回はあるシニアの方についてお話ししたいと思います。
お名前は青井さん(仮名)ということにしておきます。
──────────────────────
敬遠されるのは当然だと理解する
──────────────────────
青井さんは70歳くらいの男性です。
中ペン(中国式ペンホルダー)の片面だけに裏ソフトを貼った、オーソドックスなスタイルです。
青井さんが重視しているのは、卓球場に集う他の人との関係性です。
巷にある民間の卓球場では利用料を払い、試合あるいは自分の好きな練習をします。
それは運動不足やストレス解消であったり、技術的向上を目指すためという場合が多いでしょう。
青井さんの場合もそういう目的はあるのですが、自分がいかに卓球場の中に溶け込めているかに注力しています。
ご自身がシニア世代に突入している状態をしっかり認識すべきとのお考えです。
他の方はほとんどが自分より若い世代で10代の若者もいます。
そういう人たちとは、やはりある程度の心理的距離が生じるのは自然で、それを和らげるようにされています。
お名前は青井さん(仮名)ということにしておきます。
──────────────────────
敬遠されるのは当然だと理解する
──────────────────────
青井さんは70歳くらいの男性です。
中ペン(中国式ペンホルダー)の片面だけに裏ソフトを貼った、オーソドックスなスタイルです。
青井さんが重視しているのは、卓球場に集う他の人との関係性です。
巷にある民間の卓球場では利用料を払い、試合あるいは自分の好きな練習をします。
それは運動不足やストレス解消であったり、技術的向上を目指すためという場合が多いでしょう。
青井さんの場合もそういう目的はあるのですが、自分がいかに卓球場の中に溶け込めているかに注力しています。
ご自身がシニア世代に突入している状態をしっかり認識すべきとのお考えです。
他の方はほとんどが自分より若い世代で10代の若者もいます。
そういう人たちとは、やはりある程度の心理的距離が生じるのは自然で、それを和らげるようにされています。
2024 .03.16
今回は今年の夏に開かれるパリオリンピックについてお話ししたいと思います。
東京五輪が1年延期されたため、なんだもう次のオリンピックなのかと感じている方が多いかもしれませんね。
──────────────────────
うれしい放送時間
──────────────────────
大会全体の開催期間は7月26日~8月12日です。
その中で卓球競技は7月27日~8月10日にかけて行われます。
フランスのパリと日本の時差は8時間。
そのため自宅で録画しておいた映像の視聴が多くなりそうです。
映像を見る前に、さまざまな媒体より漏れ聞こえてくる試合結果を遮断するのはかなり難しいと予想されます。
と思っていた所、その心配はあまりなさそうということが分かりました。
山場を迎えた試合はいずれも視聴しやすい時間帯に行われるからです。
メダル獲得がかかった試合の開始時刻は以下の通りです(日本時間)。
7/30(火)混合ダブルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/3(土)女子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/4(日)男子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/9(金)男子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
8/10(土)女子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
おぉっ、なんてナイスな時間なんでしょうか!
東京五輪が1年延期されたため、なんだもう次のオリンピックなのかと感じている方が多いかもしれませんね。
──────────────────────
うれしい放送時間
──────────────────────
大会全体の開催期間は7月26日~8月12日です。
その中で卓球競技は7月27日~8月10日にかけて行われます。
フランスのパリと日本の時差は8時間。
そのため自宅で録画しておいた映像の視聴が多くなりそうです。
映像を見る前に、さまざまな媒体より漏れ聞こえてくる試合結果を遮断するのはかなり難しいと予想されます。
と思っていた所、その心配はあまりなさそうということが分かりました。
山場を迎えた試合はいずれも視聴しやすい時間帯に行われるからです。
メダル獲得がかかった試合の開始時刻は以下の通りです(日本時間)。
7/30(火)混合ダブルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/3(土)女子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/4(日)男子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/9(金)男子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
8/10(土)女子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
おぉっ、なんてナイスな時間なんでしょうか!
今回は卓球界の主流である、両面に裏ソフトラバーを貼ったドライブマンについてお話ししたいと思います。
攻撃型で裏裏だとドライブマンだと短絡的に考えてしまいがちです。
そうではなく本当のドライブマンとはどんな人なのか深堀りしてみます。
──────────────────────
ドライブ連打だからドライブマン
──────────────────────
シェークにしろペンにしろ、両面裏ソフトの人は多数派です。
その中にはミート主体やブロック多用、ラリーを好まず一発打ち抜きタイプの人もいます。
従ってドライブマンという呼称は適切でないように思えます。
別にそういうタイプの人を批判しているわけではなく、それはそれで各自が選んだスタイルなので尊重します。
ただ私個人が理想とするのは、純粋なドライブマンです。
卓球という競技はボールに回転を掛けることが大きな特徴です。
表現が大げさに聞こえるかもしれませんが、それが卓球をする醍醐味で回転を操る喜びを皆さんにも堪能してもらえたらと考えています。
攻撃型で裏裏だとドライブマンだと短絡的に考えてしまいがちです。
そうではなく本当のドライブマンとはどんな人なのか深堀りしてみます。
──────────────────────
ドライブ連打だからドライブマン
──────────────────────
シェークにしろペンにしろ、両面裏ソフトの人は多数派です。
その中にはミート主体やブロック多用、ラリーを好まず一発打ち抜きタイプの人もいます。
従ってドライブマンという呼称は適切でないように思えます。
別にそういうタイプの人を批判しているわけではなく、それはそれで各自が選んだスタイルなので尊重します。
ただ私個人が理想とするのは、純粋なドライブマンです。
卓球という競技はボールに回転を掛けることが大きな特徴です。
表現が大げさに聞こえるかもしれませんが、それが卓球をする醍醐味で回転を操る喜びを皆さんにも堪能してもらえたらと考えています。
今回は世界卓球選手権についてお話しします。
各種メディアで報道がなされており、スケジュールや試合結果など一般的な情報はそちらご確認いただければと思います。
──────────────────────
紆余曲折を辿った開催
──────────────────────
開催場所はお隣韓国のプサン(釜山)です。
首都のソウルも飛行機ですぐに着くのですが、プサンはさらに距離が近いため福岡から船で訪れるコースも人気です。
プサンのアルファベット表記はBusanでPusanではありません。
最初の文字がBだと読みはP、日本語で言うところのパ行になるようです。
冬のソナタでお馴染みのヨン様ことペ・ヨンジュンさんも名字はBaeです。
他にも韓国のアルファベット表記は、最初の文字がRやLだと読み飛ばすなど少しややこしいです。
本来は2020年にプサンで世界選手権が行われる予定でした。
ところがその年の最初に全世界でコロナショックが巻き起こりました。
延期に次ぐ延期が発表され、結局開催見送りとなった経緯があります。
今回は満を持しての仕切り直し開催という意味もあるでしょう。
今年はオリンピックイヤーとなるため、世界選手権は通常の開催時期よりも早めに行われます。
ビッグイベントが短期間で連続しないようにしています。
私だけではないでしょうが、もうオリンピックなんだという不思議な感じがあります。
それは東京オリンピックが1年延期されたことが影響しています。
コロナは別に収束したわけではなく、変異を続けながら感染者は世界中で引き続き出ています。
しかし重篤化する危険性が下がったことや、ウイズコロナの考えが広まり以前の日常がほぼ戻ってきました。
私も昨年後半に感染してしまいました。
幸いにも大事に至ることはなく、市販の風邪薬を服用しながら1週間大人しく過ごすことで治りました。
各種メディアで報道がなされており、スケジュールや試合結果など一般的な情報はそちらご確認いただければと思います。
──────────────────────
紆余曲折を辿った開催
──────────────────────
開催場所はお隣韓国のプサン(釜山)です。
首都のソウルも飛行機ですぐに着くのですが、プサンはさらに距離が近いため福岡から船で訪れるコースも人気です。
プサンのアルファベット表記はBusanでPusanではありません。
最初の文字がBだと読みはP、日本語で言うところのパ行になるようです。
冬のソナタでお馴染みのヨン様ことペ・ヨンジュンさんも名字はBaeです。
他にも韓国のアルファベット表記は、最初の文字がRやLだと読み飛ばすなど少しややこしいです。
本来は2020年にプサンで世界選手権が行われる予定でした。
ところがその年の最初に全世界でコロナショックが巻き起こりました。
延期に次ぐ延期が発表され、結局開催見送りとなった経緯があります。
今回は満を持しての仕切り直し開催という意味もあるでしょう。
今年はオリンピックイヤーとなるため、世界選手権は通常の開催時期よりも早めに行われます。
ビッグイベントが短期間で連続しないようにしています。
私だけではないでしょうが、もうオリンピックなんだという不思議な感じがあります。
それは東京オリンピックが1年延期されたことが影響しています。
コロナは別に収束したわけではなく、変異を続けながら感染者は世界中で引き続き出ています。
しかし重篤化する危険性が下がったことや、ウイズコロナの考えが広まり以前の日常がほぼ戻ってきました。
私も昨年後半に感染してしまいました。
幸いにも大事に至ることはなく、市販の風邪薬を服用しながら1週間大人しく過ごすことで治りました。
2024 .02.03
先月の1月22日から28日までの日程で全日本選手権が開催されました。
試合結果などについては大手メディアを参照いただければと思います。
私が練習をご一緒する方々との雑談で出た意見をご紹介いたします。
──────────────────────
分散開催、TV放送
──────────────────────
最初にいただいたのは、従来通りの大会は今回が最後だねというお話でした。
来年はシングルスとダブルスが分離開催されます。
2025年1月21日~26日に東京体育館でシングルスが行われ、続いて1月30日から2月2日にかけて愛知県のスカイホール豊田でダブルスが行われます。
2つに分かれるとそれぞれの大会規模が縮小され、話題性もやや下がるのではないかと思われます。
しかしこれは選手ファーストの観点からすれば改善であり、妥当ではないでしょうか。
全日本ではありませんが、昔の世界選手権は団体戦と個人戦を1回の大会で行っていたという、かなり無茶な運営がありました。
ある1人の選手が物理的に出場可能なのは、団体、シングルス、男女どちらかのダブルス、混合ダブルスの計4種目でしょうが、全てにエントリーすると多忙すぎて倒れてしまうでしょう。
他には今回の全日本は開催時期が1週間早かったら良かったのにというご意見がありました。
いつものようにNHKは全日本を放送してはくれたのですが、大相撲と重なってしまったのでNHK的には相撲の方をメインに取り上げざるを得ない事情がありました。
テレビの映像は最近の世界選手権のような横方向ではなく、縦方向のアングルにほぼ固定されており、そのほうがいいねという感想が多数出ました。
ただし放送中にNHK総合のサブチャンネルとの切り替わりがあり、その影響を受けた方がいました。
録画機器が追従できなかったり、サブチャンネルは画質が落ちていたケースがあったようです。
試合結果などについては大手メディアを参照いただければと思います。
私が練習をご一緒する方々との雑談で出た意見をご紹介いたします。
──────────────────────
分散開催、TV放送
──────────────────────
最初にいただいたのは、従来通りの大会は今回が最後だねというお話でした。
来年はシングルスとダブルスが分離開催されます。
2025年1月21日~26日に東京体育館でシングルスが行われ、続いて1月30日から2月2日にかけて愛知県のスカイホール豊田でダブルスが行われます。
2つに分かれるとそれぞれの大会規模が縮小され、話題性もやや下がるのではないかと思われます。
しかしこれは選手ファーストの観点からすれば改善であり、妥当ではないでしょうか。
全日本ではありませんが、昔の世界選手権は団体戦と個人戦を1回の大会で行っていたという、かなり無茶な運営がありました。
ある1人の選手が物理的に出場可能なのは、団体、シングルス、男女どちらかのダブルス、混合ダブルスの計4種目でしょうが、全てにエントリーすると多忙すぎて倒れてしまうでしょう。
他には今回の全日本は開催時期が1週間早かったら良かったのにというご意見がありました。
いつものようにNHKは全日本を放送してはくれたのですが、大相撲と重なってしまったのでNHK的には相撲の方をメインに取り上げざるを得ない事情がありました。
テレビの映像は最近の世界選手権のような横方向ではなく、縦方向のアングルにほぼ固定されており、そのほうがいいねという感想が多数出ました。
ただし放送中にNHK総合のサブチャンネルとの切り替わりがあり、その影響を受けた方がいました。
録画機器が追従できなかったり、サブチャンネルは画質が落ちていたケースがあったようです。
2024 .01.20
技術の進歩や制度の改革などにより私達の生活様式は向上しています。
それは卓球にも当てはまります。
主に中高年の方との話を通じて再確認した具体例を見ていきたいと思います。
──────────────────────
何をおいてもまずはラバー
──────────────────────
用具関連ではラバーの進化が最も実感できる変化です。
卓球のいわば創世記には、板でそのまま打ったりコルクを貼って打ったりしていたのが、次第にゴムシートかスポンジを貼ることに集約されていきました。
いろいろな議論や検討を経て、半世紀ほど前におおよそ現在に近いラバーの取り決めとなりました。
しかしその後も大枠は保たれたまま改良が進み、テンションラバー全盛期を迎えています。
弾むのに回転もかかり、おまけに扱いやすい。
定番のロゼナなどを使っていると、入門用の位置づけ製品でも十分に高性能です。
かつての王道ラバーと言われたスレイバーやマークVがかすんでしまう存在です。
裏ソフト以外でも、例えば粒高ラバーのスポンジはものすごい微妙な薄さのバリエーションがあります。
昔はスポンジ厚がかなり適当でバラツキがあったという話をされた方には、隔世の感があるそうです。
それは卓球にも当てはまります。
主に中高年の方との話を通じて再確認した具体例を見ていきたいと思います。
──────────────────────
何をおいてもまずはラバー
──────────────────────
用具関連ではラバーの進化が最も実感できる変化です。
卓球のいわば創世記には、板でそのまま打ったりコルクを貼って打ったりしていたのが、次第にゴムシートかスポンジを貼ることに集約されていきました。
いろいろな議論や検討を経て、半世紀ほど前におおよそ現在に近いラバーの取り決めとなりました。
しかしその後も大枠は保たれたまま改良が進み、テンションラバー全盛期を迎えています。
弾むのに回転もかかり、おまけに扱いやすい。
定番のロゼナなどを使っていると、入門用の位置づけ製品でも十分に高性能です。
かつての王道ラバーと言われたスレイバーやマークVがかすんでしまう存在です。
裏ソフト以外でも、例えば粒高ラバーのスポンジはものすごい微妙な薄さのバリエーションがあります。
昔はスポンジ厚がかなり適当でバラツキがあったという話をされた方には、隔世の感があるそうです。
2024 .01.06
全国津々浦々、各地の卓球場では試合が行われています。
私が普段お邪魔している所でも練習に続いて試合という流れで進みます。
今回はその試合中に感じたことをお話ししたいと思います。
──────────────────────
バックハンドで打つべし
──────────────────────
ネット上にある上級者の試合動画を見ると、フォア前に出されたサーブをすすっとフォア側に動き鮮やかにバックハンドで払う場面があります。
お手本のようなバックハンド攻撃で、片面だけにラバーを貼ったペンの私にはできない芸当です。
過去に裏面打法を試みて挫折した苦い思い出がふとよみがえることもあります。
そんなことは綺麗さっぱり忘れなさいと自分に言い聞かせると同時に、両面にラバーを貼っている皆さんには頑張って欲しいという思いがあります。
試合の審判をしていると、シェーク裏裏同士の対戦なのにやたらとバックのツッツキ合いが続くことがあります。
打ち込んでいくとそれなりの確率でミスってしまうため、慎重になっているのは分かります。
それでも流石にバウンド後のボールが明らかに台から出る長さなら、バックハンドを振って欲しいと見ていてイライラがつのります。
私ならとうの昔にフォアで回り込んで攻撃を仕掛けています。
片面にしかラバーを貼っていないので自分はこれしかないという決意があり、強引な回り込みが多いのは自分でも認識しています。
かなり差し込まれた返球でバック側サイドを切るボールを気合で回り込んで打つと、中高生などからスゲーと言われます。
そんな私からすれば、せっかくラバーを2枚貼っているんだからもっとバックから攻撃して欲しいぞと心のなかで叫んでいます。
私が普段お邪魔している所でも練習に続いて試合という流れで進みます。
今回はその試合中に感じたことをお話ししたいと思います。
──────────────────────
バックハンドで打つべし
──────────────────────
ネット上にある上級者の試合動画を見ると、フォア前に出されたサーブをすすっとフォア側に動き鮮やかにバックハンドで払う場面があります。
お手本のようなバックハンド攻撃で、片面だけにラバーを貼ったペンの私にはできない芸当です。
過去に裏面打法を試みて挫折した苦い思い出がふとよみがえることもあります。
そんなことは綺麗さっぱり忘れなさいと自分に言い聞かせると同時に、両面にラバーを貼っている皆さんには頑張って欲しいという思いがあります。
試合の審判をしていると、シェーク裏裏同士の対戦なのにやたらとバックのツッツキ合いが続くことがあります。
打ち込んでいくとそれなりの確率でミスってしまうため、慎重になっているのは分かります。
それでも流石にバウンド後のボールが明らかに台から出る長さなら、バックハンドを振って欲しいと見ていてイライラがつのります。
私ならとうの昔にフォアで回り込んで攻撃を仕掛けています。
片面にしかラバーを貼っていないので自分はこれしかないという決意があり、強引な回り込みが多いのは自分でも認識しています。
かなり差し込まれた返球でバック側サイドを切るボールを気合で回り込んで打つと、中高生などからスゲーと言われます。
そんな私からすれば、せっかくラバーを2枚貼っているんだからもっとバックから攻撃して欲しいぞと心のなかで叫んでいます。
私は部活で卓球をしていた頃は万年補欠だったので勝率はかなり低めでした。
その後は初級者との対戦も増え、ある程度はマシになりました。
それでも負け試合は多く、振り返った時の感想を述べてみます。
──────────────────────
良い負け試合
──────────────────────
ここで言う「良い」という表現は、客観的・合理的に良いという意味ではありません。
私の気持ちとして「負けたけれど納得できる試合だった」と思えた試合のことです。
そういうのはやはり数回以上のラリーが何度も続いた試合です。
一般的な卓球の試合でイメージするボールの往復があると充実感が満たされます。
さらに適度に競った場合、満足度がより高くなります。
ドラマチック効果なのかもしれません。
相手が格上の場合ならどんな展開でそう思えるでしょうか。
エースボールをブロックできた、裏を掻いた一打が決まったなど自分が一矢報いた場面があった時はそう感じます。
やられてしまった時も絶妙の流し打ちや、ネットインをカーブロングで返されたりすると、自分に対しこんな離れ業を披露してくれるのかと一瞬感謝したくなります。
その後は初級者との対戦も増え、ある程度はマシになりました。
それでも負け試合は多く、振り返った時の感想を述べてみます。
──────────────────────
良い負け試合
──────────────────────
ここで言う「良い」という表現は、客観的・合理的に良いという意味ではありません。
私の気持ちとして「負けたけれど納得できる試合だった」と思えた試合のことです。
そういうのはやはり数回以上のラリーが何度も続いた試合です。
一般的な卓球の試合でイメージするボールの往復があると充実感が満たされます。
さらに適度に競った場合、満足度がより高くなります。
ドラマチック効果なのかもしれません。
相手が格上の場合ならどんな展開でそう思えるでしょうか。
エースボールをブロックできた、裏を掻いた一打が決まったなど自分が一矢報いた場面があった時はそう感じます。
やられてしまった時も絶妙の流し打ちや、ネットインをカーブロングで返されたりすると、自分に対しこんな離れ業を披露してくれるのかと一瞬感謝したくなります。
2023 .12.09
ずっと前にラバーの貼り替えについてお話をしました。
その時は主に貼り替え方法についてご説明いたしました。
今回は貼り替えるタイミングについて述べてみたいと思います。
一口にラバーの貼り替え時期と言ってもラバーの種類によって判断基準が異なります。
そこで大きな分類である、裏ソフト、表ソフト、粒高、アンチの4種類それぞれについて考えてみたいと思います。
──────────────────────
裏ソフト
──────────────────────
一般的に貼り替え時期の判断は、裏ソフトの生命線である引っかかりの劣化度合いによります。
例外としては台の角などにぶつけてしまい亀裂が入った時は、まだ十分なグリップ力があるのに泣く泣く貼り替えざるを得ないというケースがあります。
さらに稀な例としては、製造不良でシートがスポンジから剥がれてしまう剥離というものあります。
剥離が起きるとその部分だけが若干ポコッと浮いたようになります。
さて話を元に戻して通常の引っかかりの衰えについてですが、物理的に詳しい原因は私もよく分かりません。
微細なレベルで観察すれば、シートの表面に細かな傷や凹凸が生じ、そこにゴミなども入る。
あるいは別の要因としてゴムシートの弾力が低下してくる。
などがあるのでしょう。
なんとなく後者の理由のほうが確率が高そうな気がします。
弾力の低下といっても経年劣化ではなく、試合や練習であれだけバシバシボールを叩き続けているのですから、ゴムシート君にとってはたまったものではないと感じているからです。
用具メーカーが案内している貼り替え時期の判断で、表面の色がくすんできたり、下にある粒の形が浮き上がってきた場合というのがあります。
公式にそういう案内をしているので概ね合っているのでしょう。
私としては使っている本人の感覚を重視してはと考えています。
粒が浮いていても劣化を感じないのならそのまま使い続けます。
たとえ新品の時と比べて劣化を感じたとしても、使っている本人がまだ十分いけそうと思うのなら使い続けるのです。
車のタイヤであれば安全に直結するため目視確認による減り具合で判断すべきです。
でも卓球のラバーにはそういうことはありません。
初級レベルの人なら劣化が分からず、縁がボロボロに欠けた状態でも使っている人がいます。
流石にそのあたりになるともう貼り替えてはどうかと思います。
その時は主に貼り替え方法についてご説明いたしました。
今回は貼り替えるタイミングについて述べてみたいと思います。
一口にラバーの貼り替え時期と言ってもラバーの種類によって判断基準が異なります。
そこで大きな分類である、裏ソフト、表ソフト、粒高、アンチの4種類それぞれについて考えてみたいと思います。
──────────────────────
裏ソフト
──────────────────────
一般的に貼り替え時期の判断は、裏ソフトの生命線である引っかかりの劣化度合いによります。
例外としては台の角などにぶつけてしまい亀裂が入った時は、まだ十分なグリップ力があるのに泣く泣く貼り替えざるを得ないというケースがあります。
さらに稀な例としては、製造不良でシートがスポンジから剥がれてしまう剥離というものあります。
剥離が起きるとその部分だけが若干ポコッと浮いたようになります。
さて話を元に戻して通常の引っかかりの衰えについてですが、物理的に詳しい原因は私もよく分かりません。
微細なレベルで観察すれば、シートの表面に細かな傷や凹凸が生じ、そこにゴミなども入る。
あるいは別の要因としてゴムシートの弾力が低下してくる。
などがあるのでしょう。
なんとなく後者の理由のほうが確率が高そうな気がします。
弾力の低下といっても経年劣化ではなく、試合や練習であれだけバシバシボールを叩き続けているのですから、ゴムシート君にとってはたまったものではないと感じているからです。
用具メーカーが案内している貼り替え時期の判断で、表面の色がくすんできたり、下にある粒の形が浮き上がってきた場合というのがあります。
公式にそういう案内をしているので概ね合っているのでしょう。
私としては使っている本人の感覚を重視してはと考えています。
粒が浮いていても劣化を感じないのならそのまま使い続けます。
たとえ新品の時と比べて劣化を感じたとしても、使っている本人がまだ十分いけそうと思うのなら使い続けるのです。
車のタイヤであれば安全に直結するため目視確認による減り具合で判断すべきです。
でも卓球のラバーにはそういうことはありません。
初級レベルの人なら劣化が分からず、縁がボロボロに欠けた状態でも使っている人がいます。
流石にそのあたりになるともう貼り替えてはどうかと思います。
ラケットに貼るラバーは必ずロゴ部分を残し、どのメーカーのどのラバーなのかを明示させておく必要があります。
今回はそれらを全て集めた公認ラバーリストについてお話したいと思います。
──────────────────────
仕切っているのはITTF
──────────────────────
ロゴマーク周囲を見ると番号が書いてあるものが沢山あります。
ITTF(国際卓球連盟)のマークに続き、ハイフンで繋がった数字が四角で囲われています。
例えば売れ筋であるニッタクのファスタークG1であれば、54-015という番号があります。
勘の良い方なら最初の54がニッタクを表し、後ろの015はファスタークG1を表すのではないかと考えるでしょう。
まさにその通りで、これは遡ること2008年にITTFがラバーにつけることを課した識別番号です。
国際大会の公式戦で使用するラバーはITTFが承認したラバーを使うこととなっています。
メーカーが承認を依頼し、ITTFの公認ラバーリストに登録されると使えるようになります。
今回はそれらを全て集めた公認ラバーリストについてお話したいと思います。
──────────────────────
仕切っているのはITTF
──────────────────────
ロゴマーク周囲を見ると番号が書いてあるものが沢山あります。
ITTF(国際卓球連盟)のマークに続き、ハイフンで繋がった数字が四角で囲われています。
例えば売れ筋であるニッタクのファスタークG1であれば、54-015という番号があります。
勘の良い方なら最初の54がニッタクを表し、後ろの015はファスタークG1を表すのではないかと考えるでしょう。
まさにその通りで、これは遡ること2008年にITTFがラバーにつけることを課した識別番号です。
国際大会の公式戦で使用するラバーはITTFが承認したラバーを使うこととなっています。
メーカーが承認を依頼し、ITTFの公認ラバーリストに登録されると使えるようになります。
これまでにも卓球動画について何度かお話をしたことがありました。
動画にもいろいろなものがあり、自分のプレーやフォームを確認する自撮り動画、トップ選手から巷の選手まで幅広いレベルが存在する試合動画などがあります。
今回はそれらとも異なるレッスンビデオ的な動画を取り上げてみたいと思います。
──────────────────────
分かりやすく無料なのが嬉しい
──────────────────────
実用性を考えると、レッスン動画は自撮り映像に次ぐ有用度の高さがあるのではないでしょうか。
どうやれば自分は上手くなれるのか日々悩んでいるワナビーには、一筋の光に思える映像に巡り合うことがあります。
YGサーブの出し方、レシーブのバリエーション、(私が挫折した)ペン裏面打法など、様々なハウツー映像がアップロードされています。
若干の広告映像や「チャンネル登録お願いします」などのメッセージが流れたりしますが、無料で上手い人の技術解説が視聴できるのを活用しない手はありません。
テーマ毎に短く分けて作成されているものが多く、電車での移動中など隙間時間にお手軽視聴ができてしまいます。
内容につられて手を動かしてしまうことがあるかもしれません。
しかし空いている車内であれば「むむっ」とチラ見される程度でどなたに迷惑もかかりません。
昔だと雑誌に載っている連続写真をじっくり見て、頭の中で再現する必要がありました。
動画であればそのままリアルな動きが把握できます。
そしてこの打法の肝となる部分はどこかや、陥りやすい駄目パターンを併せて説明してくれているものもあります。
キーワードを工夫して検索を繰り返せば、少数派やニッチな話題についてもヒットすることがあります。
絶滅の危機にあるペンホルダーといった大雑把なくくりだけでなく、さらに競技人口の少ないペン表のPUSH、ツッツキ、弱点など詳細まで出てくることがあります。
動画にもいろいろなものがあり、自分のプレーやフォームを確認する自撮り動画、トップ選手から巷の選手まで幅広いレベルが存在する試合動画などがあります。
今回はそれらとも異なるレッスンビデオ的な動画を取り上げてみたいと思います。
──────────────────────
分かりやすく無料なのが嬉しい
──────────────────────
実用性を考えると、レッスン動画は自撮り映像に次ぐ有用度の高さがあるのではないでしょうか。
どうやれば自分は上手くなれるのか日々悩んでいるワナビーには、一筋の光に思える映像に巡り合うことがあります。
YGサーブの出し方、レシーブのバリエーション、(私が挫折した)ペン裏面打法など、様々なハウツー映像がアップロードされています。
若干の広告映像や「チャンネル登録お願いします」などのメッセージが流れたりしますが、無料で上手い人の技術解説が視聴できるのを活用しない手はありません。
テーマ毎に短く分けて作成されているものが多く、電車での移動中など隙間時間にお手軽視聴ができてしまいます。
内容につられて手を動かしてしまうことがあるかもしれません。
しかし空いている車内であれば「むむっ」とチラ見される程度でどなたに迷惑もかかりません。
昔だと雑誌に載っている連続写真をじっくり見て、頭の中で再現する必要がありました。
動画であればそのままリアルな動きが把握できます。
そしてこの打法の肝となる部分はどこかや、陥りやすい駄目パターンを併せて説明してくれているものもあります。
キーワードを工夫して検索を繰り返せば、少数派やニッチな話題についてもヒットすることがあります。
絶滅の危機にあるペンホルダーといった大雑把なくくりだけでなく、さらに競技人口の少ないペン表のPUSH、ツッツキ、弱点など詳細まで出てくることがあります。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。