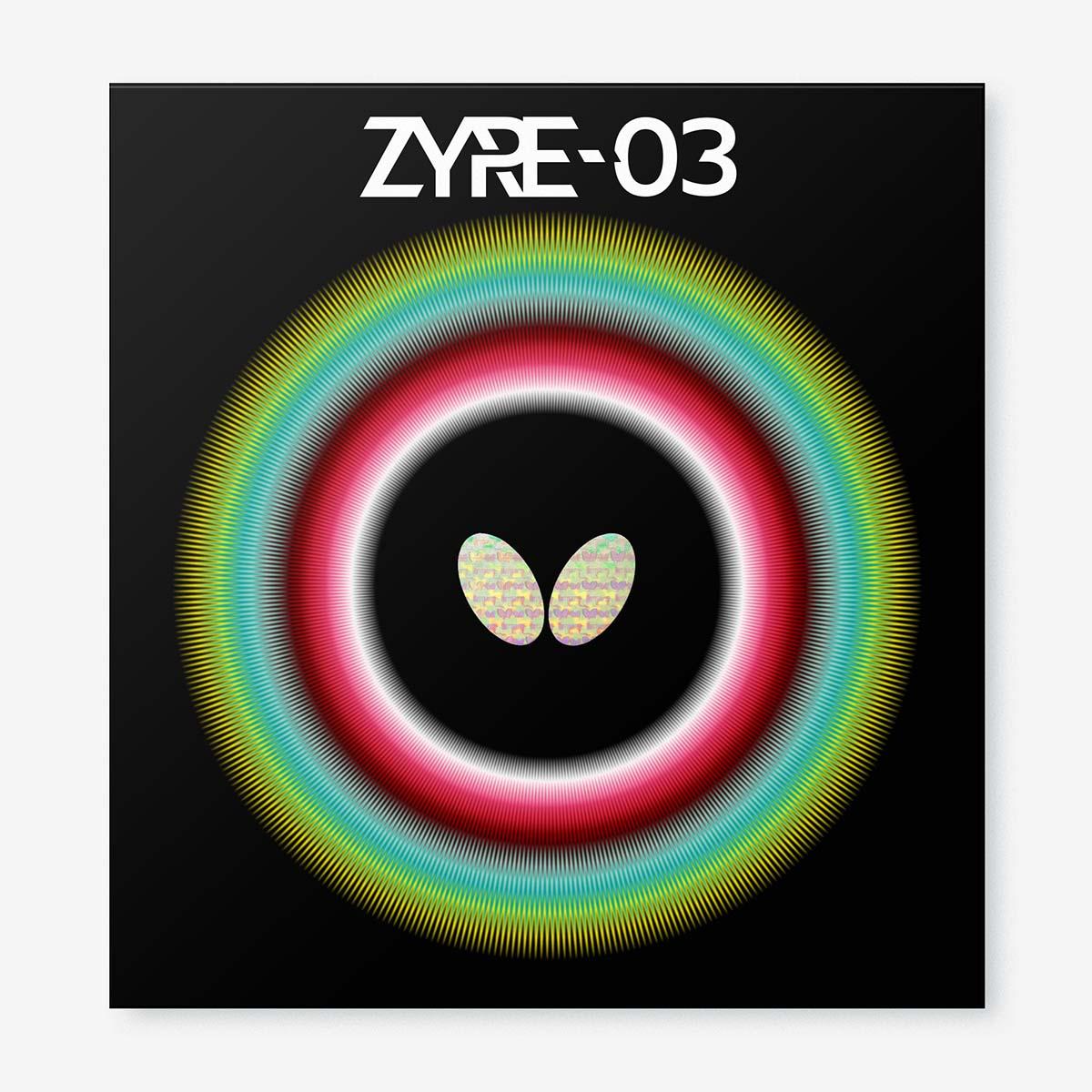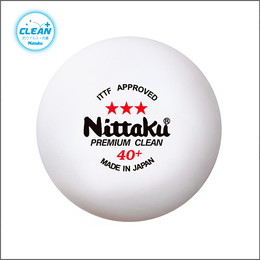2013 .03.02
各社が出している製品を眺めていると、コンセプト、打ち出し方、他の製品とのラインアップなどで少し疑問に感じるものがあります。
練習仲間からいただいた意見のいくつかをご紹介したいと思います。
──────────────────────
太っ腹な付録で訴求力アップ
──────────────────────
昔、アンドロの上位モデルのラケットで、もれなくラケットケースが付いていた製品がありました。
いかにもおまけで付けているようなケースではなく、しっかりとした作りで洗練されたデザインでした。
書店に足を運ぶと似たような体験ができます。
女性雑誌にはこれでもかと言わんばかりのすごい付録がついているものがあり、男性の私ですら思わず見入ってしまうことがあります。
アンドロ社の商品企画担当者は、同じような効果を狙ったのでしょうか。
でも正直なところ、そういう高性能ラケットを購入する人ならラケットケースはすでに持っています。
例えばラバー貼りラケットにピン球が付いているのは、その製品の利用者のことをよく考えていると思います。
卓球を始めるにあたりボールも準備したいという要望や、買ったラケットで球突きをして打球の感覚を養えるという効果もあります。
そしてピン球なら、たとえ余分にあっても邪魔になりません。
一方、アンドロのラケットにケースが付いていてうれしかった人は、そんなに多くなかったのではないかと想像します。
またお店にラケットを陳列する場合、箱の大きさが各社大体似通っていると、店員さんはレイアウトがイメージしやすくなります。
このケース付きラケットは箱のサイズが大きく、販売店は並べ方に苦慮していたのではないでしょうか。
──────────────────────
購入者の心理
──────────────────────
ダーカーはボールを打球する部分ではなく、グリップの所にだけカーボンを使った「ポイントカーボン」というラケットを販売しています。
本体で受けた力を、グリップのカーボンにより打ち返す仕組みだと説明があります。
通常は強い反発力を得るためのカーボンを、あえてグリップ部分にのみ使うという発想は独創的だと思います。
ただ実際に購入を検討する場合、多くの人はカーボンを使ったラケットなら、やはり打球部分に使って欲しいと考えるのが自然だと思います。
この心理的なモヤモヤが、少なからず購入の障害になっている気がします。
ダーカーのラケットには、もう一つおやっと思うことがあります。
7P-2Aというラケットがあり、同じ系統の製品として以下の3つがあります。
a.7P-2A(木材のみ使用したブレード)
b.7P-2Aポイントカーボン(グリップだけにカーボン使用)
c.7P-2Aカーボン(全体にカーボン使用)
値段の順に並べると、a<b<cとなります。
高性能な素材を使っているほうが高くなるという予想通りの順序で、納得のいく値付けです。
それでは弾みの順に並べるとどうなるでしょうか。
実は予想される、a<b<cの順ではなく、a<c<bという部分的に逆転現象が起きているのです。
私達の先入観通りではなく、実測に基づいた正直な見せ方なのはいいことです。
でもこういう結果になると、論理立てて製品のラインアップを説明するのに苦しいかもしれません。
ポイントカーボンは、7P-2Aとは違った別の製品体系にすればよかったのではと思います。
──────────────────────
重心の位置
──────────────────────
スティガのラケットには、グリップ部分に空洞を設けているものがあります。
メーカの説明によると、ラケットの重心が先端寄りになって打球位置に近づくため、スピードとコントロールが向上するとのことです。
卓球のラケットにはいろいろな形状があり、その中の一つに中国式ペンホルダー(中ペン)というのがあります。
一見グリップの短いシェークハンドに見えます。
じっくり観察すると、ブレードのグリップに近い部分がシェークよりもふくらんでエラが張ったような中ペンがあります。
スティガの中ペンには、そういった形のものがいくつかあります。
重心がグリップ寄りになることで安定性が向上し、中ペンを使う人にはこのタイプを好む人もいます。
エラ張り中ペンにもグリップが空洞のタイプがあります。
エラ張りにして重心をグリップ寄りにしているのに、グリップの空洞化で重心を先端寄りにしています。
これは相反することの組み合わせになっていて、お互いの効果を打ち消しているような感じがしてしまいます。
空洞はラケット「全体」の軽量化には貢献しています。
従って該当する中ペンを使っている人は、軽くしているという点だけを喜び、それ以外は深く考えないほうがいいかもしれません。
──────────────────────
名前で赤と黒は避けるべき
──────────────────────
アームストロングの表ソフトに赤マークという製品があります。
それとは別の裏ソフトラバーで、レッドマークという製品もあります。
「赤マーク=レッドマーク」なのかと誤解した人もいると思います。
普通に考えれば、これら2つの製品名を共存させるのは問題があります。
何かこうせざるを得ない複雑な事情があったのでしょうか。
もう一つの問題として、ラバーの色には赤と黒があります。
赤マークとレッドマークにも赤と黒があります。
例えばあるお店の店員さんが、赤マークの黒と、レッドマークの赤を注文した場合、発注や納品のどこかでミスが起きないか不安が胸をよぎります。
お店の在庫を検品するときもややこしいですし、フラストレーションがたまるのは良くないですね。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは、また次号をお楽しみに。
Comment
Trackback
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。