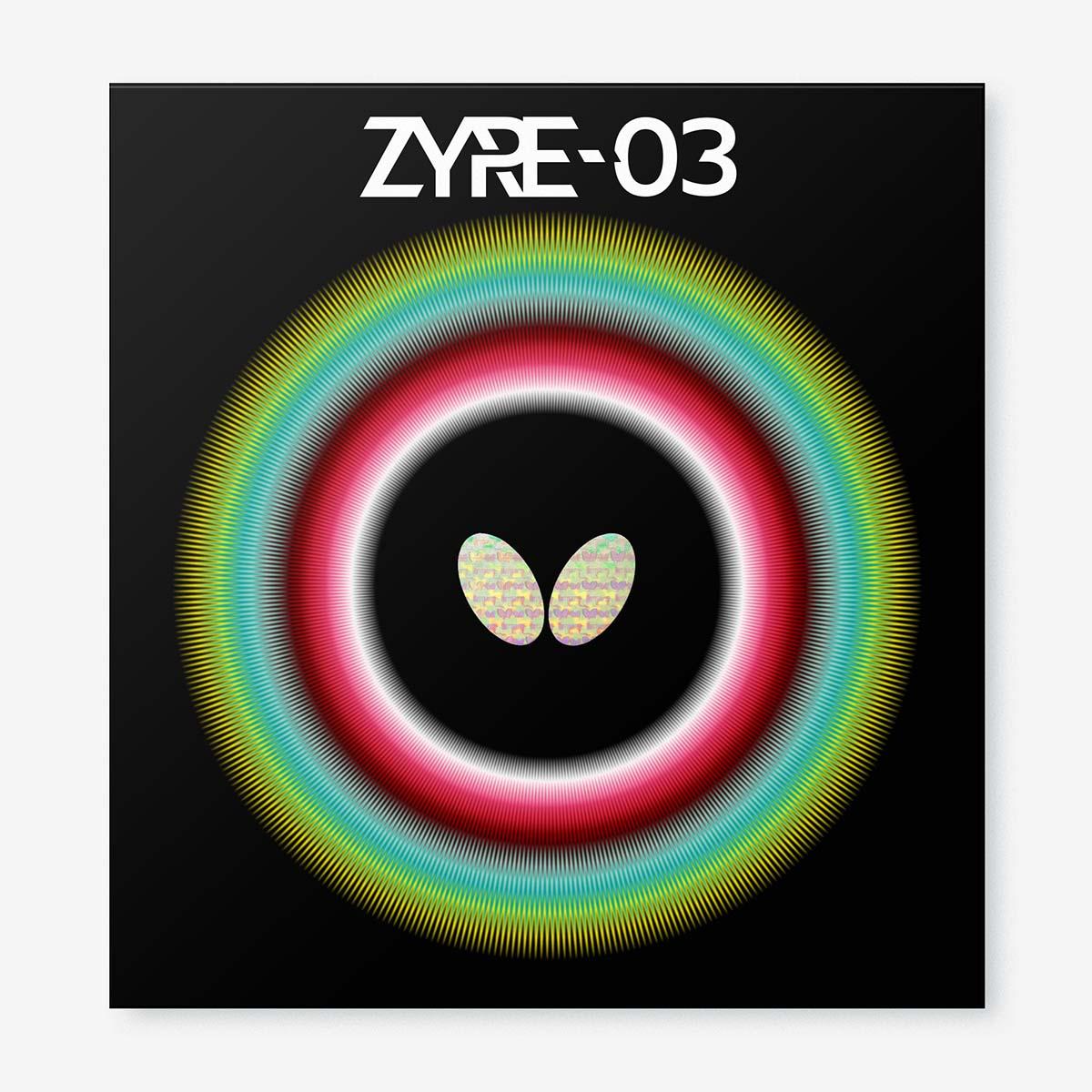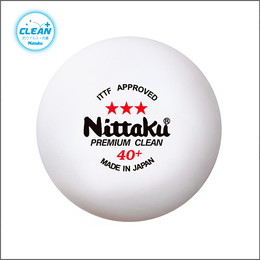試合をすると当然ながら実力の異なる人と対戦します。
その差がかなり大きいとどうしていいか試合中に戸惑ってしまうことがあります。
──────────────────────
心の持ちよう
──────────────────────
私はこれまでに0-11でゲームを失ったことが8回ありました。
内3回はレベルが離れすぎている同一人物で、何度試合をしても絶対に1ゲームも取れない人でした。
かなり強い方と対戦すると、いろいろな感情が脳裏をよぎります。
1)面白いように得点を決められてしまう。
2)自分の展開に持ち込めない。
3)点が取れないままだと0-11になる恐れがある。
誰しも人間なので悔しかったり情けなかったりすることはあります。
さらに途中で焦ってしまい、強い相手には100%の力でぶつからなければならないのに60%の出来だったという場合もあり得ます。
ではどう自分の気持ちに折り合いをつけるべきか。
結論としては必要以上に落ち込まず、現実をそのまま受け止めるしかありません。
その差がかなり大きいとどうしていいか試合中に戸惑ってしまうことがあります。
──────────────────────
心の持ちよう
──────────────────────
私はこれまでに0-11でゲームを失ったことが8回ありました。
内3回はレベルが離れすぎている同一人物で、何度試合をしても絶対に1ゲームも取れない人でした。
かなり強い方と対戦すると、いろいろな感情が脳裏をよぎります。
1)面白いように得点を決められてしまう。
2)自分の展開に持ち込めない。
3)点が取れないままだと0-11になる恐れがある。
誰しも人間なので悔しかったり情けなかったりすることはあります。
さらに途中で焦ってしまい、強い相手には100%の力でぶつからなければならないのに60%の出来だったという場合もあり得ます。
ではどう自分の気持ちに折り合いをつけるべきか。
結論としては必要以上に落ち込まず、現実をそのまま受け止めるしかありません。
2024 .09.14
7年前にX氏が関西学生リーグを見てきて私に語ってくれました。
それを皆さんにもご紹介しました。
今回X氏が再び観戦をしてきたので、そのレポートをお届けしたいと思います。
(卓球そのものの内容は少なめなのでご容赦願います)
──────────────────────
秋季リーグではない
──────────────────────
X氏の出張計画は、通常であれば午前中関西に移動し、午後は翌日の顧客訪問に備えた資料の読み込みとプレゼン作成でした。
そこを前倒しして深夜バスに切り替え早朝到着、そして試合を見ながら資料の読み込み、夜にホテルでプレゼン作成という強行日程に切り替えました。
一応、大会の名称は「秋季リーグ戦」となっています。
しかし初日は8月下旬に始まり、9月に入ってからも連日30度を超える日々の中、熱戦が繰り広げられます。
つっこみタイプのX氏は、まずここに指摘を行いました。
「春季・秋季リーグ戦じゃなく、前期・後期リーグ戦に改めるべきだ」
早速始まったと思いつつ、私は「確かにそうですね」と相槌を打ちました。
それを皆さんにもご紹介しました。
今回X氏が再び観戦をしてきたので、そのレポートをお届けしたいと思います。
(卓球そのものの内容は少なめなのでご容赦願います)
──────────────────────
秋季リーグではない
──────────────────────
X氏の出張計画は、通常であれば午前中関西に移動し、午後は翌日の顧客訪問に備えた資料の読み込みとプレゼン作成でした。
そこを前倒しして深夜バスに切り替え早朝到着、そして試合を見ながら資料の読み込み、夜にホテルでプレゼン作成という強行日程に切り替えました。
一応、大会の名称は「秋季リーグ戦」となっています。
しかし初日は8月下旬に始まり、9月に入ってからも連日30度を超える日々の中、熱戦が繰り広げられます。
つっこみタイプのX氏は、まずここに指摘を行いました。
「春季・秋季リーグ戦じゃなく、前期・後期リーグ戦に改めるべきだ」
早速始まったと思いつつ、私は「確かにそうですね」と相槌を打ちました。
少し前に2021年に新規採用された、いわゆるカラーラバーについてお話をしました。
今回は厳密には新色ラバーの話というわけではないのですが、関連する流れということで新色ラバーの第4回ということにさせていただきます。
──────────────────────
白いラバー
──────────────────────
ある日卓球初心者の女性Aさんとお相手する機会がありました。
その方とお話することで、卓球競技者は暗黙の常識に染まっていることを認識しました。
Aさんには卓球場にあるラバー貼りラケットを手渡しました。
ニッタクのシェークハンドラケットです。
しばらく打ちながら合間合間に卓球に関する問いかけがあり、それに私が答えていました。
突拍子もない質問(例:表ソフトとバタフライはどうちがうんですか?)は飛び出さず、ぽこぽこピン球を打ち合っていました。
ところが遂にハッとするクエスチョンがAさんから発せられました。
「なんでラケットの片面が黒なんですか」
私は両面同じ色のラバーが認められていた時代の出来事から説明をしようと考えました。
しかしAさんが疑問を持ったのは単純な色使いに関することだと分かりました。
最も地味な色でAさん的にはゴキ○○をイメージする黒をなぜ使っているのかという問いかけです。
普通(卓球しない人の普通)に考えると、赤と青などビビッドな色を使ったほうが楽しいというご指摘です。
「白はどう?」(いや、ピン球と同じ色なので…)
「両方赤でいいじゃない」
怒涛の質問攻めに遭いタジタジになりました。
今回は厳密には新色ラバーの話というわけではないのですが、関連する流れということで新色ラバーの第4回ということにさせていただきます。
──────────────────────
白いラバー
──────────────────────
ある日卓球初心者の女性Aさんとお相手する機会がありました。
その方とお話することで、卓球競技者は暗黙の常識に染まっていることを認識しました。
Aさんには卓球場にあるラバー貼りラケットを手渡しました。
ニッタクのシェークハンドラケットです。
しばらく打ちながら合間合間に卓球に関する問いかけがあり、それに私が答えていました。
突拍子もない質問(例:表ソフトとバタフライはどうちがうんですか?)は飛び出さず、ぽこぽこピン球を打ち合っていました。
ところが遂にハッとするクエスチョンがAさんから発せられました。
「なんでラケットの片面が黒なんですか」
私は両面同じ色のラバーが認められていた時代の出来事から説明をしようと考えました。
しかしAさんが疑問を持ったのは単純な色使いに関することだと分かりました。
最も地味な色でAさん的にはゴキ○○をイメージする黒をなぜ使っているのかという問いかけです。
普通(卓球しない人の普通)に考えると、赤と青などビビッドな色を使ったほうが楽しいというご指摘です。
「白はどう?」(いや、ピン球と同じ色なので…)
「両方赤でいいじゃない」
怒涛の質問攻めに遭いタジタジになりました。
2024 .08.17
オリンピックの感動の余韻が冷めやらぬ今、私の周囲でもまだ継続してこの話題が続いているため、引き続き関連する事柄について書いてみたいと思います。
──────────────────────
実況中継
──────────────────────
実況するアナウンサーが「卓球は9オールからとよく言われます」と語っていました。
えっ、そういうのってよく言われるんですか?
練習場で他の人にも尋ねてみました。
「聞いたことがない」
「卓球はラブオールからだよ」
「スレイバーにすれいば」なら何度か聞いたことがある。
放送局の前準備で、誰かが考えたこのフレーズを使うよう指示があったのではないでしょうか。
元になったのは「野球は2アウトから」ですね。
「卓球は9オール~」は疑問符でしたが、テレビ局のスタッフさんが努力されている点はいろいろな場面で解りました。
観客席にメダリストや選手のご家族がいればカンペを作っておき、画面切り替えでチラリと切り替わった瞬間、どういう方であるかが読み上げられていました。
民放の中継映像だと、選手名などの表示を日本語の上書き表示で自然に見せている工夫がありました。
他国の選手同士の対戦はTVerで見ることができ、とても満足できたという意見がありました。
──────────────────────
実況中継
──────────────────────
実況するアナウンサーが「卓球は9オールからとよく言われます」と語っていました。
えっ、そういうのってよく言われるんですか?
練習場で他の人にも尋ねてみました。
「聞いたことがない」
「卓球はラブオールからだよ」
「スレイバーにすれいば」なら何度か聞いたことがある。
放送局の前準備で、誰かが考えたこのフレーズを使うよう指示があったのではないでしょうか。
元になったのは「野球は2アウトから」ですね。
「卓球は9オール~」は疑問符でしたが、テレビ局のスタッフさんが努力されている点はいろいろな場面で解りました。
観客席にメダリストや選手のご家族がいればカンペを作っておき、画面切り替えでチラリと切り替わった瞬間、どういう方であるかが読み上げられていました。
民放の中継映像だと、選手名などの表示を日本語の上書き表示で自然に見せている工夫がありました。
他国の選手同士の対戦はTVerで見ることができ、とても満足できたという意見がありました。
2024 .08.03
前回に引き続き今回も新色ラバーについてお話しする予定でした。
しかしながらオリンピック開催中ということで練習仲間の間でいろいろな会話が交わされました。
そのためラバーの話は延期し、パリ五輪の内容に変更することにします。
いつものことながら試合結果や識者の分析など、普通の内容については大手メディアのほうを参照いただければと思います。
──────────────────────
演出効果
──────────────────────
練習場の雑談で出た意見としては、試合映像の合間に挿入される各種情報についてイイネとダメの評価がありました。
まずは悪い方から挙げると、卓球台を模したCGでどの位置にボールがバウンドしたかをドットをつけて分布図のように見せていました。
カメラ映像から瞬時に位置を割り出し、それをわかりやすく見せる今風のハイテク演出なのは理解できます。
普段卓球をしない一般の方なら、これは重要なデータでなんとなく凄そうと思うかもしれません。
しかしゲームの合間にあれを数秒間チラ見させただけでは、卓球競技者であってもそこから何かを読み取るのは困難です。
他にも何やら一覧表で表示されますが、同じく不要との厳しい意見がありました。
一方好意的な意見としては映画マトリックス風の3Dリプレイや、ボールの回転数表示を挙げた人がいました。
私としてはネットにかかったボールがギュルギュル回転している状態をズームアップ再生してくれたら、一般の方にも凄さが伝わるかなと思っています。
しかしながらオリンピック開催中ということで練習仲間の間でいろいろな会話が交わされました。
そのためラバーの話は延期し、パリ五輪の内容に変更することにします。
いつものことながら試合結果や識者の分析など、普通の内容については大手メディアのほうを参照いただければと思います。
──────────────────────
演出効果
──────────────────────
練習場の雑談で出た意見としては、試合映像の合間に挿入される各種情報についてイイネとダメの評価がありました。
まずは悪い方から挙げると、卓球台を模したCGでどの位置にボールがバウンドしたかをドットをつけて分布図のように見せていました。
カメラ映像から瞬時に位置を割り出し、それをわかりやすく見せる今風のハイテク演出なのは理解できます。
普段卓球をしない一般の方なら、これは重要なデータでなんとなく凄そうと思うかもしれません。
しかしゲームの合間にあれを数秒間チラ見させただけでは、卓球競技者であってもそこから何かを読み取るのは困難です。
他にも何やら一覧表で表示されますが、同じく不要との厳しい意見がありました。
一方好意的な意見としては映画マトリックス風の3Dリプレイや、ボールの回転数表示を挙げた人がいました。
私としてはネットにかかったボールがギュルギュル回転している状態をズームアップ再生してくれたら、一般の方にも凄さが伝わるかなと思っています。
ずっと前に新色のラバーについて2度触れたことがありました。
それを振り返りつつ、最近の私の周囲で見聞きしたことをご紹介いたします。
──────────────────────
1年遅れた採用時期
──────────────────────
2021年10月1日に新色ラバーが追加されました。
本来であればそれより1年前に実施されていたのですが、変更になった理由は新型コロナウイルスでした。
ITTF(国際卓球連盟)は東京オリンピックの後にこのルールを適用するという事前通知をしていました。
コロナでオリンピックが延期になったため、新色ラバーの販売も1年後ろへずれました。
これに関してはおそらく揉めたのではないかと考えています。
プレーに関係する変更ならオリンピックというビッグイベントを待つのは分かります。
でも新色を追加するだけなら五輪のプレー内容に何も影響はありません。
「オリンピック後」と発表した意味は、そこが節目になってちょうどいいよねということだったはずです。
1年も遅らせるのは準備をしていたメーカーの出鼻をくじいたと想像できます。
そして新色を心待ちにしていた卓球ファンはがっかりしたことでしょう。
やっと販売となりそれなりの年月が経過しました。
局所的な意見で恐縮ですが、私が出入りする練習場の新色ラバー状況をお伝えします。
それを振り返りつつ、最近の私の周囲で見聞きしたことをご紹介いたします。
──────────────────────
1年遅れた採用時期
──────────────────────
2021年10月1日に新色ラバーが追加されました。
本来であればそれより1年前に実施されていたのですが、変更になった理由は新型コロナウイルスでした。
ITTF(国際卓球連盟)は東京オリンピックの後にこのルールを適用するという事前通知をしていました。
コロナでオリンピックが延期になったため、新色ラバーの販売も1年後ろへずれました。
これに関してはおそらく揉めたのではないかと考えています。
プレーに関係する変更ならオリンピックというビッグイベントを待つのは分かります。
でも新色を追加するだけなら五輪のプレー内容に何も影響はありません。
「オリンピック後」と発表した意味は、そこが節目になってちょうどいいよねということだったはずです。
1年も遅らせるのは準備をしていたメーカーの出鼻をくじいたと想像できます。
そして新色を心待ちにしていた卓球ファンはがっかりしたことでしょう。
やっと販売となりそれなりの年月が経過しました。
局所的な意見で恐縮ですが、私が出入りする練習場の新色ラバー状況をお伝えします。
2024 .07.06
私は正式な試合にはあまり参加しませんが、巷の卓球場ではよく試合を行っています。
今回は最近私が試合をしたお相手や、その方たちとお話をした内容について書いてみたいと思います。
──────────────────────
前のめりな高校生
──────────────────────
A君はカットマンですが最近よくあるタイプで超攻撃的です。
そして自身の性格も多分に影響しており、とても強引なところがあります。
サーブ権があると必ず3球目攻撃を仕掛けるつもりで、構えた時点でギラギラオーラが半径5mに拡散しています。
フォア面は裏ソフト、バック面は粒高です。
従って回り込んで3球目をフォアで引っぱたく予定です。
私のほうはそれを100%承知しており、攻撃をさせないようバックの粒高側に返球します。
ところが勢いの止まらないA君は、これでもかと言わんばかりに回り込んできます。
バック側サイドを切る返球も打ってくるので、まるで昭和のペンドラ選手かと見まごうほどです。
A君とは過去にも複数回試合をしたことがありました。
そこで私は更なる対策としてバック前に短く落とすレシーブを加えました。
流石にそれは回り込んで打つことができず、バック面の粒高でカットし、そこから通常のカットマン的展開となっていました。
同じことをしようとしたのですが、A君は新たな対策をしてきました。
バック前の短いボールはラケットを反転させ、裏ソフトでフリックをしてくるようになったのです。
部活で毎日練習できる環境にあると新しいこともすぐ身につくのでしょうか。
少し話をしてみると、色んな技を取り入れたいと積極的な考えの若者であることが伝わってきました。
今回は最近私が試合をしたお相手や、その方たちとお話をした内容について書いてみたいと思います。
──────────────────────
前のめりな高校生
──────────────────────
A君はカットマンですが最近よくあるタイプで超攻撃的です。
そして自身の性格も多分に影響しており、とても強引なところがあります。
サーブ権があると必ず3球目攻撃を仕掛けるつもりで、構えた時点でギラギラオーラが半径5mに拡散しています。
フォア面は裏ソフト、バック面は粒高です。
従って回り込んで3球目をフォアで引っぱたく予定です。
私のほうはそれを100%承知しており、攻撃をさせないようバックの粒高側に返球します。
ところが勢いの止まらないA君は、これでもかと言わんばかりに回り込んできます。
バック側サイドを切る返球も打ってくるので、まるで昭和のペンドラ選手かと見まごうほどです。
A君とは過去にも複数回試合をしたことがありました。
そこで私は更なる対策としてバック前に短く落とすレシーブを加えました。
流石にそれは回り込んで打つことができず、バック面の粒高でカットし、そこから通常のカットマン的展開となっていました。
同じことをしようとしたのですが、A君は新たな対策をしてきました。
バック前の短いボールはラケットを反転させ、裏ソフトでフリックをしてくるようになったのです。
部活で毎日練習できる環境にあると新しいこともすぐ身につくのでしょうか。
少し話をしてみると、色んな技を取り入れたいと積極的な考えの若者であることが伝わってきました。
2024 .06.22
今回は最近私が指導員からいただいた、アドバイスのいくつかをご紹介したいと思います。
どれかはご自身にも当てはまるか、あるいは対戦相手を観察する際のヒントになるかもしれません。
──────────────────────
横回転流し打ち
──────────────────────
私は裏ソフトを貼っていますが、比較的パチパチ打って強打で決めに行く傾向があります。
フォアハンドで返す攻撃的なボールには、スマッシュ、ループドライブ、フラット打ちの比率が高く、普通のドライブは少なめです。
本人はラリー指向を意識していますが、傍から見た感じでは速攻タイプに映っています。
ある日、指導員からフラット打ちしている場面をもう少し工夫してはと言われました。
ラケットを立てた状態でそのまま打つのではなく、シュート回転で横に流す打ち方を増やしてはという助言です。
ボールをラバーにミートさせた状態で、真横にぬるっとこするのです。
強烈な横回転を与え相手を惑わす効果を期待しているわけではありません。
横にこする動作でボールを保持している感覚が生じ、フラット打ちよりも安定した球さばきとなります。
これがいわゆる「質の高いつなぎ球」なのかもしれません。
カットマンのカット返球にも似た感じの教え方があります。
切ったボールを送り出そうと前に押すスイングをしてはいけないそうです。
フォアカットであれバックカットであれ、体の遠い位置から体の側に向かって引き込む振りでボールをタッチすると上手くいくのです。
どれかはご自身にも当てはまるか、あるいは対戦相手を観察する際のヒントになるかもしれません。
──────────────────────
横回転流し打ち
──────────────────────
私は裏ソフトを貼っていますが、比較的パチパチ打って強打で決めに行く傾向があります。
フォアハンドで返す攻撃的なボールには、スマッシュ、ループドライブ、フラット打ちの比率が高く、普通のドライブは少なめです。
本人はラリー指向を意識していますが、傍から見た感じでは速攻タイプに映っています。
ある日、指導員からフラット打ちしている場面をもう少し工夫してはと言われました。
ラケットを立てた状態でそのまま打つのではなく、シュート回転で横に流す打ち方を増やしてはという助言です。
ボールをラバーにミートさせた状態で、真横にぬるっとこするのです。
強烈な横回転を与え相手を惑わす効果を期待しているわけではありません。
横にこする動作でボールを保持している感覚が生じ、フラット打ちよりも安定した球さばきとなります。
これがいわゆる「質の高いつなぎ球」なのかもしれません。
カットマンのカット返球にも似た感じの教え方があります。
切ったボールを送り出そうと前に押すスイングをしてはいけないそうです。
フォアカットであれバックカットであれ、体の遠い位置から体の側に向かって引き込む振りでボールをタッチすると上手くいくのです。
今回はあまり見かけないラケットの握り方についてお話しいたします。
私はこれまでにもユニークな用具や打法を色々試してみました。
やってみて自分なりに考えてみようとする気持ちが強めなのかなと思っています。
──────────────────────
ペンなのかシェークなのか
──────────────────────
VICTAS(ヴィクタス)のアドバイザリースタッフに小塩さん姉妹がいます。
妹の悠菜さんが独創的なラケットの握り方をしていて、私はそれを「皿づかみ」と勝手に命名しました。
使っているのはシェークハンドラケットで、フォアに表ソフト、バックに裏ソフトを貼っています。
フォア表というだけでかなり少数派の部類に入ります。
そしてなぜかそのラケットをペン持ちして使います。
更に異彩を放つのが、ペンホルダーなら表面に回すであろう人差し指を裏面側にしています。
つまりフォア面は親指のみで、バック面は4本の指を添えた握り方です。
これは果たしてペンホルダーの握りと言えるのでしょうか。
一応私なりの解釈では、グリップが手のひら側にあるのがシェークハンド、手の甲側にあるのがペンホルダーだと考えています。
従って変則的ではありますが、この「皿づかみ」はペンホルダー握りの亜種だと認識しています。
私はこれまでにもユニークな用具や打法を色々試してみました。
やってみて自分なりに考えてみようとする気持ちが強めなのかなと思っています。
──────────────────────
ペンなのかシェークなのか
──────────────────────
VICTAS(ヴィクタス)のアドバイザリースタッフに小塩さん姉妹がいます。
妹の悠菜さんが独創的なラケットの握り方をしていて、私はそれを「皿づかみ」と勝手に命名しました。
使っているのはシェークハンドラケットで、フォアに表ソフト、バックに裏ソフトを貼っています。
フォア表というだけでかなり少数派の部類に入ります。
そしてなぜかそのラケットをペン持ちして使います。
更に異彩を放つのが、ペンホルダーなら表面に回すであろう人差し指を裏面側にしています。
つまりフォア面は親指のみで、バック面は4本の指を添えた握り方です。
これは果たしてペンホルダーの握りと言えるのでしょうか。
一応私なりの解釈では、グリップが手のひら側にあるのがシェークハンド、手の甲側にあるのがペンホルダーだと考えています。
従って変則的ではありますが、この「皿づかみ」はペンホルダー握りの亜種だと認識しています。
2週に渡りお話ししてきました粒高ラバーですが、今回も実際に私が使ってみた感想をお届けします。
粒高使いのエキスパートの意見ではなく、ちょっと試してみようと思った粒初心者が感じるであろう共通の感想も一部含まれていると思います。
──────────────────────
お試し技術はマシン相手がベスト
──────────────────────
先ずは前回ご紹介した粒高ラバーの開祖、中国の張燮林(チャンシエリン)選手に倣いペンホルダーでのカットマンを試みました。
はるか昔にも少しだけやったことのある、スポンジのない粒高1枚ラバーでのペンカットです。
まずお相手いただくのは卓球マシンです。
最初は当然のことながら目も当てられない悲惨な返球となるので、相手をがっかりさせることなく、自分が申し訳ないと感じることもない相手は機械にするのが最善です。
初っ端はあり得ないリターンを数発放った後、そこそこ返せる感覚が分かりかけてきました。
フォアは思ったよりは順調で、続いて鬼門になるだろうと予想していたバックカットを試しました。
ちなみにここで試すバックカットは裏面を使うカットではなく、張選手と同じくフォア側と同じ表面の粒高を使います。
見事にメタメタで、フォアカットの時のようになかなか安定モードに入りません。
台の中に入れようという意識を強くするとスイングがどんどん小さくなり、胸の前でコンパクトに縦に撫ぜるだけの振りになってしまっていました。
これは恐らくほぼナックルボールで相手にとっては絶好球、加えて返球できる状況が極めて限定されてしまう悪例だと察知しました。
一旦中断しスマホで張選手の動画を確認しました。
一般的なシェークのカットマンは、フリーハンド側の肩の前方かつ、腰の高さで打球するのがベストの位置のようです。
張選手はそれよりももう少しだけ体の外側で、更に若干より前方でわずかに打点も低めのように見えました。
それをお手本にして続けるとややマシになりましたが、フォアカットくらいの安定性までには持っていけませんでした。
粒高使いのエキスパートの意見ではなく、ちょっと試してみようと思った粒初心者が感じるであろう共通の感想も一部含まれていると思います。
──────────────────────
お試し技術はマシン相手がベスト
──────────────────────
先ずは前回ご紹介した粒高ラバーの開祖、中国の張燮林(チャンシエリン)選手に倣いペンホルダーでのカットマンを試みました。
はるか昔にも少しだけやったことのある、スポンジのない粒高1枚ラバーでのペンカットです。
まずお相手いただくのは卓球マシンです。
最初は当然のことながら目も当てられない悲惨な返球となるので、相手をがっかりさせることなく、自分が申し訳ないと感じることもない相手は機械にするのが最善です。
初っ端はあり得ないリターンを数発放った後、そこそこ返せる感覚が分かりかけてきました。
フォアは思ったよりは順調で、続いて鬼門になるだろうと予想していたバックカットを試しました。
ちなみにここで試すバックカットは裏面を使うカットではなく、張選手と同じくフォア側と同じ表面の粒高を使います。
見事にメタメタで、フォアカットの時のようになかなか安定モードに入りません。
台の中に入れようという意識を強くするとスイングがどんどん小さくなり、胸の前でコンパクトに縦に撫ぜるだけの振りになってしまっていました。
これは恐らくほぼナックルボールで相手にとっては絶好球、加えて返球できる状況が極めて限定されてしまう悪例だと察知しました。
一旦中断しスマホで張選手の動画を確認しました。
一般的なシェークのカットマンは、フリーハンド側の肩の前方かつ、腰の高さで打球するのがベストの位置のようです。
張選手はそれよりももう少しだけ体の外側で、更に若干より前方でわずかに打点も低めのように見えました。
それをお手本にして続けるとややマシになりましたが、フォアカットくらいの安定性までには持っていけませんでした。
前回に引き続き魔球を放つ異色の卓球アイテム、粒高ラバーについてお話しいたします。
──────────────────────
粒高ラバーの開祖、張選手
──────────────────────
そもそも粒高ラバーというものが生まれた経緯はどのようなものだったのでしょうか。
それにはずっと前にもご紹介したことがある、中国の張燮林(チャンシエリン)という選手が大きく関係しています。
張選手は1950年代の末期、中国式ペンホルダーを使ったカットマンでした。
当時の中国はペンホルダーのカットマンもそれなりに存在し、スポンジのない1枚ラバーを使っている人が多かったそうです。
張選手は紅双喜というメーカーが廃棄する不良ラバーを入手し、それを使ってみました。
裏ソフトラバーに使われるはずだった若干粒が高めのゴムシートで、それを逆向きにして1枚ラバーとして貼ってみたのです。
今の粒高ほどの高い粒ではありませんでしたが、通常の1枚ラバーとは異なる特徴を見出しました。
まだ卓球界には粒高ラバーというジャンルが認知されていなかったこともあり、1960年代に入って張選手のミラクルボールは強力な武器となりました。
ちなみに張選手は中ペン(中国式ペンホルダー)を使うカットマンですが、バックカットは裏面を使うのではなく表面でカットしていました。
またカットの時は人差し指をラケットの裏面に回し、表面は親指だけという握りでした。
──────────────────────
粒高ラバーの開祖、張選手
──────────────────────
そもそも粒高ラバーというものが生まれた経緯はどのようなものだったのでしょうか。
それにはずっと前にもご紹介したことがある、中国の張燮林(チャンシエリン)という選手が大きく関係しています。
張選手は1950年代の末期、中国式ペンホルダーを使ったカットマンでした。
当時の中国はペンホルダーのカットマンもそれなりに存在し、スポンジのない1枚ラバーを使っている人が多かったそうです。
張選手は紅双喜というメーカーが廃棄する不良ラバーを入手し、それを使ってみました。
裏ソフトラバーに使われるはずだった若干粒が高めのゴムシートで、それを逆向きにして1枚ラバーとして貼ってみたのです。
今の粒高ほどの高い粒ではありませんでしたが、通常の1枚ラバーとは異なる特徴を見出しました。
まだ卓球界には粒高ラバーというジャンルが認知されていなかったこともあり、1960年代に入って張選手のミラクルボールは強力な武器となりました。
ちなみに張選手は中ペン(中国式ペンホルダー)を使うカットマンですが、バックカットは裏面を使うのではなく表面でカットしていました。
またカットの時は人差し指をラケットの裏面に回し、表面は親指だけという握りでした。
今回は卓球用具の中でも魔球製造機と呼ばれる、粒高ラバーについてお話しします。
異彩を放つラバーのためコアな愛好家がいらっしゃり、語りだすと止まらない人に何人か出会いました。
それら粒高マニアからいただいたご意見をご紹介します。
──────────────────────
特徴が出る形状や材質
──────────────────────
メーカー各社から様々な粒高ラバーが販売されています。
それぞれに個性があり、ざっとご説明すると以下のような部分に違いがあります。
1)粒の高さ:高いと変化幅が大きく、低いと安定性重視
2)粒の太さ:太いと安定性重視、細いと変化重視
3)粒の硬さ:硬いと攻撃向き、柔らかいと安定性重視
4)粒の形状:円柱形は変化重視、根本が台形だと安定性重視
5)粒の間隔:狭いと安定性重視、広いと変化重視
世間一般にはこのように言われています。
私も4番めまでは確かめるまでもない当然のことかなと思っています。
少し疑問に感じたのは5番目の粒の間隔についての違いです。
先日、打ち比べる機会があったので試してみました。
異彩を放つラバーのためコアな愛好家がいらっしゃり、語りだすと止まらない人に何人か出会いました。
それら粒高マニアからいただいたご意見をご紹介します。
──────────────────────
特徴が出る形状や材質
──────────────────────
メーカー各社から様々な粒高ラバーが販売されています。
それぞれに個性があり、ざっとご説明すると以下のような部分に違いがあります。
1)粒の高さ:高いと変化幅が大きく、低いと安定性重視
2)粒の太さ:太いと安定性重視、細いと変化重視
3)粒の硬さ:硬いと攻撃向き、柔らかいと安定性重視
4)粒の形状:円柱形は変化重視、根本が台形だと安定性重視
5)粒の間隔:狭いと安定性重視、広いと変化重視
世間一般にはこのように言われています。
私も4番めまでは確かめるまでもない当然のことかなと思っています。
少し疑問に感じたのは5番目の粒の間隔についての違いです。
先日、打ち比べる機会があったので試してみました。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。