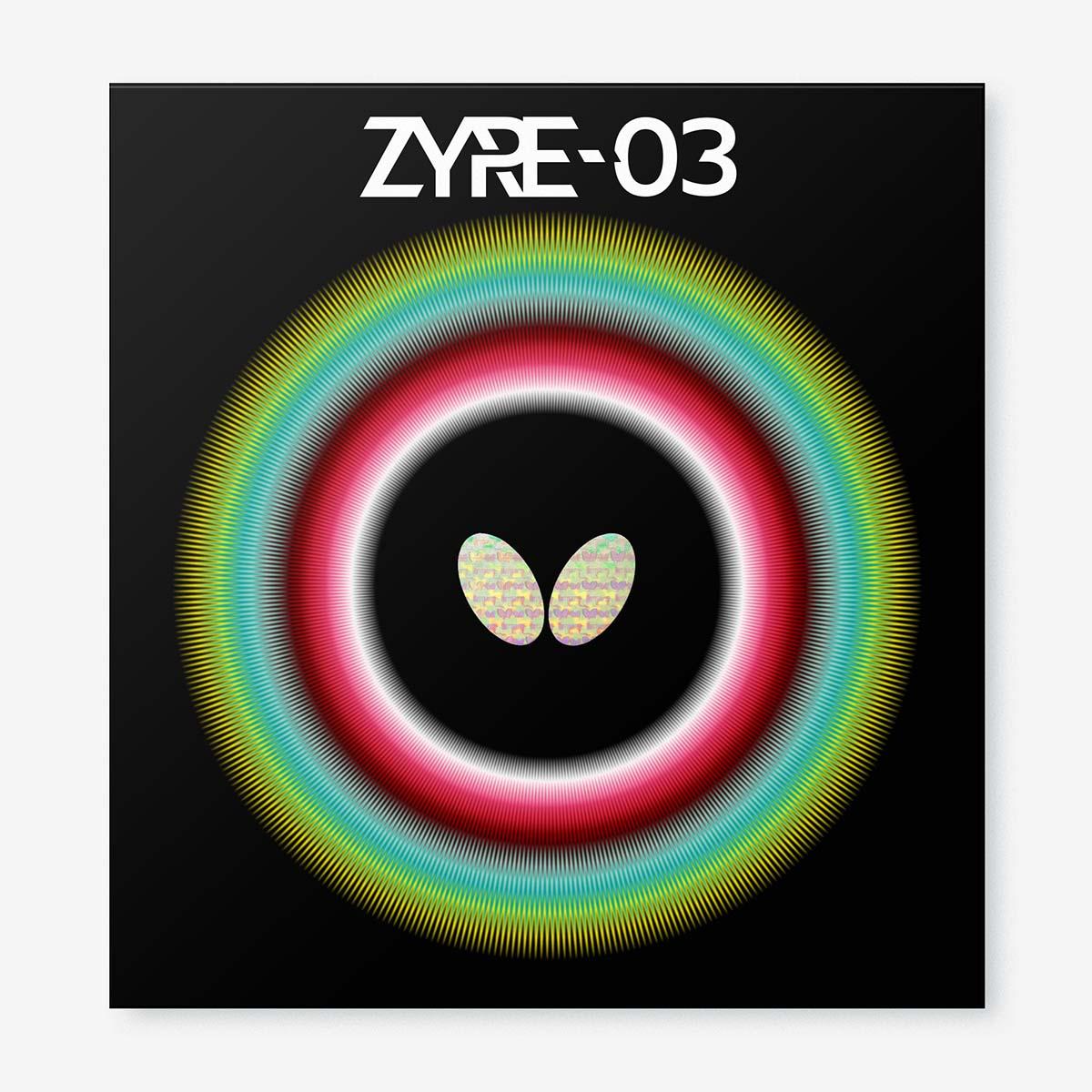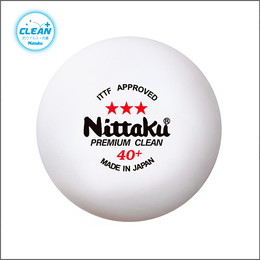今回はある若い方をご紹介いたします。
人物が特定されるのを避けるため、局所的に事実とは異なる内容に変えています。
──────────────────────
動きまくるカットマン
──────────────────────
飯田さん(仮名)は、20代の男性です。
フリーランスでお仕事をされていて、ロフト付きの賃貸ワンルームにお住まいです。
フットウェアには並々ならぬこだわりをお持ちです。
床はフローリングで、1年中ほぼ室内でも履物を履いて過ごしています。
夏は渓流の中も歩けるような特殊ソールのサンダルを、冬は防寒も兼ねてハイカットのバスケットボールシューズにしています。
卓球をする時は、ミッドカットのバッシュと決めています。
飯田さんの戦型はカットマンで、特殊素材入りのカット用ラケットに薄の裏ソフトと1枚ラバーの粒高を貼っています。
1枚の粒高は少し珍しく、台上は結構反転させて変化で惑わしてきます。
反転プレーを多用するには、カットマンに多いストレートグリップではなく、フレアのほうがいいそうです。
かなり動き回り、ノータッチで抜けそうなボールにも果敢に飛びつきます。
こういうスタイルにはバッシュが最適だというお考えです。
人物が特定されるのを避けるため、局所的に事実とは異なる内容に変えています。
──────────────────────
動きまくるカットマン
──────────────────────
飯田さん(仮名)は、20代の男性です。
フリーランスでお仕事をされていて、ロフト付きの賃貸ワンルームにお住まいです。
フットウェアには並々ならぬこだわりをお持ちです。
床はフローリングで、1年中ほぼ室内でも履物を履いて過ごしています。
夏は渓流の中も歩けるような特殊ソールのサンダルを、冬は防寒も兼ねてハイカットのバスケットボールシューズにしています。
卓球をする時は、ミッドカットのバッシュと決めています。
飯田さんの戦型はカットマンで、特殊素材入りのカット用ラケットに薄の裏ソフトと1枚ラバーの粒高を貼っています。
1枚の粒高は少し珍しく、台上は結構反転させて変化で惑わしてきます。
反転プレーを多用するには、カットマンに多いストレートグリップではなく、フレアのほうがいいそうです。
かなり動き回り、ノータッチで抜けそうなボールにも果敢に飛びつきます。
こういうスタイルにはバッシュが最適だというお考えです。
今回は、試合や練習をご一緒するお仲間の性格について書いてみます。
3つの例を取り上げてみました。
──────────────────────
イライラ型
──────────────────────
少しでもうまくいかないと、かんしゃくを起こしてしまう性格の人です。
某所で月に2~3回お会いする男性がそういう方でした。
ある日、今までとは違う銘柄のラバーに貼り替えたそうで、試合前の肩慣らしでは感触を確かめつつ、いい感じっぽい印象を持っているようでした。
ところが試合が始まると凡ミスが目立ちます。
当然ながらウォーミングアップのフォア打ちは単調な基本打法であり、打ちやすいボールを返してもらっている状況です。
一方の試合は短い下回転系のサーブから始まることが多く、それはできるだけ相手に打たせないようにしていることにほかなりません。
そのあたりも意識されているのかどうかは不明ですが、険しい表情をしてブツブツつぶやいています。
ラケットの縁に当たることも何度かありました。
それについてはラバーの違い云々よりも、時間ぎりぎりに到着し準備運動なども一切なしで、いきなりやり始めたことが主要因のように思えます。
イライラ男性が試行錯誤していることは伺え、相手コートにボールを置きにいく打ち方をしたり、逆に思い切って強打で返すのを試みていました。
しかしいずれもその男性が仕掛けていって自滅する流れでした。
うなったり自分を批判する言葉を発する気持ちは理解できます。
でも試合の相手をしている側としては、イヤーな気持ちになってしまいます。
線の細い人だと、自分が叱られているかのように感じてしまうかもしれません。
その時私は審判をしていたのですが、対戦相手はイライラ状態を気にせずポーカーフェイスでした。
そういう対応がベストですねと思っていると、マッチポイントを握った直後、イライラ男性のフォアへ高速ロングサーブを出しました。
鮮やかにノータッチで抜けていきました。
私は一瞬イライラ男性が切れてしまい、ラケットを床に叩きつけるようなことにでもなるかとヒヤッとしました。
怒りを爆発させることはなく「グッ」と低く声を出しただけでうなだれていました。
私ならそういう挑発的ともとれるロングサーブは、あの場面では出せないでしょうね。
3つの例を取り上げてみました。
──────────────────────
イライラ型
──────────────────────
少しでもうまくいかないと、かんしゃくを起こしてしまう性格の人です。
某所で月に2~3回お会いする男性がそういう方でした。
ある日、今までとは違う銘柄のラバーに貼り替えたそうで、試合前の肩慣らしでは感触を確かめつつ、いい感じっぽい印象を持っているようでした。
ところが試合が始まると凡ミスが目立ちます。
当然ながらウォーミングアップのフォア打ちは単調な基本打法であり、打ちやすいボールを返してもらっている状況です。
一方の試合は短い下回転系のサーブから始まることが多く、それはできるだけ相手に打たせないようにしていることにほかなりません。
そのあたりも意識されているのかどうかは不明ですが、険しい表情をしてブツブツつぶやいています。
ラケットの縁に当たることも何度かありました。
それについてはラバーの違い云々よりも、時間ぎりぎりに到着し準備運動なども一切なしで、いきなりやり始めたことが主要因のように思えます。
イライラ男性が試行錯誤していることは伺え、相手コートにボールを置きにいく打ち方をしたり、逆に思い切って強打で返すのを試みていました。
しかしいずれもその男性が仕掛けていって自滅する流れでした。
うなったり自分を批判する言葉を発する気持ちは理解できます。
でも試合の相手をしている側としては、イヤーな気持ちになってしまいます。
線の細い人だと、自分が叱られているかのように感じてしまうかもしれません。
その時私は審判をしていたのですが、対戦相手はイライラ状態を気にせずポーカーフェイスでした。
そういう対応がベストですねと思っていると、マッチポイントを握った直後、イライラ男性のフォアへ高速ロングサーブを出しました。
鮮やかにノータッチで抜けていきました。
私は一瞬イライラ男性が切れてしまい、ラケットを床に叩きつけるようなことにでもなるかとヒヤッとしました。
怒りを爆発させることはなく「グッ」と低く声を出しただけでうなだれていました。
私ならそういう挑発的ともとれるロングサーブは、あの場面では出せないでしょうね。
前回は実店舗での販売の様子をお伝えしました。
今回はネット上での通販について書いてみたいと思います。
──────────────────────
混沌とした通販サイト
──────────────────────
ネットショップに関してはずっと前にも取り上げたことはあります。
それは日本にあるお店でした。
今回は海外の通販サイトをご紹介します。
ご存じの方には今さらの感はありますが、とっても有名な、アリエクスプレス(Aliexpress)です。
わかりやすく例えると「中国製品がメインのアマゾン」みたいなところです。
何だか怪しそうと思う方もいらっしゃるでしょう。
それは否定しません。
アマゾンは監視が行き届き、変なものは概ね排除されています。
一方アリエクスプレスはかなり緩く、玉石混交のサイトと言えるでしょう。
トラブる確率はアマゾンよりは高めで、発送ミスや問い合わせに対する問題などいろいろなことがネット上に挙げられています。
クレジットカード決済のみで、商品到着まで時間がかかることが多いそうです。
そんなデメリットがあるのに、なぜ利用する人が多いのか。
それは当然のことながら、ちゃんとした商品でお買い得なものもたくさんあるからです。
不愉快なことは最小限に抑え、クレバーに利用することが肝要ということでしょうか。
さてそれでは、アリエクスプレスにある卓球用品を見ていきましょう。
今回はネット上での通販について書いてみたいと思います。
──────────────────────
混沌とした通販サイト
──────────────────────
ネットショップに関してはずっと前にも取り上げたことはあります。
それは日本にあるお店でした。
今回は海外の通販サイトをご紹介します。
ご存じの方には今さらの感はありますが、とっても有名な、アリエクスプレス(Aliexpress)です。
わかりやすく例えると「中国製品がメインのアマゾン」みたいなところです。
何だか怪しそうと思う方もいらっしゃるでしょう。
それは否定しません。
アマゾンは監視が行き届き、変なものは概ね排除されています。
一方アリエクスプレスはかなり緩く、玉石混交のサイトと言えるでしょう。
トラブる確率はアマゾンよりは高めで、発送ミスや問い合わせに対する問題などいろいろなことがネット上に挙げられています。
クレジットカード決済のみで、商品到着まで時間がかかることが多いそうです。
そんなデメリットがあるのに、なぜ利用する人が多いのか。
それは当然のことながら、ちゃんとした商品でお買い得なものもたくさんあるからです。
不愉快なことは最小限に抑え、クレバーに利用することが肝要ということでしょうか。
さてそれでは、アリエクスプレスにある卓球用品を見ていきましょう。
今回は新しくオープンしたお店について書いてみたいと思います。
──────────────────────
店舗概要
──────────────────────
場所は最高ににぎやかな新宿で、さらに駅からめっちゃ近いという超便利な立地です。
新宿駅東口から徒歩でわずか1分、歌舞伎町に向かう方向に新宿ユニカビルというのがあります。
地上8階地下2階の建物で、以前はヤマダ電機LAVI新宿東口館だったところです。
新宿には他にもヤマダ電機の大型店があり、複数存在するのはよろしくないという経営判断がくだされました。
営業を始めてから約10年という、やや早めの撤退でした。
一等地でこれだけ大規模な空き物件というのはめったにないことです。
ただその時期が微妙で、閉店したのは2020年10月4日でした。
コロナウイルス禍で、すぐにどこかの企業が入るのかはわかりかねる状況でした。
しばらくブランクがあった後、新しく入ることになったのは、アルペン系列のスポーツ・アウトドア用品店でした。
お店の名称は「Alpen TOKYO」で、オープンは今月の4月1日でした。
地下1階には、水泳、バレーボール、テニス、バドミントン、そして卓球関連の売り場があります。
──────────────────────
店舗概要
──────────────────────
場所は最高ににぎやかな新宿で、さらに駅からめっちゃ近いという超便利な立地です。
新宿駅東口から徒歩でわずか1分、歌舞伎町に向かう方向に新宿ユニカビルというのがあります。
地上8階地下2階の建物で、以前はヤマダ電機LAVI新宿東口館だったところです。
新宿には他にもヤマダ電機の大型店があり、複数存在するのはよろしくないという経営判断がくだされました。
営業を始めてから約10年という、やや早めの撤退でした。
一等地でこれだけ大規模な空き物件というのはめったにないことです。
ただその時期が微妙で、閉店したのは2020年10月4日でした。
コロナウイルス禍で、すぐにどこかの企業が入るのかはわかりかねる状況でした。
しばらくブランクがあった後、新しく入ることになったのは、アルペン系列のスポーツ・アウトドア用品店でした。
お店の名称は「Alpen TOKYO」で、オープンは今月の4月1日でした。
地下1階には、水泳、バレーボール、テニス、バドミントン、そして卓球関連の売り場があります。
2022 .04.02
ルールの改正などが行われれば、当然それらは競技者に直接影響が及びます。
しかしそれ以外にも世の中の情勢に応じ、私達の卓球ライフに変化をもたらすことはいろいろとあります。
最近の雑談の中で出た話題をご紹介いたします。
──────────────────────
円安が及ぼす影響
──────────────────────
現在数年ぶりの円安となっています。
輸出には好ましい一方で、輸入品にはこれまで以上の日本円を払うこととなります。
そのため海外メーカーの製品は値上げとなる可能性があります。
これについては脊髄反射的に拒絶反応を示すのではなく、ある程度はやむを得ないと思っている方がいました。
ただその方は電気やガス料金と同様、反対の円安に動けば値下げになるべきという、至極当然のお考えの人でした。
ところが過去に円安を理由に値上げを行ったものの、円高に転じても値下げはしないヨーロッパの某社を好ましく思っていませんでした。
まあ多くの方は基本的に値下げは期待しておらず、あきらめモードなのでしょう。
値下げは全く無いかといえばそうではなく、つい最近バタフライがラケットの値下げを行いました。
ビスカリアの上位モデルである、ビスカリアSUPER ALCが販売されたので、従来モデルの無印ビスカリアは3000円値下げされました。
これは好意的に受け入れられたかというと、恐らくそうではないでしょう。
ずっと前に税別10000円で販売されていたビスカリアを、25000円で再登場させた形なので、素直に喜べる人はいないと思います。
しかしそれ以外にも世の中の情勢に応じ、私達の卓球ライフに変化をもたらすことはいろいろとあります。
最近の雑談の中で出た話題をご紹介いたします。
──────────────────────
円安が及ぼす影響
──────────────────────
現在数年ぶりの円安となっています。
輸出には好ましい一方で、輸入品にはこれまで以上の日本円を払うこととなります。
そのため海外メーカーの製品は値上げとなる可能性があります。
これについては脊髄反射的に拒絶反応を示すのではなく、ある程度はやむを得ないと思っている方がいました。
ただその方は電気やガス料金と同様、反対の円安に動けば値下げになるべきという、至極当然のお考えの人でした。
ところが過去に円安を理由に値上げを行ったものの、円高に転じても値下げはしないヨーロッパの某社を好ましく思っていませんでした。
まあ多くの方は基本的に値下げは期待しておらず、あきらめモードなのでしょう。
値下げは全く無いかといえばそうではなく、つい最近バタフライがラケットの値下げを行いました。
ビスカリアの上位モデルである、ビスカリアSUPER ALCが販売されたので、従来モデルの無印ビスカリアは3000円値下げされました。
これは好意的に受け入れられたかというと、恐らくそうではないでしょう。
ずっと前に税別10000円で販売されていたビスカリアを、25000円で再登場させた形なので、素直に喜べる人はいないと思います。
2022 .03.19
新型コロナウイルスへの対策は、緩和の方向に向かいつつある気配が感じられます。
でもまだ出口は見えないというもどかしい状況です。
今回は卓球界における対応はどうなのかについて、私の意見を述べさせていただきます。
──────────────────────
飛沫の拡散防止に重点を置くべき
──────────────────────
まず、コロナ禍で開催されたオリンピックや全日本選手権を振り返ってみます。
台に落ちた汗は拭いてもらい、手のひらの汗を台でぬぐうのも禁止でした。
握手はせず、ボールは手袋をした審判から渡されました。
最高の舞台では厳格な対策が取られるべきという考えのように思えました。
個人的にはそれらの対応は、あまり意味をなさなかったのではと解釈しています。
やらないよりもやったほうが、感染リスクをより低減できることには同意します。
しかしもどかしさの見返りに得られる効果が、極めて低いと受け止めているのです。
今年の全日本では終盤に上位選手の棄権が続きました。
前述の対策を取っていてもそうなったので、もしそうでなかったらとお考えの人がいらっしゃるかもしれません。
でも棄権した選手は、別の場所でリスクのある状況下に置かれていたからではないでしょうか。
最も基本的で最大の注意を払うべきは、飛沫の拡散を防ぐことです。
その対策はしっかりと行い、それ以外は多大な手間やコストがかかるようであれば見合わせても良いのではないでしょうか。
選手は試合の時のみマスクを外すのを認める、点数コールはしない、などは妥当だと思います。
でもゲームの合間毎に台の拭き取りをするといった対策は、やらなくてもいいというか、まあ勇気を出して言うと、やめたらどうですか。
逆にかなり野放しになっていた、大声を出す行為を取り締まるべきです。
そして私としてこだわりたい点は、会場に入ってくる選手や関係者のマスクは不織布タイプのみを認め、布マスク等は不可にしてはと思います。
病院ではそうしているところが多いと聞いています。
ウイルスを正しく恐れ、現実的に取れる対策で科学的に効果が高いものは何なのか、合理的に優先度をつけて考えることが大切です。
でもまだ出口は見えないというもどかしい状況です。
今回は卓球界における対応はどうなのかについて、私の意見を述べさせていただきます。
──────────────────────
飛沫の拡散防止に重点を置くべき
──────────────────────
まず、コロナ禍で開催されたオリンピックや全日本選手権を振り返ってみます。
台に落ちた汗は拭いてもらい、手のひらの汗を台でぬぐうのも禁止でした。
握手はせず、ボールは手袋をした審判から渡されました。
最高の舞台では厳格な対策が取られるべきという考えのように思えました。
個人的にはそれらの対応は、あまり意味をなさなかったのではと解釈しています。
やらないよりもやったほうが、感染リスクをより低減できることには同意します。
しかしもどかしさの見返りに得られる効果が、極めて低いと受け止めているのです。
今年の全日本では終盤に上位選手の棄権が続きました。
前述の対策を取っていてもそうなったので、もしそうでなかったらとお考えの人がいらっしゃるかもしれません。
でも棄権した選手は、別の場所でリスクのある状況下に置かれていたからではないでしょうか。
最も基本的で最大の注意を払うべきは、飛沫の拡散を防ぐことです。
その対策はしっかりと行い、それ以外は多大な手間やコストがかかるようであれば見合わせても良いのではないでしょうか。
選手は試合の時のみマスクを外すのを認める、点数コールはしない、などは妥当だと思います。
でもゲームの合間毎に台の拭き取りをするといった対策は、やらなくてもいいというか、まあ勇気を出して言うと、やめたらどうですか。
逆にかなり野放しになっていた、大声を出す行為を取り締まるべきです。
そして私としてこだわりたい点は、会場に入ってくる選手や関係者のマスクは不織布タイプのみを認め、布マスク等は不可にしてはと思います。
病院ではそうしているところが多いと聞いています。
ウイルスを正しく恐れ、現実的に取れる対策で科学的に効果が高いものは何なのか、合理的に優先度をつけて考えることが大切です。
今回も特定の人物に焦点を当ててみたいと思います。
何かに対する感度は、通常レベルより高い人と低い人が正規分布のグラフを描いて存在します。
一般に、高いゾーンにいる人を取り上げたほうが面白いため、今回もそうしたいと思います。
──────────────────────
エコな卓球ライフ
──────────────────────
ももさん(仮名)は、20代の女性です。
何年か前に彼女は断捨離の考えに触れ、コロナ禍の状況でそれをどんどん推し進めるようになったと語ってくれました。
ユニフォームは色違いが2着あれば十分で、通常の練習はTシャツで構いません。
そのため他は古着店で売却しました。
卓球ユニフォームとしての付加価値をつけてもらえるはずはなく、普通の夏物衣料としてでした。
JTTAの承認タグがついているので、できれば卓球関係者の手に渡ってもらいたいですね。
6本持っていたラケットは2本に絞りました。
程度の良いものはフリマアプリで売却し、そうでないものは卓球場に寄贈しました。
残した2本はどちらもいただきもので、ヨーラ社のクールとジュウイック社のエアテクサという10数年前の製品でした。
かなり分厚くて、こういうタイプは現在あまりありません。
彼女のお気に入りは世間では少数派のため、貴重な2本です。
何かに対する感度は、通常レベルより高い人と低い人が正規分布のグラフを描いて存在します。
一般に、高いゾーンにいる人を取り上げたほうが面白いため、今回もそうしたいと思います。
──────────────────────
エコな卓球ライフ
──────────────────────
ももさん(仮名)は、20代の女性です。
何年か前に彼女は断捨離の考えに触れ、コロナ禍の状況でそれをどんどん推し進めるようになったと語ってくれました。
ユニフォームは色違いが2着あれば十分で、通常の練習はTシャツで構いません。
そのため他は古着店で売却しました。
卓球ユニフォームとしての付加価値をつけてもらえるはずはなく、普通の夏物衣料としてでした。
JTTAの承認タグがついているので、できれば卓球関係者の手に渡ってもらいたいですね。
6本持っていたラケットは2本に絞りました。
程度の良いものはフリマアプリで売却し、そうでないものは卓球場に寄贈しました。
残した2本はどちらもいただきもので、ヨーラ社のクールとジュウイック社のエアテクサという10数年前の製品でした。
かなり分厚くて、こういうタイプは現在あまりありません。
彼女のお気に入りは世間では少数派のため、貴重な2本です。
全日本選手権は結構な数の棄権が出ながらも、なんとか終了しました。
全種目が概ねスケジュール通り行われ、観客を入れての開催もできました。
ただ関係者の気持ちとしては、ほっとしたというより大変厳しかったというのが正直な感想だったのではと推測します。
有力選手の感染が終盤になって続き、ギリギリの状況だったためです。
それ以降の主要な大会は、東京大会を始め多くが中止になってしまいました。
より小規模の試合も同じで、春の学生リーグにも暗雲が立ち込めています。
さて、前置きとは全く別の話となりますが、ラバーに新色が追加されてからそれなりの月日が経過しました。
今回はそれに関してお話ししたいと思います。
──────────────────────
色々なご意見
──────────────────────
私もピンク、緑、青の3色は実際に使っている方を見かけました。
あるシニアの男性のご意見は、青の表ソフトを出してもらいたいとのことでした。
ラバーの色の規制が緩やかだった昔、世界を席巻していた中国の前陣速攻型の選手が青い表ソフトラバーを使っていて、懐かしい思い出があるのだそうです。
1つ残念なことは、仮に今どこかのメーカーが製品化しても、昔のイメージをそっくり再現できない点です。
かつての青い表ソフトは本当の青で、現在認められているのは水色に近い淡い青です。
その方は新色に紫も認めたため、青はそれとは明らかに異なる水色にされてしまったのだろうとお怒りでした。
紫が採用されたことに異議を唱える人は他にもいらっしゃいました。
紫はボツにして、片面に必須の色である黒とのコントラストが明確な黄色を採用して欲しかったというご意見です。
なるほどそのお考えは十分にわかります。
私も黒と黄色は素敵だと思います。
しかしボールの色としてオレンジがまだ認められているため、黄色の採用は難しいのだと思います。
黄色のラバーを採用して、ボールは白のみに変更する案は無理だったんでしょうか。
全種目が概ねスケジュール通り行われ、観客を入れての開催もできました。
ただ関係者の気持ちとしては、ほっとしたというより大変厳しかったというのが正直な感想だったのではと推測します。
有力選手の感染が終盤になって続き、ギリギリの状況だったためです。
それ以降の主要な大会は、東京大会を始め多くが中止になってしまいました。
より小規模の試合も同じで、春の学生リーグにも暗雲が立ち込めています。
さて、前置きとは全く別の話となりますが、ラバーに新色が追加されてからそれなりの月日が経過しました。
今回はそれに関してお話ししたいと思います。
──────────────────────
色々なご意見
──────────────────────
私もピンク、緑、青の3色は実際に使っている方を見かけました。
あるシニアの男性のご意見は、青の表ソフトを出してもらいたいとのことでした。
ラバーの色の規制が緩やかだった昔、世界を席巻していた中国の前陣速攻型の選手が青い表ソフトラバーを使っていて、懐かしい思い出があるのだそうです。
1つ残念なことは、仮に今どこかのメーカーが製品化しても、昔のイメージをそっくり再現できない点です。
かつての青い表ソフトは本当の青で、現在認められているのは水色に近い淡い青です。
その方は新色に紫も認めたため、青はそれとは明らかに異なる水色にされてしまったのだろうとお怒りでした。
紫が採用されたことに異議を唱える人は他にもいらっしゃいました。
紫はボツにして、片面に必須の色である黒とのコントラストが明確な黄色を採用して欲しかったというご意見です。
なるほどそのお考えは十分にわかります。
私も黒と黄色は素敵だと思います。
しかしボールの色としてオレンジがまだ認められているため、黄色の採用は難しいのだと思います。
黄色のラバーを採用して、ボールは白のみに変更する案は無理だったんでしょうか。
今回は、物事は感情に左右されず客観的に判断しましょうと説く方をご紹介します。
畑さん(仮名)は、60歳くらいと思われる男性です。
某所の卓球場の休憩時間に、ふとした雑談を交わしたのがきっかけでした。
常日頃ご自身が思っていることがあり、それを私に感情を込めず淡々と語ってくれました。
──────────────────────
女子ダブルス決勝(2019,2021)
──────────────────────
主な内容は2つで、まず1つめは世界選手権の女子ダブルスの話でした。
2019年の決勝戦は、日本の伊藤+早田ペア対、中国の王+孫ペアの対戦でした。
終盤に日本側が出したサーブを中国側が返せませんでした。
しかしそのサーブはネットに触れていたため、無効であるという異議が出され揉めました。
映像を見るとネットにはかすりもしていませんでしたが、ネットに触れたと判定されやり直しとなりました。
そして試合は中国側の勝利となりました。
昨年の世界卓球2021の決勝も同じ対戦となりました。
テレビ東京は不本意な前回の判定を何度も取り上げ、リベンジを願う報じ方をしていました。
これについて畑さんはずっと違和感を感じていたそうです。
ある日ほげ~っとした表情で聞いてくれそうに見えた私に出会い、溜まっていた思いを吐き出したようでした。
あのテレ東の報道は恥ずかしいと冷ややかでした。
視聴者が感情移入し、応援しようと見てくれれば視聴率は上がります。
そのための誘導は半分理解でき、半分うんざりするというご意見でした。
それはそれで割り切って考えることとしたそうです。
次に最も良くない点の核心部分になりました。
ミスジャッジが、試合の勝敗の大部分を決めるかのような印象操作になってしまっているというご指摘です。
確かにあれは重要な局面で重要な意味合いを持つことは認めます。
でもそれ以外に、この場面でこうしていればと振り返ると、思い当たることはいくつもあるものです。
将棋の対局などでは、1つのミスで完全に形勢逆転してしまうということはあり得ます。
しかし卓球はそうではなく、重要なポイントが要所要所にあり、それらが積み重なって試合の結果が決まるのが普通です。
私は念のため日本に1点入ったあとの展開と、無効になったときでは取れる戦術は違ってくるのではと畑さんに問いかけてみました。
お答えは、それは考慮に入れた上でもあの判定ミスを過大に取り上げすぎ、とのことでした。
畑さん(仮名)は、60歳くらいと思われる男性です。
某所の卓球場の休憩時間に、ふとした雑談を交わしたのがきっかけでした。
常日頃ご自身が思っていることがあり、それを私に感情を込めず淡々と語ってくれました。
──────────────────────
女子ダブルス決勝(2019,2021)
──────────────────────
主な内容は2つで、まず1つめは世界選手権の女子ダブルスの話でした。
2019年の決勝戦は、日本の伊藤+早田ペア対、中国の王+孫ペアの対戦でした。
終盤に日本側が出したサーブを中国側が返せませんでした。
しかしそのサーブはネットに触れていたため、無効であるという異議が出され揉めました。
映像を見るとネットにはかすりもしていませんでしたが、ネットに触れたと判定されやり直しとなりました。
そして試合は中国側の勝利となりました。
昨年の世界卓球2021の決勝も同じ対戦となりました。
テレビ東京は不本意な前回の判定を何度も取り上げ、リベンジを願う報じ方をしていました。
これについて畑さんはずっと違和感を感じていたそうです。
ある日ほげ~っとした表情で聞いてくれそうに見えた私に出会い、溜まっていた思いを吐き出したようでした。
あのテレ東の報道は恥ずかしいと冷ややかでした。
視聴者が感情移入し、応援しようと見てくれれば視聴率は上がります。
そのための誘導は半分理解でき、半分うんざりするというご意見でした。
それはそれで割り切って考えることとしたそうです。
次に最も良くない点の核心部分になりました。
ミスジャッジが、試合の勝敗の大部分を決めるかのような印象操作になってしまっているというご指摘です。
確かにあれは重要な局面で重要な意味合いを持つことは認めます。
でもそれ以外に、この場面でこうしていればと振り返ると、思い当たることはいくつもあるものです。
将棋の対局などでは、1つのミスで完全に形勢逆転してしまうということはあり得ます。
しかし卓球はそうではなく、重要なポイントが要所要所にあり、それらが積み重なって試合の結果が決まるのが普通です。
私は念のため日本に1点入ったあとの展開と、無効になったときでは取れる戦術は違ってくるのではと畑さんに問いかけてみました。
お答えは、それは考慮に入れた上でもあの判定ミスを過大に取り上げすぎ、とのことでした。
1年で最も寒い時期に突入しましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
今回はもう定番ネタとなってしまった、巷の愛好家の方にスポットを当ててみたいと思います。
──────────────────────
硬派なドライブマン
──────────────────────
山崎さん(仮名)は、40歳くらいの男性です。
ヤサカの馬琳ハードカーボンという中ペン(中国式ペンホルダー)を使っています。
ラバーはオモテ面に私が知らない銘柄の中国粘着ラバーを貼っていて、ウラ面はバタフライのロゼナです。
かなり重めのラケットで、加えてその両面に分厚いラバーを貼っているため私には扱えない代物です。
筋トレで鍛え重い用具を使うという考えと、そこから逃避して軽い用具を選ぶという2つの選択肢があります。
ストイックな山崎さんは前者を、ヘタレの私は後者を選んでいます。
山崎さんは回転重視のプレーで、普通ならスマッシュを打っても良さそうな場面でもう一発パワードライブを叩き込みます。
短時間ですが平日は自宅で筋トレを行い、週末の卓球場ではフットワークなど体に負担のかかる練習をして自分を追い込みます。
普段はほぼデスクワークのため、なまった体に活を入れているそうです。
フォア面に貼った中国粘着ラバーは黒で、山崎さん曰く「やっぱり黒のほうが回転がかかっていいね」とおっしゃっていました。
色による性能差はないというのがメーカーの見解です。
しかし赤よりも黒のほうが高性能と考えている方は一定数いて、山崎さんもその一人でした。
私はメーカーの説明を100%信じていますが、それを受け入れない人もいるということに理解を示す立場です。
今回はもう定番ネタとなってしまった、巷の愛好家の方にスポットを当ててみたいと思います。
──────────────────────
硬派なドライブマン
──────────────────────
山崎さん(仮名)は、40歳くらいの男性です。
ヤサカの馬琳ハードカーボンという中ペン(中国式ペンホルダー)を使っています。
ラバーはオモテ面に私が知らない銘柄の中国粘着ラバーを貼っていて、ウラ面はバタフライのロゼナです。
かなり重めのラケットで、加えてその両面に分厚いラバーを貼っているため私には扱えない代物です。
筋トレで鍛え重い用具を使うという考えと、そこから逃避して軽い用具を選ぶという2つの選択肢があります。
ストイックな山崎さんは前者を、ヘタレの私は後者を選んでいます。
山崎さんは回転重視のプレーで、普通ならスマッシュを打っても良さそうな場面でもう一発パワードライブを叩き込みます。
短時間ですが平日は自宅で筋トレを行い、週末の卓球場ではフットワークなど体に負担のかかる練習をして自分を追い込みます。
普段はほぼデスクワークのため、なまった体に活を入れているそうです。
フォア面に貼った中国粘着ラバーは黒で、山崎さん曰く「やっぱり黒のほうが回転がかかっていいね」とおっしゃっていました。
色による性能差はないというのがメーカーの見解です。
しかし赤よりも黒のほうが高性能と考えている方は一定数いて、山崎さんもその一人でした。
私はメーカーの説明を100%信じていますが、それを受け入れない人もいるということに理解を示す立場です。
2022 .01.08
新型コロナウイルスの状況は、依然として世界的に厳しい状態が続いています。
我が国も爆発的な第6波に見舞われようとしています。
そのような困難な状況の中、2022年の全日本選手権が開催されます。
──────────────────────
フル開催+観客
──────────────────────
東京オリンピックとの関係で、2020年、2021年の全日本は大阪で開催されました。
今回は2年ぶりに東京体育館に戻ってきました。
開催期間は1月24日(月)~30日(日)です。
前回大会は感染防止のため、1)シングルスのみの実施、2)リモートマッチ(無観客試合)という、これまで経験したことのない制限下で行われました。
今回は、1)従来どおり全種目の実施、2)最後の2日間に限り観客を入れて実施、となりました。
1)の全種目とは具体的に挙げると、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス、ジュニアの男女シングルスです。
ダブルスを行うと来場する選手の数が増えますし、ペアを組んだ選手同士は至近距離でプレーすることになります。
前回はそのような理由もあって見送られたのでしょう。
全種目を実施できる規模の立派な会場だったのに、シングルスだけでしかも観客がいなかった大阪市中央体育館は寂しい限りでした。
2)の有観客での実施については、当初無観客で行う予定だったのが変更されて実現しました。
全試合リモートマッチにしてしまえば、感染予防に対する安全性がより高くなるのは紛れもない事実です。
事なかれ主義で考えれば「観客を入れては」という要望があっても、今なら「コロナ対策」という強力な理由で拒絶することが簡単にできてしまいます。
それを覆し、2日間だけですが観客を受け入れることにした判断や努力には、並々ならぬものがあったのだと想像します。
我が国も爆発的な第6波に見舞われようとしています。
そのような困難な状況の中、2022年の全日本選手権が開催されます。
──────────────────────
フル開催+観客
──────────────────────
東京オリンピックとの関係で、2020年、2021年の全日本は大阪で開催されました。
今回は2年ぶりに東京体育館に戻ってきました。
開催期間は1月24日(月)~30日(日)です。
前回大会は感染防止のため、1)シングルスのみの実施、2)リモートマッチ(無観客試合)という、これまで経験したことのない制限下で行われました。
今回は、1)従来どおり全種目の実施、2)最後の2日間に限り観客を入れて実施、となりました。
1)の全種目とは具体的に挙げると、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス、ジュニアの男女シングルスです。
ダブルスを行うと来場する選手の数が増えますし、ペアを組んだ選手同士は至近距離でプレーすることになります。
前回はそのような理由もあって見送られたのでしょう。
全種目を実施できる規模の立派な会場だったのに、シングルスだけでしかも観客がいなかった大阪市中央体育館は寂しい限りでした。
2)の有観客での実施については、当初無観客で行う予定だったのが変更されて実現しました。
全試合リモートマッチにしてしまえば、感染予防に対する安全性がより高くなるのは紛れもない事実です。
事なかれ主義で考えれば「観客を入れては」という要望があっても、今なら「コロナ対策」という強力な理由で拒絶することが簡単にできてしまいます。
それを覆し、2日間だけですが観客を受け入れることにした判断や努力には、並々ならぬものがあったのだと想像します。
卓球をお気軽な運動不足解消の場と捉えているような人だと、試合や練習をしても正直やりっぱなし、一時的な思い出で終わってしまうことも多いでしょう。
今回はそうではなく毎回パソコンで記録している人についてお話ししたいと思います。
──────────────────────
記録に至った流れ
──────────────────────
加藤さん(仮名)は40歳くらいの男性で、週イチで卓球をする愛好家です。
仕事や日常の生活でちょっとしたことを書き留めていたことを、パソコンに入力してざっと見返していました。
別段強く意識することもなく、それを卓球についても自然に行うようになりました。
大昔、部活でやっていたときは、合宿の際、練習内容をノートに取ったり目標を壁に貼ったりと文字で書き記したことは時たまありました。
しかしそれは技術面についてのことがほとんどでかつ、やらされ感が強いものでした。
愛好家レベルの卓球ライフとなった今、練習内容はゆるく、緊張感もほとんどありません。
その反面、いろんな視点で広く観察できるような精神的余裕が生まれました。
最初は毎回の練習で備忘録としてメモをしていました。
それが戦術だけでなく、一緒に練習する人や卓球場の設備、そこに行くまでの効率的な移動方法など、種々雑多なことを記録するように変わっていきました。
ごった煮風味の日記のような感じです。
今回はそうではなく毎回パソコンで記録している人についてお話ししたいと思います。
──────────────────────
記録に至った流れ
──────────────────────
加藤さん(仮名)は40歳くらいの男性で、週イチで卓球をする愛好家です。
仕事や日常の生活でちょっとしたことを書き留めていたことを、パソコンに入力してざっと見返していました。
別段強く意識することもなく、それを卓球についても自然に行うようになりました。
大昔、部活でやっていたときは、合宿の際、練習内容をノートに取ったり目標を壁に貼ったりと文字で書き記したことは時たまありました。
しかしそれは技術面についてのことがほとんどでかつ、やらされ感が強いものでした。
愛好家レベルの卓球ライフとなった今、練習内容はゆるく、緊張感もほとんどありません。
その反面、いろんな視点で広く観察できるような精神的余裕が生まれました。
最初は毎回の練習で備忘録としてメモをしていました。
それが戦術だけでなく、一緒に練習する人や卓球場の設備、そこに行くまでの効率的な移動方法など、種々雑多なことを記録するように変わっていきました。
ごった煮風味の日記のような感じです。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。