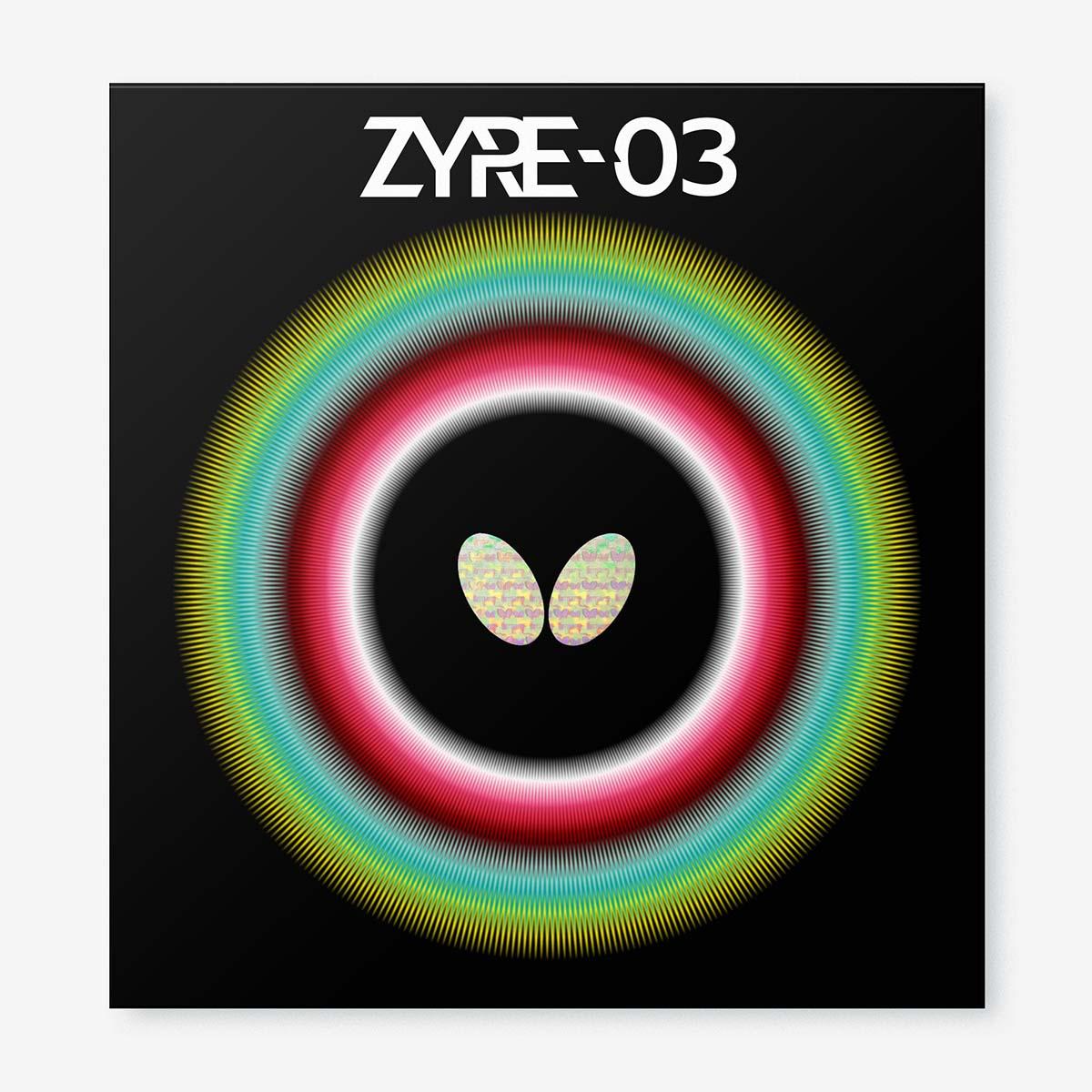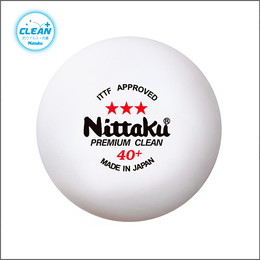2020 .02.08
前回に引き続き、大阪へ全日本選手権を見に行ったD氏のレポートをお届けします。
今回は脱線の度合いが著しく、もう試合そのものとは関係ない内容であることを最初にお断りしておきます。
──────────────────────
DONICブース
──────────────────────
会場は半分地下に埋まっている構造で、野球場のようにアリーナ周囲をぐるっと取り囲む形で通路が配されています。
いつものようにその通路にメーカー各社が販売所を設けていました。
今年の干支であるネズミのイラストや、この大会オリジナルのデザインを施したTシャツなどがイチオシのようでしたが、D氏はその手の商品には全く興味がありませんでした。
まず目に止まったのはDONICでした。
B級品ラケットなる表示があり、新品なのに3000円という激安価格がついていました。
B級品ということは、どこかに傷があるなど何らかの不具合を抱えていそうです。
D氏はお店の人に質問してみました。
返ってきた返事は問題があるからではなく、仕様変更などが理由で品質や外観についてはちゃんとした製品であるとのお答えでした。
D氏はこれにときめき、どれか購入してしまいそうになりました。
PayPayで支払える点も魅力的でした。
ヤフオクで溜まった売上金を利用できるからです。
結局購入は見送りましたが、それはグリップ形状がマイナーなアナトミックだった点で、フレアなら迷わず買っていたそうです。
今回は脱線の度合いが著しく、もう試合そのものとは関係ない内容であることを最初にお断りしておきます。
──────────────────────
DONICブース
──────────────────────
会場は半分地下に埋まっている構造で、野球場のようにアリーナ周囲をぐるっと取り囲む形で通路が配されています。
いつものようにその通路にメーカー各社が販売所を設けていました。
今年の干支であるネズミのイラストや、この大会オリジナルのデザインを施したTシャツなどがイチオシのようでしたが、D氏はその手の商品には全く興味がありませんでした。
まず目に止まったのはDONICでした。
B級品ラケットなる表示があり、新品なのに3000円という激安価格がついていました。
B級品ということは、どこかに傷があるなど何らかの不具合を抱えていそうです。
D氏はお店の人に質問してみました。
返ってきた返事は問題があるからではなく、仕様変更などが理由で品質や外観についてはちゃんとした製品であるとのお答えでした。
D氏はこれにときめき、どれか購入してしまいそうになりました。
PayPayで支払える点も魅力的でした。
ヤフオクで溜まった売上金を利用できるからです。
結局購入は見送りましたが、それはグリップ形状がマイナーなアナトミックだった点で、フレアなら迷わず買っていたそうです。
2020 .01.25
大阪で行われていた全日本選手権についてお話したいと思います。
正確に言うと、全日本選手権を見に行った人がそれに関することがらを勝手気ままに話してくれた内容です。
試合のちゃんとしたレポートを期待されると肩透かしを喰らいますので、ご理解くださるようお願いいたします。
──────────────────────
改元を機にわかりやすい名称へ
──────────────────────
今回も昨年と同様、大阪への出張をうまく利用して観戦してきたD氏のレポートをお届けいたします。
話の出だしは大会の名前に関することでした。
前回までは和暦かつ年度を冠した大会名でした。
例えば平成31年の1月に行われる試合は「平成30年度全日本卓球選手権大会」となっていて、ややこしい感は否めませんでした。
元号の変更をきっかけに、西暦かつ年度ではない大会名に変更されたのは良かったとのご意見です。
従来の名称を踏襲すると「令和元年度全日本」になっていたはずで、聞いた途端、眉間にシワが寄りそうな違和感を覚えます。
2020年度全日本に切り替えた英断を私も評価したいと思います。
正確に言うと、全日本選手権を見に行った人がそれに関することがらを勝手気ままに話してくれた内容です。
試合のちゃんとしたレポートを期待されると肩透かしを喰らいますので、ご理解くださるようお願いいたします。
──────────────────────
改元を機にわかりやすい名称へ
──────────────────────
今回も昨年と同様、大阪への出張をうまく利用して観戦してきたD氏のレポートをお届けいたします。
話の出だしは大会の名前に関することでした。
前回までは和暦かつ年度を冠した大会名でした。
例えば平成31年の1月に行われる試合は「平成30年度全日本卓球選手権大会」となっていて、ややこしい感は否めませんでした。
元号の変更をきっかけに、西暦かつ年度ではない大会名に変更されたのは良かったとのご意見です。
従来の名称を踏襲すると「令和元年度全日本」になっていたはずで、聞いた途端、眉間にシワが寄りそうな違和感を覚えます。
2020年度全日本に切り替えた英断を私も評価したいと思います。
昨年末の忘年会でいろいろな話題が飛び交いました。
失敗にまつわる話がそれなりにあったので、内4つをまとめてご紹介します。
──────────────────────
注意が必要な接着シート
──────────────────────
ラバーを貼るには接着剤を用いる場合と接着シートを使う場合があります。
ほとんどの人は接着剤であり、接着シートはスポンジのないラバーにあらかじめ貼ってあるものを利用するケースがほとんどだと思います。
従って接着シート単品を買い求める人は大変まれです。
Aさんはそんな接着シートを買った一人でした。
ただし当初はラバーをラケットに貼り付けるつもりで買ったのではありませんでした。
裏ソフトラバーの表面を保護するシートと間違って買ってしまったのです。
このまま捨てるのは悔しいためカーペットのホコリ取りとして利用した後、捨てようかと考えました。
いやそれはかなりもったいないと思い、次のラバーを貼るときに使うこととしました。
使用感は接着剤とそれほど違いを感じませんでした。
さらに次のラバーに貼り替える際、問題が生じました。
接着シートの粘着物質がラケット表面に残ったままとなったのです。
そのままラバーを貼っても接着できそうで、その反面剥がれてしまいそうにも思えました。
液体の接着剤を試しに少しだけ上塗りしてみました。
ラケットの表面がより汚くなってしまいました。
5分間悩んだ末、Aさんはラケットを持って東急ハンズに向かいました。
店員さんに助けを求め、適切なネバネバ除去剤を選んでもらいました。
ほぼ満足のいく修復ができ、Aさんはほっとしました。
接着シートは繰り返し接着シートで貼る場合に使うべきだということを教訓として学びました。
失敗にまつわる話がそれなりにあったので、内4つをまとめてご紹介します。
──────────────────────
注意が必要な接着シート
──────────────────────
ラバーを貼るには接着剤を用いる場合と接着シートを使う場合があります。
ほとんどの人は接着剤であり、接着シートはスポンジのないラバーにあらかじめ貼ってあるものを利用するケースがほとんどだと思います。
従って接着シート単品を買い求める人は大変まれです。
Aさんはそんな接着シートを買った一人でした。
ただし当初はラバーをラケットに貼り付けるつもりで買ったのではありませんでした。
裏ソフトラバーの表面を保護するシートと間違って買ってしまったのです。
このまま捨てるのは悔しいためカーペットのホコリ取りとして利用した後、捨てようかと考えました。
いやそれはかなりもったいないと思い、次のラバーを貼るときに使うこととしました。
使用感は接着剤とそれほど違いを感じませんでした。
さらに次のラバーに貼り替える際、問題が生じました。
接着シートの粘着物質がラケット表面に残ったままとなったのです。
そのままラバーを貼っても接着できそうで、その反面剥がれてしまいそうにも思えました。
液体の接着剤を試しに少しだけ上塗りしてみました。
ラケットの表面がより汚くなってしまいました。
5分間悩んだ末、Aさんはラケットを持って東急ハンズに向かいました。
店員さんに助けを求め、適切なネバネバ除去剤を選んでもらいました。
ほぼ満足のいく修復ができ、Aさんはほっとしました。
接着シートは繰り返し接着シートで貼る場合に使うべきだということを教訓として学びました。
練習場でお会いした人を折に触れて紹介してきました。
今回も個性的な方がいたのでお話したいと思います。
──────────────────────
見慣れない用具の組合わせ
──────────────────────
40代と思われる男性でお名前はわかりません。
いつものように有名人で似た人がいればその名前にしてしまうのですが、適当な人が思い浮かびません。
50mくらい離れるとほんのわずかにTOKIOの松岡さんに似ているかもしれないので、松岡さんということにしておきます。
松岡さんは特徴が2つあります。
1つ目は卓球のプレースタイルです。
ペンホルダーで、現在急速にその数を減らしつつある日本式の角型です。
角ペンというと定番はヒノキの単板です。
松岡さんの用具はそうではなく、ニッタクのラージボール用の特殊素材入り合板ラケットを使っています。
そして片面だけに裏ソフトラバーを貼っています。
伝統的なペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)と思われるかもしれません。
ところが貼っているラバーの銘柄はバタフライのタキネスチョップ2で、つまりカットマン向けの製品です。
しかも厚さは極薄という、なかなか見かけない変わったチョイスです。
今回も個性的な方がいたのでお話したいと思います。
──────────────────────
見慣れない用具の組合わせ
──────────────────────
40代と思われる男性でお名前はわかりません。
いつものように有名人で似た人がいればその名前にしてしまうのですが、適当な人が思い浮かびません。
50mくらい離れるとほんのわずかにTOKIOの松岡さんに似ているかもしれないので、松岡さんということにしておきます。
松岡さんは特徴が2つあります。
1つ目は卓球のプレースタイルです。
ペンホルダーで、現在急速にその数を減らしつつある日本式の角型です。
角ペンというと定番はヒノキの単板です。
松岡さんの用具はそうではなく、ニッタクのラージボール用の特殊素材入り合板ラケットを使っています。
そして片面だけに裏ソフトラバーを貼っています。
伝統的なペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)と思われるかもしれません。
ところが貼っているラバーの銘柄はバタフライのタキネスチョップ2で、つまりカットマン向けの製品です。
しかも厚さは極薄という、なかなか見かけない変わったチョイスです。
某卓球場では参加者がコーチと10分ずつ課題練習をして、アドバイスをもらえます。
私は事前にこれこれこういう練習を行い、何かコメントをいただけたらと計画していました。
私の順番になり気合を入れて4~5本打ったところで待ったがかかりました。
打ち方が良くないとのご指摘で、そこから当初予定とは全く異なるフォーム矯正練習になってしまいました。
──────────────────────
打球位置
──────────────────────
自分の癖というものは、自覚できているものとそうでないものがあります。
私の場合、前者については体の上下動が激しい点、払っていく際に無駄なラケットワークが入る点があります。
後者についてはラケットの面が外に向いていること、上体が正面を向いたまま打っている場合が多いことです。
以前書いたことがありますが、自覚できていないものでも異なる2人の人から同じ指摘があれば、もうそれはほぼ客観的な意見なのだろうと考えています。
具体的に今回コーチから言われたのは、打球位置が体から遠すぎることが多いという点でした。
私は中ペン(中国式ペンホルダー)と日ペン(日本式ペンホルダー)を使い分けていて、その日は角型の日ペンを使っていました。
日ペンは中ペンよりも少しリーチが長く威力のあるボールが打てます。
そのため調子に乗って、より体から離れ遠心力を活かした位置で打っていたのかもしれません。
打点が体から遠いだけでなく、通常よりも後ろになっていると追加の分析をいただきました。
私は事前にこれこれこういう練習を行い、何かコメントをいただけたらと計画していました。
私の順番になり気合を入れて4~5本打ったところで待ったがかかりました。
打ち方が良くないとのご指摘で、そこから当初予定とは全く異なるフォーム矯正練習になってしまいました。
──────────────────────
打球位置
──────────────────────
自分の癖というものは、自覚できているものとそうでないものがあります。
私の場合、前者については体の上下動が激しい点、払っていく際に無駄なラケットワークが入る点があります。
後者についてはラケットの面が外に向いていること、上体が正面を向いたまま打っている場合が多いことです。
以前書いたことがありますが、自覚できていないものでも異なる2人の人から同じ指摘があれば、もうそれはほぼ客観的な意見なのだろうと考えています。
具体的に今回コーチから言われたのは、打球位置が体から遠すぎることが多いという点でした。
私は中ペン(中国式ペンホルダー)と日ペン(日本式ペンホルダー)を使い分けていて、その日は角型の日ペンを使っていました。
日ペンは中ペンよりも少しリーチが長く威力のあるボールが打てます。
そのため調子に乗って、より体から離れ遠心力を活かした位置で打っていたのかもしれません。
打点が体から遠いだけでなく、通常よりも後ろになっていると追加の分析をいただきました。
みなさんご存知の通り、東京オリンピックは迷走状態が若干(かなり?)続いています。
国立競技場、ロゴマーク、マラソン競歩の会場、次々と見直しが入りました。
直接関係はありませんが都知事もスキャンダルで交代が続き、開催地が東京に決まったときの歓喜の再生映像から、二代前の都知事のお姿はほぼカットされています。
一方で各競技場の建設は着実に進み、さすが日本の底力と胸を張りたいものの、開催までにまだ何かが起こりそうな不安があります。
──────────────────────
チケットの第2次抽選
──────────────────────
さて競技を観戦する立場の私達にはどういった影響があったでしょうか。
チケット販売の内容や時期がころころ変わり戸惑いがありました。
それは申込状況を分析した上での適切な方針変更なのだと肯定的に受け止めたいと思います。
当初予定とは異なり、チケットの2次抽選の申し込みが11/26までありました。
最初の抽選で外れ、もう諦めていましたがわずかな可能性にかけ再度申し込みを行いました。
2次抽選には最大6枚までの申し込みができました。
6枚全てを卓球に投入する予定でした。
しかし価格と観戦できる内容・座席を熟考した結果、卓球は予選の一番安い席4枚に抑えました。
高い席はワタクシ的にやはり割に合わないという結論です。
残りの2枚は開会式と閉会式を1枚ずつ申し込みました。
最初と最後の式典となると一番安い席でも12000円ですが、なんとかそれだけの値打ちがあるかなと思えたのです。
このことを話すと練習場の仲間からは、あまり色よい意見はもらえませんでした。
「えーっ開会式なんて当たるわけないじゃん」
「俺は迷わず卓球に6枚使ったよ」
まあいいじゃないですか。
どうせみんな外れるんだし。
万が一(もっと低いですね)、開会式が当たったら練習仲間には黙っておきます。
もう一言だけぼやきを入れさせてもらうと、いくらオリンピックだからと言ってもかなり高額です。
少なくとも今の値段より30%くらいは安くないと内容に見合いません。
練習場のある人は、お値段青天井でオークションが行われる、ごく少数のスーパーエグゼクティブシートを設定し、そのお金で通常の抽選で決まる席の料金を下げてはどうかという提案をしていました。
一つの解決策としては理解できますが、当然どういう批判も起こるか想像がつきます。
国立競技場、ロゴマーク、マラソン競歩の会場、次々と見直しが入りました。
直接関係はありませんが都知事もスキャンダルで交代が続き、開催地が東京に決まったときの歓喜の再生映像から、二代前の都知事のお姿はほぼカットされています。
一方で各競技場の建設は着実に進み、さすが日本の底力と胸を張りたいものの、開催までにまだ何かが起こりそうな不安があります。
──────────────────────
チケットの第2次抽選
──────────────────────
さて競技を観戦する立場の私達にはどういった影響があったでしょうか。
チケット販売の内容や時期がころころ変わり戸惑いがありました。
それは申込状況を分析した上での適切な方針変更なのだと肯定的に受け止めたいと思います。
当初予定とは異なり、チケットの2次抽選の申し込みが11/26までありました。
最初の抽選で外れ、もう諦めていましたがわずかな可能性にかけ再度申し込みを行いました。
2次抽選には最大6枚までの申し込みができました。
6枚全てを卓球に投入する予定でした。
しかし価格と観戦できる内容・座席を熟考した結果、卓球は予選の一番安い席4枚に抑えました。
高い席はワタクシ的にやはり割に合わないという結論です。
残りの2枚は開会式と閉会式を1枚ずつ申し込みました。
最初と最後の式典となると一番安い席でも12000円ですが、なんとかそれだけの値打ちがあるかなと思えたのです。
このことを話すと練習場の仲間からは、あまり色よい意見はもらえませんでした。
「えーっ開会式なんて当たるわけないじゃん」
「俺は迷わず卓球に6枚使ったよ」
まあいいじゃないですか。
どうせみんな外れるんだし。
万が一(もっと低いですね)、開会式が当たったら練習仲間には黙っておきます。
もう一言だけぼやきを入れさせてもらうと、いくらオリンピックだからと言ってもかなり高額です。
少なくとも今の値段より30%くらいは安くないと内容に見合いません。
練習場のある人は、お値段青天井でオークションが行われる、ごく少数のスーパーエグゼクティブシートを設定し、そのお金で通常の抽選で決まる席の料金を下げてはどうかという提案をしていました。
一つの解決策としては理解できますが、当然どういう批判も起こるか想像がつきます。
2019 .11.16
私が時々お邪魔する卓球場は、試合だけをする時間帯が設けてあります。
そのときにあった出来事をお話ししたいと思います。
──────────────────────
取れないサーブ
──────────────────────
おじさんと小学生の女の子が試合をしていて、私は抜け番で審判をしていました。
おじさんはテクニシャンで、強烈なバックスピンを掛けた山なりのサーブをフォア前へ短く出しました。
そのサーブは相手コートに入り、そのまま放置すると自コートに戻ってくるボテボテサーブです。
大人ならフォア前へさっと動いてひっぱたけば済みます。
しかし女の子はまだ体格が小さいためそれができず、何もできないまま傍観するしかありません。
私は卑怯だなとは思いつつ、おじさん側に得点を与えました。
しばらく試合が進行し、おじさんは再度同じサーブを出しました。
流石にこれはイカンと思い「そのサーブはなしにしてもらえませんか」とおじさんに伝えました。
相手にちょっとした異議を唱える場合、同じことが2度起きたときや3度起きた時点で切り出すという対人関係スキルを、昔会社の研修であったのを思い出しました。
おじさんは素直に受け入れてくれ、レットにしてやり直すことができました。
内心ほっとしました。
そのときにあった出来事をお話ししたいと思います。
──────────────────────
取れないサーブ
──────────────────────
おじさんと小学生の女の子が試合をしていて、私は抜け番で審判をしていました。
おじさんはテクニシャンで、強烈なバックスピンを掛けた山なりのサーブをフォア前へ短く出しました。
そのサーブは相手コートに入り、そのまま放置すると自コートに戻ってくるボテボテサーブです。
大人ならフォア前へさっと動いてひっぱたけば済みます。
しかし女の子はまだ体格が小さいためそれができず、何もできないまま傍観するしかありません。
私は卑怯だなとは思いつつ、おじさん側に得点を与えました。
しばらく試合が進行し、おじさんは再度同じサーブを出しました。
流石にこれはイカンと思い「そのサーブはなしにしてもらえませんか」とおじさんに伝えました。
相手にちょっとした異議を唱える場合、同じことが2度起きたときや3度起きた時点で切り出すという対人関係スキルを、昔会社の研修であったのを思い出しました。
おじさんは素直に受け入れてくれ、レットにしてやり直すことができました。
内心ほっとしました。
前回に続いて、私が印象に残っているペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)選手についてお話したいと思います。
──────────────────────
イジョンウ選手
──────────────────────
イジョンウ選手は、アテネ五輪金メダリストであるユスンミン選手の後継者的位置づけで頭角を現してきました。
長身ということもあり構えは足をガバっと開いて低い前傾姿勢を取ります。
左利きでリーチが長く、一方で少し童顔なのがアンバランスです。
私の目には、ユスンミン選手はスピードドライブ、イジョンウ選手は回転量重視のドライブのように映っています。
バック側は早い打点でのプッシュかショートです。
ああいう伸びのあるフォアハンドドライブが打てたならといいなと、羨ましく思っています。
私が理想とするプレースタイルに近い選手です。
お気に入りの試合動画があったのですが、半年ほど前に何故か削除されてしまいショックを受けました。
イ選手もすでに引退していて、おそらく韓国最後のペンドラだったということになりそうです。
──────────────────────
イジョンウ選手
──────────────────────
イジョンウ選手は、アテネ五輪金メダリストであるユスンミン選手の後継者的位置づけで頭角を現してきました。
長身ということもあり構えは足をガバっと開いて低い前傾姿勢を取ります。
左利きでリーチが長く、一方で少し童顔なのがアンバランスです。
私の目には、ユスンミン選手はスピードドライブ、イジョンウ選手は回転量重視のドライブのように映っています。
バック側は早い打点でのプッシュかショートです。
ああいう伸びのあるフォアハンドドライブが打てたならといいなと、羨ましく思っています。
私が理想とするプレースタイルに近い選手です。
お気に入りの試合動画があったのですが、半年ほど前に何故か削除されてしまいショックを受けました。
イ選手もすでに引退していて、おそらく韓国最後のペンドラだったということになりそうです。
私は片面だけにラバーを貼ったペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)です。
同じスタイルの方は見かけることは見かけるのですが、その95%は中高年プレーヤーです。
角型ペンを振り回している高校生を見つけると、2000円札あるいは白いヘビに遭遇したほどの珍しさを感じます。
かつての日本では伝統的な戦型でしたが急速に廃れ、アジア系の選手の間でももはや絶滅の危機に直面しています。
そういう寂しさを感じつつ、今回は印象に残るペンドラ選手について述べてみたいと思います。
(角型日本式ペンホルダーの片面だけに、裏ソフトラバーを貼った選手を対象としました)
──────────────────────
キムテクス選手
──────────────────────
理想的なペンドラ選手No.1は誰かと聞かれれば、私は韓国のキムテクス選手を挙げたいと思います。
多くの方が口にするのがフォームの美しさです。
他のペンドラ選手と比較すると上体がスッと立っているような感じがあり、重心が安定している印象を受けます。
世界トップレベルで活躍したペンドラだけあって、縦横無尽のフットワークを誇り、それでいてフォームが乱れないのは素晴らしいお手本です。
バックは、鉄壁のブロック、バックハンド強打、フィッシュの3つを駆使します。
最後のフィッシュとは低いロビングのようなしのぎ技です。
空中高く上げるロビングはほぼ防戦だけの技術で、相手がスマッシュミスをしてくれるのを願うのみとなります。
一方フィッシュはロビングほどには追い込まれた感は強くなく、反撃に転じることができる可能性がそれなりにあります。
実際キム選手は連続フィッシュでしのぎ、回り込んでフォアドライブあるいはバックハンド強打で攻勢に転じた場面が何度もありました。
あまり無茶打ちをすることはなく、変な小細工のような仕掛けも見られません。
そのあたりも模範的と見られている理由なのでしょう。
少しだけ指摘されているのがサーブで、フリーハンドをもう少しだけ開いて静止させてはどうかという意見には同意します。
キム選手の動画は結構ありますので、今もたまに見ることがあります。
同じスタイルの方は見かけることは見かけるのですが、その95%は中高年プレーヤーです。
角型ペンを振り回している高校生を見つけると、2000円札あるいは白いヘビに遭遇したほどの珍しさを感じます。
かつての日本では伝統的な戦型でしたが急速に廃れ、アジア系の選手の間でももはや絶滅の危機に直面しています。
そういう寂しさを感じつつ、今回は印象に残るペンドラ選手について述べてみたいと思います。
(角型日本式ペンホルダーの片面だけに、裏ソフトラバーを貼った選手を対象としました)
──────────────────────
キムテクス選手
──────────────────────
理想的なペンドラ選手No.1は誰かと聞かれれば、私は韓国のキムテクス選手を挙げたいと思います。
多くの方が口にするのがフォームの美しさです。
他のペンドラ選手と比較すると上体がスッと立っているような感じがあり、重心が安定している印象を受けます。
世界トップレベルで活躍したペンドラだけあって、縦横無尽のフットワークを誇り、それでいてフォームが乱れないのは素晴らしいお手本です。
バックは、鉄壁のブロック、バックハンド強打、フィッシュの3つを駆使します。
最後のフィッシュとは低いロビングのようなしのぎ技です。
空中高く上げるロビングはほぼ防戦だけの技術で、相手がスマッシュミスをしてくれるのを願うのみとなります。
一方フィッシュはロビングほどには追い込まれた感は強くなく、反撃に転じることができる可能性がそれなりにあります。
実際キム選手は連続フィッシュでしのぎ、回り込んでフォアドライブあるいはバックハンド強打で攻勢に転じた場面が何度もありました。
あまり無茶打ちをすることはなく、変な小細工のような仕掛けも見られません。
そのあたりも模範的と見られている理由なのでしょう。
少しだけ指摘されているのがサーブで、フリーハンドをもう少しだけ開いて静止させてはどうかという意見には同意します。
キム選手の動画は結構ありますので、今もたまに見ることがあります。
2019 .10.05
卓球はこれまでのルール変更で、サーブの威力を弱める改革が何度もなされてきました。
それでも今なお強力なサーブが存在し、得点を連続献上してしまうシーンをあちこちで見かけます。
一部の人はそれに嫌気がさし、とりあえず返球できればと粒高ラバーやアンチラバーに変えてしまう人もいるそうです。
レシーブのことを第一に考えたラバー選択をするとどうなるのか、私なりの意見を述べさせていただきます。
──────────────────────
粒高ラバー、アンチラバー
──────────────────────
まず先に挙げた粒高ラバーとアンチラバーですが、それらは確かに返球は楽になります。
漫画で回転のさまを表現すると「ブインブイン」あるいは「ギュワンギュワン」といった、ものすごい回転がかかったサーブも、ツンと当てるだけで返せる場面が増えます。
ですがそういうサーブは、レシーブする側が裏ソフトだからこそ出されているのです。
粒やアンチに凝ったサーブを出すと、逆に気持ち悪い返球で返されてしまう場合があります。
そのため初級レベルでは、相手がカットマンでなければ粒やアンチに向けてロングサーブを出すのが基本だと思います。
ロングサーブを出し、ショートで返してきた変化の少ない長めの返球を3球目攻撃で狙い撃つのです。
そういうパターンでめった打ちに合うと、粒やアンチにしたラバーの選択を再考すべきかもしれません。
もちろん粒やアンチを貼っている強い人は、カット製ブロックで返球するなどレシーブおよびその後の対処もいろいろな技を持っています。
ただレシーブを最優先にして粒やアンチを選ぶのは、局所的・短絡的なように思えます。
そしてこういった変化系ラバーはどうしても守備的になり、できることが制約されます。
ご自身のプレースタイルを総合的に考えた上での選択であって欲しいですね。
それでも今なお強力なサーブが存在し、得点を連続献上してしまうシーンをあちこちで見かけます。
一部の人はそれに嫌気がさし、とりあえず返球できればと粒高ラバーやアンチラバーに変えてしまう人もいるそうです。
レシーブのことを第一に考えたラバー選択をするとどうなるのか、私なりの意見を述べさせていただきます。
──────────────────────
粒高ラバー、アンチラバー
──────────────────────
まず先に挙げた粒高ラバーとアンチラバーですが、それらは確かに返球は楽になります。
漫画で回転のさまを表現すると「ブインブイン」あるいは「ギュワンギュワン」といった、ものすごい回転がかかったサーブも、ツンと当てるだけで返せる場面が増えます。
ですがそういうサーブは、レシーブする側が裏ソフトだからこそ出されているのです。
粒やアンチに凝ったサーブを出すと、逆に気持ち悪い返球で返されてしまう場合があります。
そのため初級レベルでは、相手がカットマンでなければ粒やアンチに向けてロングサーブを出すのが基本だと思います。
ロングサーブを出し、ショートで返してきた変化の少ない長めの返球を3球目攻撃で狙い撃つのです。
そういうパターンでめった打ちに合うと、粒やアンチにしたラバーの選択を再考すべきかもしれません。
もちろん粒やアンチを貼っている強い人は、カット製ブロックで返球するなどレシーブおよびその後の対処もいろいろな技を持っています。
ただレシーブを最優先にして粒やアンチを選ぶのは、局所的・短絡的なように思えます。
そしてこういった変化系ラバーはどうしても守備的になり、できることが制約されます。
ご自身のプレースタイルを総合的に考えた上での選択であって欲しいですね。
前回に引き続き、大阪への出張のついでにTリーグの試合を観戦してきたUさんのレポートをお届けいたします。
──────────────────────
二者択一を迫られる客席
──────────────────────
席に座り徐々にわかってきたのは、これが日本ペイントマレッツのホームゲームだということでした。
そしてたまたまですが、Uさんはマレッツ側の自由席に座りました。
マレッツ側に座った人は折りたたみ式のハリセンを渡され、それを叩いて応援することを半ば強制されました。
試合中楽器などで音を出すのは禁止されていて、ハリセンなら認められているようです。
Uさんは特にどちらかのチームを贔屓しているわけではないので、ハリセンはもらわず集団の中に控えめに座っていました。
ただし入場時に対戦相手のトップ名古屋サポーターからもらったうちわを出しておくのは良くないと考え、カバンの中に収めていました。
マレッツのホームゲームであることは認めつつ、それでも場内アナウンスまでがかなり片方にのみ肩入れし過ぎな点に疑問を抱きました。
合間合間にマレッツの応援ソングが流れていました。
手渡された資料によると、応援ソングの作詞作曲は日本ペイントの社員さんなのだそうです。
──────────────────────
二者択一を迫られる客席
──────────────────────
席に座り徐々にわかってきたのは、これが日本ペイントマレッツのホームゲームだということでした。
そしてたまたまですが、Uさんはマレッツ側の自由席に座りました。
マレッツ側に座った人は折りたたみ式のハリセンを渡され、それを叩いて応援することを半ば強制されました。
試合中楽器などで音を出すのは禁止されていて、ハリセンなら認められているようです。
Uさんは特にどちらかのチームを贔屓しているわけではないので、ハリセンはもらわず集団の中に控えめに座っていました。
ただし入場時に対戦相手のトップ名古屋サポーターからもらったうちわを出しておくのは良くないと考え、カバンの中に収めていました。
マレッツのホームゲームであることは認めつつ、それでも場内アナウンスまでがかなり片方にのみ肩入れし過ぎな点に疑問を抱きました。
合間合間にマレッツの応援ソングが流れていました。
手渡された資料によると、応援ソングの作詞作曲は日本ペイントの社員さんなのだそうです。
昨年末に3回に渡り、Tリーグを観戦してきたUさんのレポートをお伝えしました。
そのUさんが今シーズンの試合を見てきたのでその内容をお伝えします。
なおいつものようにニッチな情報なので、ちゃんとした試合結果や論評を知りたい方は公式サイトでご確認いただければ幸いです。
──────────────────────
都会の真ん中の体育館
──────────────────────
Uさんは大阪に出張する機会があり、初日の夜は大阪で開催されるTリーグ女子の試合と重なっていました。
そして幸運にも人づてで自由席のチケットを入手することができました。
昨年末は諸々の手数料を含め2324円で自由席チケットを購入しましたが、今回はタダということでUさんの顔面は緩みっぱなしでした。
Tリーグのチケットはオリンピックほどには厳格に扱われておらず、フリマサイトでの出品もOKのようでいくつか出回っているのを確認しました。
観戦を希望される方で条件が合えば、メルカリなどで入手できることもあります。
会場は大阪府立体育館でした。
大阪屈指のターミナル駅である難波(なんば)から歩いて行ける距離にあり、アクセスはすこぶる便利です。
大阪府の財政改善の一環として、家電量販店のエディオンがこの体育館の施設命名契約を結んでいます。
従って通常であれば「エディオンアリーナ大阪」と呼ぶべきなのでしょう。
しかしTリーグのWebサイトを見ると大阪府立体育館となっています。
なぜそうしているのか。
Tリーグの冠スポンサーは同じく家電量販店のノジマで、Tリーグは「ノジマ Tリーグ」であります。
どうやらライバルであるエディオンの名前は極力見せないよう忖度がなされているようです。
ちなみに日本相撲協会のサイトでは、3月場所の会場表記はエディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館)となっています。
そのUさんが今シーズンの試合を見てきたのでその内容をお伝えします。
なおいつものようにニッチな情報なので、ちゃんとした試合結果や論評を知りたい方は公式サイトでご確認いただければ幸いです。
──────────────────────
都会の真ん中の体育館
──────────────────────
Uさんは大阪に出張する機会があり、初日の夜は大阪で開催されるTリーグ女子の試合と重なっていました。
そして幸運にも人づてで自由席のチケットを入手することができました。
昨年末は諸々の手数料を含め2324円で自由席チケットを購入しましたが、今回はタダということでUさんの顔面は緩みっぱなしでした。
Tリーグのチケットはオリンピックほどには厳格に扱われておらず、フリマサイトでの出品もOKのようでいくつか出回っているのを確認しました。
観戦を希望される方で条件が合えば、メルカリなどで入手できることもあります。
会場は大阪府立体育館でした。
大阪屈指のターミナル駅である難波(なんば)から歩いて行ける距離にあり、アクセスはすこぶる便利です。
大阪府の財政改善の一環として、家電量販店のエディオンがこの体育館の施設命名契約を結んでいます。
従って通常であれば「エディオンアリーナ大阪」と呼ぶべきなのでしょう。
しかしTリーグのWebサイトを見ると大阪府立体育館となっています。
なぜそうしているのか。
Tリーグの冠スポンサーは同じく家電量販店のノジマで、Tリーグは「ノジマ Tリーグ」であります。
どうやらライバルであるエディオンの名前は極力見せないよう忖度がなされているようです。
ちなみに日本相撲協会のサイトでは、3月場所の会場表記はエディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館)となっています。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。