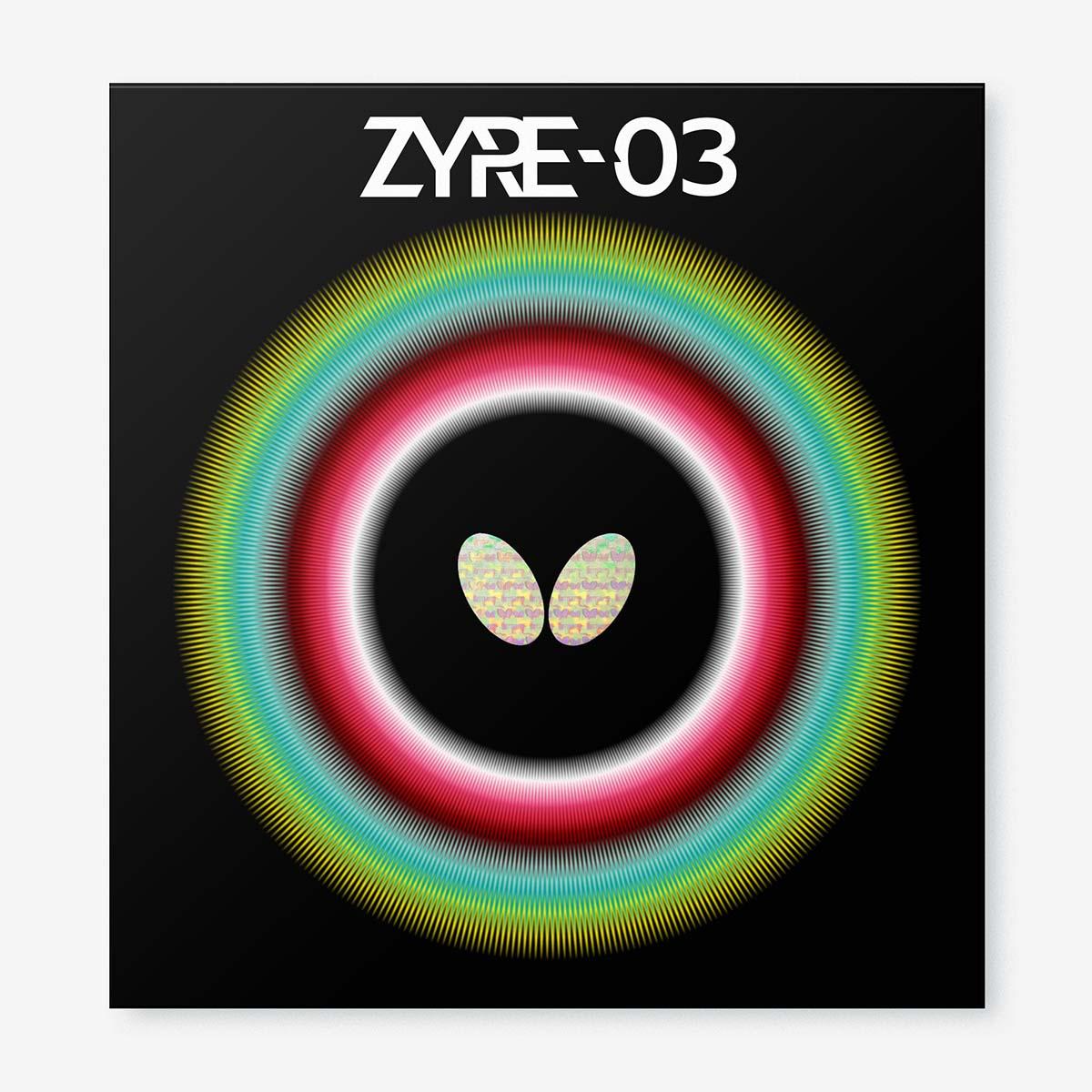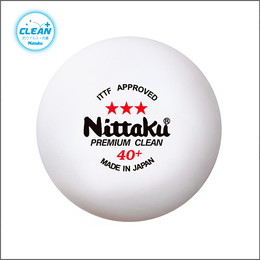前回は後半部分でシューズについて触れました。
私は足を保護することを重視しているので、クッション性の高いバレーボールやバドミントンシューズを履いてきました。
それでも次は卓球シューズを買おうと考えていました。
しかし最近は足の状態があまり思わしくなく、やはり次も別競技のシューズにしようか思案しています。
──────────────────────
回り込みと飛びつき
──────────────────────
足のどこが不調になるかというと、左足親指の付け根付近です。
そこの関節部分がずーんと痛むのです。
これは私のプレースタイルが多分に影響しています。
私は絶滅の危機に瀕している、ラケットの片面だけにラバーを貼ったペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)です。
フットワークを駆使して(いるつもりで)、できるだけフォアハンドでドライブを打ちにいきます。
必然的に遠くへ飛びつく場面が増え、その際は足を交差させたフットワークになります。
フォア側の遠くに飛びつく場合、右利きなら最初に右足を移動する方向へ少し踏み出します。
次に上体を右方向にひねりながら、左足を交差させ右側に飛びつきます。
打球後すぐに左足を着地させて踏ん張り、今度は上体を左回りに回転させながら右足も着地します。
左足で踏ん張っている瞬間が最も負担がかかっていて、その場所が親指の付け根付近になります。
左右のシューズのすり減り具合からもそのことが伺え、左足親指付け周辺の摩耗は顕著です。
こういう飛びついたり回り込むプレーは見た目は豪快ですが、あまりお勧めできません。
フットワークの大切さは意識しつつ、両ハンドで攻守をするのが現代卓球の王道だからです。
そうは言っても私は週一回の卓球で裏面打法の習得は難しく、今のごり押しプレーをするしかありません。
私は足を保護することを重視しているので、クッション性の高いバレーボールやバドミントンシューズを履いてきました。
それでも次は卓球シューズを買おうと考えていました。
しかし最近は足の状態があまり思わしくなく、やはり次も別競技のシューズにしようか思案しています。
──────────────────────
回り込みと飛びつき
──────────────────────
足のどこが不調になるかというと、左足親指の付け根付近です。
そこの関節部分がずーんと痛むのです。
これは私のプレースタイルが多分に影響しています。
私は絶滅の危機に瀕している、ラケットの片面だけにラバーを貼ったペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)です。
フットワークを駆使して(いるつもりで)、できるだけフォアハンドでドライブを打ちにいきます。
必然的に遠くへ飛びつく場面が増え、その際は足を交差させたフットワークになります。
フォア側の遠くに飛びつく場合、右利きなら最初に右足を移動する方向へ少し踏み出します。
次に上体を右方向にひねりながら、左足を交差させ右側に飛びつきます。
打球後すぐに左足を着地させて踏ん張り、今度は上体を左回りに回転させながら右足も着地します。
左足で踏ん張っている瞬間が最も負担がかかっていて、その場所が親指の付け根付近になります。
左右のシューズのすり減り具合からもそのことが伺え、左足親指付け周辺の摩耗は顕著です。
こういう飛びついたり回り込むプレーは見た目は豪快ですが、あまりお勧めできません。
フットワークの大切さは意識しつつ、両ハンドで攻守をするのが現代卓球の王道だからです。
そうは言っても私は週一回の卓球で裏面打法の習得は難しく、今のごり押しプレーをするしかありません。
最近はいろんなものが自宅に居ながらにして買うことができます。
そして実物を見ないでも購入することに抵抗のない人が増えています。
便利な世の中になり喜ぶ一方で、全てがうまくいく訳ではないことがあります。
──────────────────────
ネットで購入した一着目
──────────────────────
鈴木さん(仮名)は積極的にネットでのお買い物を利用する人です。
卓球用品に関してもT社のユニフォームを通販で購入しました。
自宅のパソコンで見ていたのは、T社Webサイトに掲載されていた画像でした。
アパレル業界では何か専門用語があるのかもしれませんが、私は知らないためここでは便宜上平面図と表現しておきます。
ユニフォームを机などの上にペタッと置いた状態の画像です。
鈴木さんはそのデザインだけを見て購入ボタンをクリックしました。
届いたのは紛れもなく選択した商品でした。
ルンルン気分で早速着用し鏡を見ました。
ん???、なんだか想像していたイメージと違います。
胸やお腹の体の前面部分と、わき腹の側面部分が仕切られたデザインのユニフォームでした。
購入前はそれを頭の中で立体画像に変換したのですが、どうも鈴木さんの画像処理能力には限界があったようでした。
そして実物を見ないでも購入することに抵抗のない人が増えています。
便利な世の中になり喜ぶ一方で、全てがうまくいく訳ではないことがあります。
──────────────────────
ネットで購入した一着目
──────────────────────
鈴木さん(仮名)は積極的にネットでのお買い物を利用する人です。
卓球用品に関してもT社のユニフォームを通販で購入しました。
自宅のパソコンで見ていたのは、T社Webサイトに掲載されていた画像でした。
アパレル業界では何か専門用語があるのかもしれませんが、私は知らないためここでは便宜上平面図と表現しておきます。
ユニフォームを机などの上にペタッと置いた状態の画像です。
鈴木さんはそのデザインだけを見て購入ボタンをクリックしました。
届いたのは紛れもなく選択した商品でした。
ルンルン気分で早速着用し鏡を見ました。
ん???、なんだか想像していたイメージと違います。
胸やお腹の体の前面部分と、わき腹の側面部分が仕切られたデザインのユニフォームでした。
購入前はそれを頭の中で立体画像に変換したのですが、どうも鈴木さんの画像処理能力には限界があったようでした。
今年1月の全日本選手権について、大阪まで出かけた特派員D氏のレポートをお届けしました。
今回はそのD氏のお宅にお邪魔したときのことをお話しします。
──────────────────────
機械はいつか壊れる
──────────────────────
なぜか巷ではあまり話題になっていませんが、10月に消費税が10%になります。
それについてD氏はいろいろと考えていて、新しいハードディスクレコーダーを購入しようか悩んでいました。
現在はもう4台めの機種なのだそうです。
中に残している映像を見せてもらうと当然卓球の録画があり、リオ五輪の水谷選手と許シン選手の試合や、石川選手とシャンシャオナ選手の熱い対戦がありました。
てっきり日本人選手の勝利の記録を残しておきたかったためだと思っていると、全く異なる理由に驚きました。
「自分と同じ貴重なペンホルダー選手の映像だから」というお答えでした。
さらにその前のロンドンオリンピックの録画については見当たりませんでした。
1つ前のレコーダーに録画はしていたのですが壊れてしまい、泣く泣く廃棄したそうです。
今回はそのD氏のお宅にお邪魔したときのことをお話しします。
──────────────────────
機械はいつか壊れる
──────────────────────
なぜか巷ではあまり話題になっていませんが、10月に消費税が10%になります。
それについてD氏はいろいろと考えていて、新しいハードディスクレコーダーを購入しようか悩んでいました。
現在はもう4台めの機種なのだそうです。
中に残している映像を見せてもらうと当然卓球の録画があり、リオ五輪の水谷選手と許シン選手の試合や、石川選手とシャンシャオナ選手の熱い対戦がありました。
てっきり日本人選手の勝利の記録を残しておきたかったためだと思っていると、全く異なる理由に驚きました。
「自分と同じ貴重なペンホルダー選手の映像だから」というお答えでした。
さらにその前のロンドンオリンピックの録画については見当たりませんでした。
1つ前のレコーダーに録画はしていたのですが壊れてしまい、泣く泣く廃棄したそうです。
今回は高級ラケットについてお話しします。
最近は各メーカーが結構なお値段のラケットを出していて、一万円台なら普通、二万円を超えても驚かないほど感覚が麻痺しつつあります。
まあそれでも一万円の大台を超えれば高級ということにしたいと思います。
一部メーカーは高級ラケットをシリーズ化していて、おおむね以下のような特徴があります。
1)木目の縞模様が目立っていたり、暗い色合いのブレードであることが多い
2)落ち着いた渋めのグリップ
3)上品なロゴやネーミング
卓球ラケットに限った話ではありませんが、高価格帯の商品は一般に利益も多く乗せられていてメーカーにはうまみがあります。
気合を入れて販促活動を行いますがヒットしたものもあれば、売れ行きが芳しくないものもあります。
──────────────────────
ガシアンシリーズ
──────────────────────
フランスにコニヨールという卓球用具メーカーがあります。
そのフランスが生んだ世界チャンピオン、ジャン=フィリップ・ガシアン選手モデルのラケットです。
日本ではジュウイックがコニヨールの製品を扱っていて、ラケットとラバーを販売しています。
ガシアンシリーズのラケットは11,000円~20,000円で発売されていて、全日本女子シングルスで準優勝した木原選手がかつて使っていました。
シリーズ全体に言えるのは重めのラケットだという点です。
全て90g以上で、ガシアン-アブソルムに至っては平均重量100gです。
どのモデルにも中ペン(中国式ペンホルダー)が設定され、世界で売ろうとする意欲が感じられる製品でした。
「でした」と過去形になっているのは、今年のカタログからは消えていて販売終了となったためです。(在庫を継続販売中)
見た目はイケてると思うのですが、価格と重量がネックになったのかもしれません。
最近は各メーカーが結構なお値段のラケットを出していて、一万円台なら普通、二万円を超えても驚かないほど感覚が麻痺しつつあります。
まあそれでも一万円の大台を超えれば高級ということにしたいと思います。
一部メーカーは高級ラケットをシリーズ化していて、おおむね以下のような特徴があります。
1)木目の縞模様が目立っていたり、暗い色合いのブレードであることが多い
2)落ち着いた渋めのグリップ
3)上品なロゴやネーミング
卓球ラケットに限った話ではありませんが、高価格帯の商品は一般に利益も多く乗せられていてメーカーにはうまみがあります。
気合を入れて販促活動を行いますがヒットしたものもあれば、売れ行きが芳しくないものもあります。
──────────────────────
ガシアンシリーズ
──────────────────────
フランスにコニヨールという卓球用具メーカーがあります。
そのフランスが生んだ世界チャンピオン、ジャン=フィリップ・ガシアン選手モデルのラケットです。
日本ではジュウイックがコニヨールの製品を扱っていて、ラケットとラバーを販売しています。
ガシアンシリーズのラケットは11,000円~20,000円で発売されていて、全日本女子シングルスで準優勝した木原選手がかつて使っていました。
シリーズ全体に言えるのは重めのラケットだという点です。
全て90g以上で、ガシアン-アブソルムに至っては平均重量100gです。
どのモデルにも中ペン(中国式ペンホルダー)が設定され、世界で売ろうとする意欲が感じられる製品でした。
「でした」と過去形になっているのは、今年のカタログからは消えていて販売終了となったためです。(在庫を継続販売中)
見た目はイケてると思うのですが、価格と重量がネックになったのかもしれません。
2019 .06.29
6月20に東京オリンピックのチケット抽選が行われました。
みなさんの中で申し込まれた方はどうだったでしょうか。
──────────────────────
甘く見すぎた競争率
──────────────────────
私は1枚だけ申し込み残念ながら、というよりむしろ当たり前の結果として当選しませんでした。
周囲で複数枚申し込んだ人も多くが涙をのみました。
当選しなかった人が口々に話していたのは「もっと沢山申し込んでいればよかった」という反省の弁です。
基本的に当選すればそのチケットは全て購入するか、全て辞退するかの二択ルールとなっています。
従って確率はとっても低いのに複数枚当たった時のことを想像してしまい、申込数を手控えてしまったことを悔やんでいました。
私も当初は3~4枚程度申し込んでみようかと考えていました。
でも全部当たってしまったらどうしよう(←今から考えるとあり得ない)、他の観戦チケットより割高だし(←オリンピックだよ)、といった迷いが生じ、結局たった1枚の申し込みに絞ってしまいました。
あーなんて馬鹿なことをしてしまったのか。
卓球は10枚くらい申し込み、他競技の安価なチケットも2~3枚申し込んでいれば良かったかもしれません。
受付時のあの混雑の度合いを見てピンとこなかった鈍い自分を恥じます。
まあ後悔先に立たずなので、ここは気持ちを切り替え次をどうするか考えたいと思います。
今後の観戦チケットの入手方法は以下の3つがあります。
1)先着販売、2)リセール、3)販売所
それぞれについて順を追ってご説明いたします。
みなさんの中で申し込まれた方はどうだったでしょうか。
──────────────────────
甘く見すぎた競争率
──────────────────────
私は1枚だけ申し込み残念ながら、というよりむしろ当たり前の結果として当選しませんでした。
周囲で複数枚申し込んだ人も多くが涙をのみました。
当選しなかった人が口々に話していたのは「もっと沢山申し込んでいればよかった」という反省の弁です。
基本的に当選すればそのチケットは全て購入するか、全て辞退するかの二択ルールとなっています。
従って確率はとっても低いのに複数枚当たった時のことを想像してしまい、申込数を手控えてしまったことを悔やんでいました。
私も当初は3~4枚程度申し込んでみようかと考えていました。
でも全部当たってしまったらどうしよう(←今から考えるとあり得ない)、他の観戦チケットより割高だし(←オリンピックだよ)、といった迷いが生じ、結局たった1枚の申し込みに絞ってしまいました。
あーなんて馬鹿なことをしてしまったのか。
卓球は10枚くらい申し込み、他競技の安価なチケットも2~3枚申し込んでいれば良かったかもしれません。
受付時のあの混雑の度合いを見てピンとこなかった鈍い自分を恥じます。
まあ後悔先に立たずなので、ここは気持ちを切り替え次をどうするか考えたいと思います。
今後の観戦チケットの入手方法は以下の3つがあります。
1)先着販売、2)リセール、3)販売所
それぞれについて順を追ってご説明いたします。
2019 .06.15
東京オリンピック観戦チケットの抽選結果が来週の6月20日に発表されます。
私は一番安い席を1枚だけ申し込みましたが、それでも結果がどうなるかドキドキしています。
そのオリンピックが終わった後、用具に関するルールが変わります。
今回はそれについてお話ししたいと思います。
──────────────────────
規制と規制緩和
──────────────────────
変更はラバーの色に関するものです。
現在は黒と赤の2色にするよう定められています。
これが黒と黒以外の色に緩和されます。
シニアの方にとっては昔に戻るという感じでしょうか。
大昔はラバーの色に関する規制が緩く、ボールと同色の白っぽい色でなければ大丈夫というかなり自由な状況でした。
従って黒と赤の他にも、青、緑、黄色など多彩でした。
ところがそれだと両面に同じ色のラバーを貼り、片方は裏ソフト、もう片方はアンチラバーにする選手が増えてきました。
回転量を分からなくしてミスをさせる作戦です。
対戦相手はほぼ判別不可能な2択を迫られ、それを観戦する者には訳の分からない凡ミスが増えたように見えました。
これはイカンということで現在の黒と赤の2色にルール変更されました。
当初は異なる2色としたのですが、黒と暗い茶色のような紛らわしい組み合わせのラバーを貼る選手がいて混乱を招きました。
そのため短期間で黒赤の2色に見直しがなされました。
このような歴史があったため、来年のルール改正は黒と明らかに黒と異なる色にしなさいとクギを刺すはずです。
「はずです」と書いているのは、黒&黒以外にすることだけが決定していて、詳細は今後詰めることになっているからです。
私は一番安い席を1枚だけ申し込みましたが、それでも結果がどうなるかドキドキしています。
そのオリンピックが終わった後、用具に関するルールが変わります。
今回はそれについてお話ししたいと思います。
──────────────────────
規制と規制緩和
──────────────────────
変更はラバーの色に関するものです。
現在は黒と赤の2色にするよう定められています。
これが黒と黒以外の色に緩和されます。
シニアの方にとっては昔に戻るという感じでしょうか。
大昔はラバーの色に関する規制が緩く、ボールと同色の白っぽい色でなければ大丈夫というかなり自由な状況でした。
従って黒と赤の他にも、青、緑、黄色など多彩でした。
ところがそれだと両面に同じ色のラバーを貼り、片方は裏ソフト、もう片方はアンチラバーにする選手が増えてきました。
回転量を分からなくしてミスをさせる作戦です。
対戦相手はほぼ判別不可能な2択を迫られ、それを観戦する者には訳の分からない凡ミスが増えたように見えました。
これはイカンということで現在の黒と赤の2色にルール変更されました。
当初は異なる2色としたのですが、黒と暗い茶色のような紛らわしい組み合わせのラバーを貼る選手がいて混乱を招きました。
そのため短期間で黒赤の2色に見直しがなされました。
このような歴史があったため、来年のルール改正は黒と明らかに黒と異なる色にしなさいとクギを刺すはずです。
「はずです」と書いているのは、黒&黒以外にすることだけが決定していて、詳細は今後詰めることになっているからです。
1月に行われた全日本選手権では、上位に勝ち進んだ選手以外にも大きくメディアに取り上げられた人がいました。
その中の1人に張本美和選手がいました。
試合が行われるコートは常に数名のカメラマンが取り囲んでいました。
マスコミは毎回若手の目玉選手を追いかける傾向があり、張本選手はその中でも最年少の注目株でした。
全日本選手権の模様については、以前特派員D氏からのレポートをお届けしました。
そしてD氏はたまたまですが張本選手の試合も見ていました。
少数派の戦型を中心に見ていたため、カットマンと対戦する張本選手の試合が目に留まったのです。
──────────────────────
長年の思い込みを修正
──────────────────────
張本選手は小学生ながら、一般の女子シングルスで3回戦まで進みました。
2回戦と3回戦はカットマンが相手で、それぞれの相手に対する感想が卓球王国の速報に書かれていました。
2回戦のカットマンは切るカットマンでしたが、3回戦の相手はナックル中心のカットマンのため苦戦して負けたとのことでした。
D氏はその速報の文章を読んで、いろいろと考えさせられることがありました。
ペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)であるD氏がカットマンと対戦するときのモットーは、ドライブで押して押しまくり、浮いた返球をスマッシュで撃ち抜くことです。
それが王道であると固く信じ、そこそこ通用してきました。
ただなぜか相手のカットにボールが合わず、ミスを連発して負けることがありました。
王国の速報を読んでいて、その負け方にピーンとくるものがありました。
「そうか、ナックル主体のカットマンか…」
つまり張本選手の試合とはすさまじいレベルの差はあるものの、自分もあまり切らないカットマンには慣れておらず、対処を間違って負けていたことに気がつきました。
D氏はカットマンは大別すると、切るタイプと入れるタイプの2種類がいると捉えていました。
切るタイプはブチ切れカットで強打を防ぎ、入れるタイプはコース取りと変化で勝負するものという理解です。
そのような独自の分類および解釈は、多くの人がそれぞれ理解しやすいように理論立てて持っています。
D氏の頭にはあまり切ってこないカットマンという存在はありましたが、それでもある程度切れているボールを通常の返球として返すものだという固定観念がありました。
ナックル主体にしてしまうと毎回強打を喰らうのは必至で、そんなスタイルは存在するわけがないと信じていました。
馬鹿打ちして自滅した過去の試合を振り返り、なるほどバックスピンがあまりかかっていないボールがやたらと多かったことを理解しました。
その中の1人に張本美和選手がいました。
試合が行われるコートは常に数名のカメラマンが取り囲んでいました。
マスコミは毎回若手の目玉選手を追いかける傾向があり、張本選手はその中でも最年少の注目株でした。
全日本選手権の模様については、以前特派員D氏からのレポートをお届けしました。
そしてD氏はたまたまですが張本選手の試合も見ていました。
少数派の戦型を中心に見ていたため、カットマンと対戦する張本選手の試合が目に留まったのです。
──────────────────────
長年の思い込みを修正
──────────────────────
張本選手は小学生ながら、一般の女子シングルスで3回戦まで進みました。
2回戦と3回戦はカットマンが相手で、それぞれの相手に対する感想が卓球王国の速報に書かれていました。
2回戦のカットマンは切るカットマンでしたが、3回戦の相手はナックル中心のカットマンのため苦戦して負けたとのことでした。
D氏はその速報の文章を読んで、いろいろと考えさせられることがありました。
ペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)であるD氏がカットマンと対戦するときのモットーは、ドライブで押して押しまくり、浮いた返球をスマッシュで撃ち抜くことです。
それが王道であると固く信じ、そこそこ通用してきました。
ただなぜか相手のカットにボールが合わず、ミスを連発して負けることがありました。
王国の速報を読んでいて、その負け方にピーンとくるものがありました。
「そうか、ナックル主体のカットマンか…」
つまり張本選手の試合とはすさまじいレベルの差はあるものの、自分もあまり切らないカットマンには慣れておらず、対処を間違って負けていたことに気がつきました。
D氏はカットマンは大別すると、切るタイプと入れるタイプの2種類がいると捉えていました。
切るタイプはブチ切れカットで強打を防ぎ、入れるタイプはコース取りと変化で勝負するものという理解です。
そのような独自の分類および解釈は、多くの人がそれぞれ理解しやすいように理論立てて持っています。
D氏の頭にはあまり切ってこないカットマンという存在はありましたが、それでもある程度切れているボールを通常の返球として返すものだという固定観念がありました。
ナックル主体にしてしまうと毎回強打を喰らうのは必至で、そんなスタイルは存在するわけがないと信じていました。
馬鹿打ちして自滅した過去の試合を振り返り、なるほどバックスピンがあまりかかっていないボールがやたらと多かったことを理解しました。
2019 .05.18
以前、バタフライからビスカリアというラケットが再販されたことについて触れました。
そしてネットなどでもいろいろな意見が出されています。
今回はそれらを眺めつつ、私なりに感じたことをお話ししたいと思います。
──────────────────────
メダリストの威光は絶大
──────────────────────
ビスカリアの人気の理由を解明する意見として以下のようなものがありました。
あのラケットのフレアグリップはチキータを打つのに最適な形状をしていて、それが張継科選手のプレーと絶妙にマッチしたためであるとのことでした。
それは張選手にインタビューをして得た情報かと言えば恐らくそうではなく、書き込みをした人はバタフライや報道関係の方ではない、あくまでも一般人による推測のはずです。
張選手は多くのラケットを試し、自分にベストの用具を選んではいることでしょう。
ですからビスカリアが最適なのは確かです。
でも具体的にどこがどう気に入っているかという詳細については本人に聞いてみないとわかりません。
この推測による書き込みはさらに飛躍し、だからチキータを使うトップ選手はビスカリアを選ぶという論理に発展しています。
バタフライにはビスカリアと同じブレードを使い、グリップデザインと名前を変えて製品展開をしているラケットがあります。
ズバリ言ってしまえばほぼ同じラケットであるわけです。
でもやっぱりビスカリアの人気があるのはゴールドメダリストが使ったことで広く認知され、その結果使用者が増えたということだと私は捉えています。
もし張選手がビスカリアと同時期に発売されたアイオライトを使っていたとすれば、アイオライト人気であったはずです。
ただ一方で、張選手が利用していることがビスカリア人気の100%の理由であるとも考えていません。
さまざまな特殊素材ラケットがある中、アリレートカーボンという2種類の素材の組み合わせは、あまたのプレーヤーによる使用実績があります。
同じシリーズで特殊素材を変えたバリエーションがあり、単純な弾みだけならアリレートカーボンよりもカーボンだけのほうが勝っています。
打球感など総合的に判断がなされた結果、現状ではより弾むカーボンよりアリレートカーボンが多くの選手の支持を得ているのだと思います。
また最大手のバタフライは製品の品質管理には定評があります。
なので私は私なりの勝手な分析をすると、ビスカリア人気の原因は以下のようになります。
金メダリスト張選手の影響:40%
アリレートカーボンを使用したラケットであること:20%
品質に対する信頼:10%
そしてネットなどでもいろいろな意見が出されています。
今回はそれらを眺めつつ、私なりに感じたことをお話ししたいと思います。
──────────────────────
メダリストの威光は絶大
──────────────────────
ビスカリアの人気の理由を解明する意見として以下のようなものがありました。
あのラケットのフレアグリップはチキータを打つのに最適な形状をしていて、それが張継科選手のプレーと絶妙にマッチしたためであるとのことでした。
それは張選手にインタビューをして得た情報かと言えば恐らくそうではなく、書き込みをした人はバタフライや報道関係の方ではない、あくまでも一般人による推測のはずです。
張選手は多くのラケットを試し、自分にベストの用具を選んではいることでしょう。
ですからビスカリアが最適なのは確かです。
でも具体的にどこがどう気に入っているかという詳細については本人に聞いてみないとわかりません。
この推測による書き込みはさらに飛躍し、だからチキータを使うトップ選手はビスカリアを選ぶという論理に発展しています。
バタフライにはビスカリアと同じブレードを使い、グリップデザインと名前を変えて製品展開をしているラケットがあります。
ズバリ言ってしまえばほぼ同じラケットであるわけです。
でもやっぱりビスカリアの人気があるのはゴールドメダリストが使ったことで広く認知され、その結果使用者が増えたということだと私は捉えています。
もし張選手がビスカリアと同時期に発売されたアイオライトを使っていたとすれば、アイオライト人気であったはずです。
ただ一方で、張選手が利用していることがビスカリア人気の100%の理由であるとも考えていません。
さまざまな特殊素材ラケットがある中、アリレートカーボンという2種類の素材の組み合わせは、あまたのプレーヤーによる使用実績があります。
同じシリーズで特殊素材を変えたバリエーションがあり、単純な弾みだけならアリレートカーボンよりもカーボンだけのほうが勝っています。
打球感など総合的に判断がなされた結果、現状ではより弾むカーボンよりアリレートカーボンが多くの選手の支持を得ているのだと思います。
また最大手のバタフライは製品の品質管理には定評があります。
なので私は私なりの勝手な分析をすると、ビスカリア人気の原因は以下のようになります。
金メダリスト張選手の影響:40%
アリレートカーボンを使用したラケットであること:20%
品質に対する信頼:10%
2019 .05.04
ゴールデンウィークの真っただ中、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
世界選手権が終わり令和に突入しました。
なんでもニッタクは「令和」の文字が入ったピン球を作り配布していたそうです。
──────────────────────
購入は2段階で行われる
──────────────────────
さていよいよ来年は東京オリンピックです。
オリンピックは4年に一度開催されるイベントですが、自国開催となると先進国でも一生に一度くらいのチャンスと言う人がいます。
それはあながち誇張ではなく、次に日本でオリンピックが開催される時には私はまだ生きているのか何とも言えません。
卓球が開催競技から外されるかもしれませんし、オリンピックそのものが存続し続けるのかという不安もあります。
従って来年は卓球競技のどこかの日程で観戦ができないか検討中です。
まだ1年以上ありますが、チケットの申し込みはもうすぐ始まります。
まず抽選申し込みがあり、その後2020年に入ってから早いもの順での販売が行われます。
絶対に行くと決めている人は、迷わず抽選申し込みを行いましょう。
5月9日から公式販売サイトで受付が始まります。
卓球会場の東京体育館は座席数10000席で、その何割かはわかりませんが抽選申し込みで決まることになります。
世界選手権が終わり令和に突入しました。
なんでもニッタクは「令和」の文字が入ったピン球を作り配布していたそうです。
──────────────────────
購入は2段階で行われる
──────────────────────
さていよいよ来年は東京オリンピックです。
オリンピックは4年に一度開催されるイベントですが、自国開催となると先進国でも一生に一度くらいのチャンスと言う人がいます。
それはあながち誇張ではなく、次に日本でオリンピックが開催される時には私はまだ生きているのか何とも言えません。
卓球が開催競技から外されるかもしれませんし、オリンピックそのものが存続し続けるのかという不安もあります。
従って来年は卓球競技のどこかの日程で観戦ができないか検討中です。
まだ1年以上ありますが、チケットの申し込みはもうすぐ始まります。
まず抽選申し込みがあり、その後2020年に入ってから早いもの順での販売が行われます。
絶対に行くと決めている人は、迷わず抽選申し込みを行いましょう。
5月9日から公式販売サイトで受付が始まります。
卓球会場の東京体育館は座席数10000席で、その何割かはわかりませんが抽選申し込みで決まることになります。
2019 .04.20
練習後に数人で入った喫茶店での話について書いてみます。
卓球の試合に関するご意見が多かったため、それに関するものに絞りました。
個性的なメンツなので一味違った内容となっています。
──────────────────────
ミスを防ぐ仕組み
──────────────────────
Tリーグで規定違反となった試合が少しありました。
それぞれの選手にはランクがついています。
試合の質の維持のためでしょうか、高いランクの選手を多く出場させるような規定が設けられています。
女子の試合であったのは、日本ペイントマレッツでAランクの選手2名が出場し、それが規定に反していることが後で問題となりました。
対戦相手のメンバー表をにらみつつ、どのオーダーでいくかを試合ごとに悩みながら考えます。
当然諸々の規定は理解していたものの、思考をあれこれと巡らせる過程で満たしているかどうかの確認が漏れてしまったのだと思います。
それについては同情する意見が聞かれました。
でもそれと同時に再発を防ぐことも大切です。
両チームがオーダーを出すと、それがシステムに登録され会場のモニターに表示されます。
そのシステムに、選手のデータベースと照合して規定を満たしているかのチェック機能をつけるべきだという意見が出ました。
せっかくコンピューターを使っているのですから、ただ表示するだけでなく人間のミスも検出させればよいというのは至極当然なことですね。
これで思い出したのがマクドナルドのレジです。
ある日セットメニューを頼んだところ、各商品が単品として計算され、割高な料金が請求されました。
レジで応対していたスタッフは、どことなくお仕事を始めてからまだ日が浅いようでした。
間違いは良くないことですが、疑問に感じたのはレジのプログラムです。
この手のミスは全世界のどこかの店舗で必ず起きているはずです。
ヒューマンエラーを見つけ、セットメニューの料金に自動補正する仕組みがなぜ導入されていないのか不思議でなりません。
卓球の試合に関するご意見が多かったため、それに関するものに絞りました。
個性的なメンツなので一味違った内容となっています。
──────────────────────
ミスを防ぐ仕組み
──────────────────────
Tリーグで規定違反となった試合が少しありました。
それぞれの選手にはランクがついています。
試合の質の維持のためでしょうか、高いランクの選手を多く出場させるような規定が設けられています。
女子の試合であったのは、日本ペイントマレッツでAランクの選手2名が出場し、それが規定に反していることが後で問題となりました。
対戦相手のメンバー表をにらみつつ、どのオーダーでいくかを試合ごとに悩みながら考えます。
当然諸々の規定は理解していたものの、思考をあれこれと巡らせる過程で満たしているかどうかの確認が漏れてしまったのだと思います。
それについては同情する意見が聞かれました。
でもそれと同時に再発を防ぐことも大切です。
両チームがオーダーを出すと、それがシステムに登録され会場のモニターに表示されます。
そのシステムに、選手のデータベースと照合して規定を満たしているかのチェック機能をつけるべきだという意見が出ました。
せっかくコンピューターを使っているのですから、ただ表示するだけでなく人間のミスも検出させればよいというのは至極当然なことですね。
これで思い出したのがマクドナルドのレジです。
ある日セットメニューを頼んだところ、各商品が単品として計算され、割高な料金が請求されました。
レジで応対していたスタッフは、どことなくお仕事を始めてからまだ日が浅いようでした。
間違いは良くないことですが、疑問に感じたのはレジのプログラムです。
この手のミスは全世界のどこかの店舗で必ず起きているはずです。
ヒューマンエラーを見つけ、セットメニューの料金に自動補正する仕組みがなぜ導入されていないのか不思議でなりません。
2019 .04.06
今回は一度だけお会いしたことのある方について書いてみたいと思います。
お名前は分からないのでAさんということにしておきます。
練習をご一緒させていただき、そのあとベンチで20分程度お話をしました。
──────────────────────
弾むラケットを求めて
──────────────────────
Aさんは推定30歳前後の男性です。
中学の3年間卓球部に所属し、半年ほど前から卓球を再開しました。
再開した当初はルールや用具の変化に戸惑いました。
中でも一番気になったのはボールがあまり飛ばなくなった点でした。
中学の時に使っていたのは特殊素材は入っていない、木材のみを使った7枚合板のラケットでした。
Aさんはこのラケットではダメだと感じ、高反発のものを調べました。
最初に目に留まったのは、最大手バタフライのガレイディアT5000でした。
特殊素材は純粋なカーボンだけで、アリレートカーボンやZLファイバーのラケットよりも反発性能は高い製品です。
そのラケットにTSPのスピード重視の裏ソフト、ヴェンタススピードを貼りました。
結構なかっ飛び用具です。
期待に胸を膨らませボールを打ってみました。
中学時代の用具よりは確実に弾みは向上したものの、イメージしたほどの効果は得られませんでした。
しばらくそのラケットで打ち続けましたがモヤモヤは解消しません。
ある日、練習場でおじさんが使っていた単板ペンホルダーで何気なく玉突きをしてみました。
その独特の打球感と分厚いラケットの感触に「これだ!」とひらめきました。
お名前は分からないのでAさんということにしておきます。
練習をご一緒させていただき、そのあとベンチで20分程度お話をしました。
──────────────────────
弾むラケットを求めて
──────────────────────
Aさんは推定30歳前後の男性です。
中学の3年間卓球部に所属し、半年ほど前から卓球を再開しました。
再開した当初はルールや用具の変化に戸惑いました。
中でも一番気になったのはボールがあまり飛ばなくなった点でした。
中学の時に使っていたのは特殊素材は入っていない、木材のみを使った7枚合板のラケットでした。
Aさんはこのラケットではダメだと感じ、高反発のものを調べました。
最初に目に留まったのは、最大手バタフライのガレイディアT5000でした。
特殊素材は純粋なカーボンだけで、アリレートカーボンやZLファイバーのラケットよりも反発性能は高い製品です。
そのラケットにTSPのスピード重視の裏ソフト、ヴェンタススピードを貼りました。
結構なかっ飛び用具です。
期待に胸を膨らませボールを打ってみました。
中学時代の用具よりは確実に弾みは向上したものの、イメージしたほどの効果は得られませんでした。
しばらくそのラケットで打ち続けましたがモヤモヤは解消しません。
ある日、練習場でおじさんが使っていた単板ペンホルダーで何気なく玉突きをしてみました。
その独特の打球感と分厚いラケットの感触に「これだ!」とひらめきました。
以前、小学生との試合についてお話したことがありました。
今回はそれとはまた違う内容で、彼ら・彼女らとのやり取りを通して感じたことを思いつくままに書いてみます。
──────────────────────
子供に対しムキになってはいけない
──────────────────────
低学年だと体格の関係でフォア前にサーブを出すのははばかられます。
冗談のつもりなのでしょうけど、強い逆回転をかけてフォア前に山なりのボールを出し、自コートに戻ってくるサーブを放つ意地悪な大人もたまにいます。
当然のことながらノータッチで得点できてしまいます。
私はその時審判をしていましたが、マイルールを強制発動しレットの判定をしました。
どこかのクラブに所属するなど毎日練習している小学生なら、結構ラリーが続き大人といい勝負になることがあります。
私と同等の週1回2時間程度しか卓球をしない者は、打球精度に難点があり先にミスをしてしまうのでしょう。
ラリーになると五分五分か、あるいはそれ以下の大人が考える卑怯な秘策はやはりサーブです。
初級者の鬼門である横回転系や、ナックルと下回転を混ぜて出す人など、姑息な工夫でラリーでの失点を補っている場面を目にします。
そういう私もワンパターンではいけないと思い、少しうまい小学生にはまやかしモーションを入れたナックルサーブを出すことがあります。
見事に引っかかってくれる場合もありますし、2度目はばれてノータッチで抜かれてしまったこともありました。
対処法が分からず、何度も同じサーブを出されて失点を続けている小学生を見たことがあります。
それについては相手の大人の方がもう少し考えてくれたらいいのにと、残念な気持ちになります。
今回はそれとはまた違う内容で、彼ら・彼女らとのやり取りを通して感じたことを思いつくままに書いてみます。
──────────────────────
子供に対しムキになってはいけない
──────────────────────
低学年だと体格の関係でフォア前にサーブを出すのははばかられます。
冗談のつもりなのでしょうけど、強い逆回転をかけてフォア前に山なりのボールを出し、自コートに戻ってくるサーブを放つ意地悪な大人もたまにいます。
当然のことながらノータッチで得点できてしまいます。
私はその時審判をしていましたが、マイルールを強制発動しレットの判定をしました。
どこかのクラブに所属するなど毎日練習している小学生なら、結構ラリーが続き大人といい勝負になることがあります。
私と同等の週1回2時間程度しか卓球をしない者は、打球精度に難点があり先にミスをしてしまうのでしょう。
ラリーになると五分五分か、あるいはそれ以下の大人が考える卑怯な秘策はやはりサーブです。
初級者の鬼門である横回転系や、ナックルと下回転を混ぜて出す人など、姑息な工夫でラリーでの失点を補っている場面を目にします。
そういう私もワンパターンではいけないと思い、少しうまい小学生にはまやかしモーションを入れたナックルサーブを出すことがあります。
見事に引っかかってくれる場合もありますし、2度目はばれてノータッチで抜かれてしまったこともありました。
対処法が分からず、何度も同じサーブを出されて失点を続けている小学生を見たことがあります。
それについては相手の大人の方がもう少し考えてくれたらいいのにと、残念な気持ちになります。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。