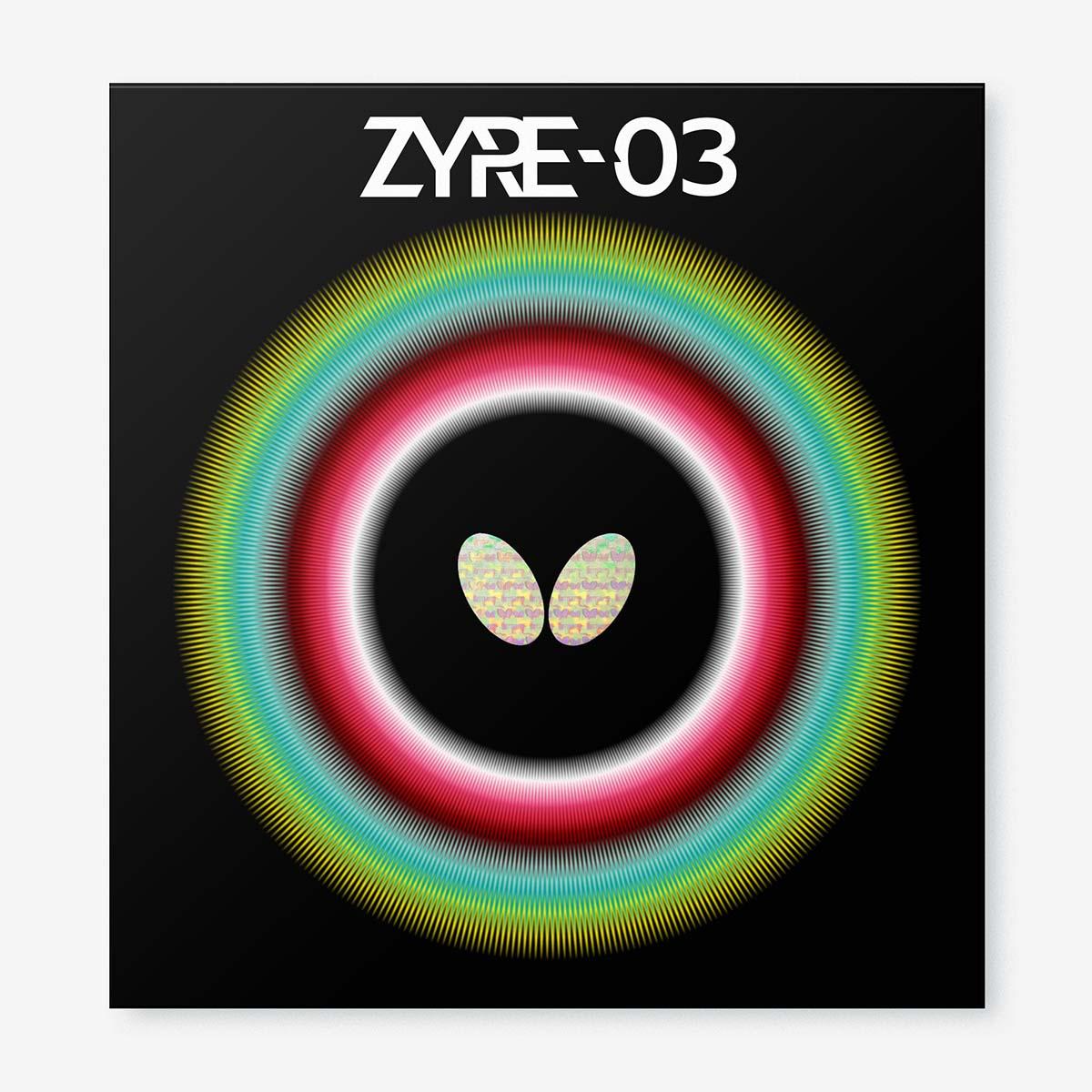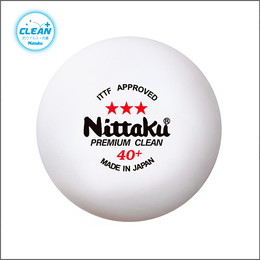今回も引き続き、現在の卓球ルールが妥当かどうかを考えてみたいと思います。
前回は1ゲーム11点制の是非についてお話しました。
今回は用具関連の規定について、私の周囲の方の意見をご紹介いたします。
──────────────────────
ラケットは木材が85%
──────────────────────
現行ルールでは、ラケットの素材は85%以上が天然木材であることと定められています。
これを見直してみることについて考えてみました。
ただしその前に85%という数値は重さなのか体積なのか、そのあたりをはっきりさせておきたいと思います。
85%以上と規定しているのは体積であり、要するに厚さです。
そしてラケットのブレード部分についてであって、ブレードに追加で貼り合わせたグリップについては言及されていません。
つまりグリップ部分にはめ込まれたプラスチック製のロゴなどは対象外ということです。
85%以上を保つ範囲で、木材同士を貼り合わせる接着層の部分に繊維材料による補強が可能となっています。
他にも厳密な規定がありますが、それについてここでは割愛させていただきます。
この85%という制限の見直しや撤廃について意見が出ました。
結果としては各自バラバラの主張で意見の集約という形になりませんでした。
前回は1ゲーム11点制の是非についてお話しました。
今回は用具関連の規定について、私の周囲の方の意見をご紹介いたします。
──────────────────────
ラケットは木材が85%
──────────────────────
現行ルールでは、ラケットの素材は85%以上が天然木材であることと定められています。
これを見直してみることについて考えてみました。
ただしその前に85%という数値は重さなのか体積なのか、そのあたりをはっきりさせておきたいと思います。
85%以上と規定しているのは体積であり、要するに厚さです。
そしてラケットのブレード部分についてであって、ブレードに追加で貼り合わせたグリップについては言及されていません。
つまりグリップ部分にはめ込まれたプラスチック製のロゴなどは対象外ということです。
85%以上を保つ範囲で、木材同士を貼り合わせる接着層の部分に繊維材料による補強が可能となっています。
他にも厳密な規定がありますが、それについてここでは割愛させていただきます。
この85%という制限の見直しや撤廃について意見が出ました。
結果としては各自バラバラの主張で意見の集約という形になりませんでした。
今回は現在の卓球ルールが妥当かどうかを考えてみたいと思います。
見るスポーツとしてはどうなのか、自分がやるスポーツとしてはどうなのか、その他多面的な観点から周囲の方の意見をまとめてみました。
──────────────────────
1ゲームは何点であるべきか
──────────────────────
昔は1ゲーム21点で、それが現在では11点とほぼ半分に変わりました。
年輩の方からも11点制は比較的好意的な意見が聞かれます。
21点というのはバレーボールやバドミントンで採用されていて、ネットを挟んで対戦する競技のスタンダードというイメージがあったそうです。
11点制については以下のようなメリットが挙げられています。
スピーディーな試合展開になってメリハリが付くことにより、観戦者がより楽しめるようになる。
競った試合や逆転劇が起きる可能性が上がり、興奮や感動シーンが増える。
つまり観戦者側のメリットが強調されています。
各競技団体は自分たちのファンを増やすことを考えていて、卓球はその点を重視した改革に踏み切ったのだと考えています。
でもそれだけでなく11点制は選手側にもメリットが大きいと思います。
21点制の頃は点差が開くと、不利な側の選手が途中で投げやりになってしまうことが少なくなかったそうです。
今でもそれはあると言えばあります。
しかし21点制だと例えば序盤で10点差がつき、21点で終わるまで投げやりモードの惰性プレーを長々と見せつけられるのはたまったもんではないと容易に想像がつきます。
見るスポーツとしてはどうなのか、自分がやるスポーツとしてはどうなのか、その他多面的な観点から周囲の方の意見をまとめてみました。
──────────────────────
1ゲームは何点であるべきか
──────────────────────
昔は1ゲーム21点で、それが現在では11点とほぼ半分に変わりました。
年輩の方からも11点制は比較的好意的な意見が聞かれます。
21点というのはバレーボールやバドミントンで採用されていて、ネットを挟んで対戦する競技のスタンダードというイメージがあったそうです。
11点制については以下のようなメリットが挙げられています。
スピーディーな試合展開になってメリハリが付くことにより、観戦者がより楽しめるようになる。
競った試合や逆転劇が起きる可能性が上がり、興奮や感動シーンが増える。
つまり観戦者側のメリットが強調されています。
各競技団体は自分たちのファンを増やすことを考えていて、卓球はその点を重視した改革に踏み切ったのだと考えています。
でもそれだけでなく11点制は選手側にもメリットが大きいと思います。
21点制の頃は点差が開くと、不利な側の選手が途中で投げやりになってしまうことが少なくなかったそうです。
今でもそれはあると言えばあります。
しかし21点制だと例えば序盤で10点差がつき、21点で終わるまで投げやりモードの惰性プレーを長々と見せつけられるのはたまったもんではないと容易に想像がつきます。
2025 .08.02
昨年ユニークなラケットの握り方についてお話をさせていただいたことがあります。
今回はその続編をお届けしたいと思います。
──────────────────────
以前の回のおさらい
──────────────────────
VICTAS社のアドバイザリースタッフに小塩悠菜さんという選手がいます。
彼女はラケットを変わった形で握っています。
シェークハンドラケットをペンホルダーとして使っています。
そしてそういう場合、普通はフォア面に親指と人差指を、バック面に残りの3本の指を当てて支えます。
ところが小塩さんは人差し指も裏側に回し、フォア側は親指だけ、バック側は4本の指で支えるというかなり独創的なグリップでプレーをされています。
私はそのグリップを勝手に「皿づかみ」と形容し、自分でも試して感想を述べてみました。
さて今回は全く同じ握り方ではありませんが、それに近いグリップを試していた方をご紹介します。
お名前は分からないので、似ている私の知人の名前で坂井さんということにしておきます。
今回はその続編をお届けしたいと思います。
──────────────────────
以前の回のおさらい
──────────────────────
VICTAS社のアドバイザリースタッフに小塩悠菜さんという選手がいます。
彼女はラケットを変わった形で握っています。
シェークハンドラケットをペンホルダーとして使っています。
そしてそういう場合、普通はフォア面に親指と人差指を、バック面に残りの3本の指を当てて支えます。
ところが小塩さんは人差し指も裏側に回し、フォア側は親指だけ、バック側は4本の指で支えるというかなり独創的なグリップでプレーをされています。
私はそのグリップを勝手に「皿づかみ」と形容し、自分でも試して感想を述べてみました。
さて今回は全く同じ握り方ではありませんが、それに近いグリップを試していた方をご紹介します。
お名前は分からないので、似ている私の知人の名前で坂井さんということにしておきます。
今回はたまたま見たネット上の動画について、私なりに感じたことを書いてみたいと思います。
WRM(ワールドラバーマーケット)のぐっちいさんがマレーシアに行った時の模様を記録・編集した動画です。
──────────────────────
続々登場ペンホルダー
──────────────────────
内容は多岐にわたり、現地選手との試合、日本人卓球クラブでの講習会、卓球ショップ訪問などでした。
現地の方との試合映像ではペンホルダーの人がいました。
私はペンを絶滅危惧種と表現したことが何度かありました。
ただペンホルダー使いは地球上からいなくなってしまったわけではなく、数が減ってしまったという状態です。
マレーシアは多民族国家で中華系の人も大勢いらっしゃいます。
そのようなこともあり、ペンで卓球をされている方が少しはいると解釈しました。
ところがペンの人が次々と現れ合計で4人も登場しました。
もちろんたまたまお邪魔した所で、たまたま試合をした人達がそうだったという偶然なのですが、東南アジアでも巷の競技者にはペンは結構いるという印象を強く持ちました。
さらにその4名の内訳は粒高が2人、片面だけにラバーを貼った角型日本式ペンホルダーが2人というとても偏ったメンバーでした。
又聞きですが南米ブラジルにもペンの人が多くいたそうです。
ひょっとしたらリオデジャネイロの卓球場に立ち寄ると、予想外にペンホルダーを見かけることができるのかもしれません。
卓球愛好家の中には保守的な人もいれば、私のように何かときめくことはないか追い求めている人もいます。
今回は後者の方の失敗談についてお話ししたいと思います。
──────────────────────
もどかしい球さばき
──────────────────────
中川さん(仮名)とは某卓球場で少し前に初めてお会いしました。
最初は普通に肩慣らしのフォア打ちから~と思っていたら、初めて使うラケットの試し打ちがしたいとのことで、なぜかバックショートから入りました。
中ペン(中国式ペンホルダー)を握っていて、粒高ラバーを貼っているようです。
ポコンポコンとこもった音が響き、それなりの打ちミスが混ざりながらふわっとした棒球が返ってきました。
何本か打った後、何となく中川さんの表情が冴えないように見えました。
「すいません。ドライブや速いボールも混ぜてもらえますか」
ご要望に応じてループドライブやフラット打ちの強打も放ちました。
典型的な粒高ラバー的ボールが返ってくることもたまにありますが、シビアな球質のものは少なめでした。
続いてツッツキ、そしてつつかれたボールをナックルプッシュされていました。
次に粒高でのフォア打ち、反対の面に貼った裏ソフトでのドライブ、裏ソフトでサーブを出してからラケットの反転等、いわゆるペン粒プレーヤーの技術を怒涛の勢いで一通り試しました。
合間合間に自分を叱責するつぶやきがあり、ぎこちない感じは否めないものの真剣に取り組んでいる意気込みがひしひしと伝わってきました。
そして最後に「ダメだ!」と叫び、私に対してはお礼を言われて終了しました。
今回は後者の方の失敗談についてお話ししたいと思います。
──────────────────────
もどかしい球さばき
──────────────────────
中川さん(仮名)とは某卓球場で少し前に初めてお会いしました。
最初は普通に肩慣らしのフォア打ちから~と思っていたら、初めて使うラケットの試し打ちがしたいとのことで、なぜかバックショートから入りました。
中ペン(中国式ペンホルダー)を握っていて、粒高ラバーを貼っているようです。
ポコンポコンとこもった音が響き、それなりの打ちミスが混ざりながらふわっとした棒球が返ってきました。
何本か打った後、何となく中川さんの表情が冴えないように見えました。
「すいません。ドライブや速いボールも混ぜてもらえますか」
ご要望に応じてループドライブやフラット打ちの強打も放ちました。
典型的な粒高ラバー的ボールが返ってくることもたまにありますが、シビアな球質のものは少なめでした。
続いてツッツキ、そしてつつかれたボールをナックルプッシュされていました。
次に粒高でのフォア打ち、反対の面に貼った裏ソフトでのドライブ、裏ソフトでサーブを出してからラケットの反転等、いわゆるペン粒プレーヤーの技術を怒涛の勢いで一通り試しました。
合間合間に自分を叱責するつぶやきがあり、ぎこちない感じは否めないものの真剣に取り組んでいる意気込みがひしひしと伝わってきました。
そして最後に「ダメだ!」と叫び、私に対してはお礼を言われて終了しました。
かなり前に特注ラケットについてお話ししたことがありました。
特注についての過去を振り返り、また現在はどのような状況なのか見てみたいと思います。
──────────────────────
古き良き時代
──────────────────────
昔は巷の卓球愛好家でも特注ラケットを注文できる選択肢が複数ありました。
20年前の2005年だと、カタログなどで公式に受け付けをPRしていたのはニッタクとバタフライの2社でした。
他にもコクタクなどが応じていて、見事に目の詰まったコクタク製スペシャル単板ラケットの持ち主から自慢の一本を触らせてもらったことがありました。
当時のお値段は選択するブレードの種類によりいくつかあり、ニッタクが11550~23625円、バタフライは15750~31500円でした。
その後バタフライは転売問題がきっかけとなったようで特注の受け付けを終了しました。
10年前の2015年当時は、ニッタクの特注ラケット価格は23760~32400円でした。
さて現在はどうなっているのでしょうか。
特注についての過去を振り返り、また現在はどのような状況なのか見てみたいと思います。
──────────────────────
古き良き時代
──────────────────────
昔は巷の卓球愛好家でも特注ラケットを注文できる選択肢が複数ありました。
20年前の2005年だと、カタログなどで公式に受け付けをPRしていたのはニッタクとバタフライの2社でした。
他にもコクタクなどが応じていて、見事に目の詰まったコクタク製スペシャル単板ラケットの持ち主から自慢の一本を触らせてもらったことがありました。
当時のお値段は選択するブレードの種類によりいくつかあり、ニッタクが11550~23625円、バタフライは15750~31500円でした。
その後バタフライは転売問題がきっかけとなったようで特注の受け付けを終了しました。
10年前の2015年当時は、ニッタクの特注ラケット価格は23760~32400円でした。
さて現在はどうなっているのでしょうか。
タイトルの通り、今回はメダル豊作となった世界選手権についてお話しします。
そろそろ熱気が冷めてしまっていて全然旬の話題じゃないとお叱りを受けるかもしれませんが、まあそう言わずしばしお付き合い願います。
そしていつものように、私および練習仲間の個性的な意見をご紹介いたします。
──────────────────────
ピンクの台を横から映す
──────────────────────
まず複数の人が口々に指摘したのが、例のピンクの卓球台です。
普通のピンクではなく、ショッキングピンクに赤成分を追加したピンクという感じでしょうか。
また、ネットやサポート、台の縁に引かれたラインは金色という独特の配色です。
「オシャレ」「ボールは見にくくないのか」などの感想がありました。
華やかさを印象付けるための思い切った試みなのでしょう。
カラーラバーの採用は思うように進まず率直に申し上げて失敗しています。
それにめげず、卓球関係者の頭の中にはほとんどなかった斬新な色使いでアピールする姿勢は評価したいと思います。
ピンクに慣れるよう選手への配慮も行われていて、試合の合間にちらっと映る練習場所の台も同じ色になっていました。
テレ東の放送について意見が割れたのは試合映像のアングルでした。
近年の傾向で横方向からの撮影を基本としています。
全体を俯瞰しているため一般の方には分かりやすい見せ方であるのは、悔しいですが事実として認めたいと思います。
しかし卓球競技者なら縦方向の映像にしてもらいたい人が多いと考えています。
いつもの卓球台に立っている感覚で、どういうやり取りをしているかが確認できるからです。
今回の映像は従来の横映像よりさらに高い位置からの撮影となっていました。
それも練習仲間の何名かの人にとっては違和感が高かったと不評でした。
ざっとまとめると、ピンクの台はOK、映像は縦アングルにして欲しいがちょっと無理かなという所です。
そろそろ熱気が冷めてしまっていて全然旬の話題じゃないとお叱りを受けるかもしれませんが、まあそう言わずしばしお付き合い願います。
そしていつものように、私および練習仲間の個性的な意見をご紹介いたします。
──────────────────────
ピンクの台を横から映す
──────────────────────
まず複数の人が口々に指摘したのが、例のピンクの卓球台です。
普通のピンクではなく、ショッキングピンクに赤成分を追加したピンクという感じでしょうか。
また、ネットやサポート、台の縁に引かれたラインは金色という独特の配色です。
「オシャレ」「ボールは見にくくないのか」などの感想がありました。
華やかさを印象付けるための思い切った試みなのでしょう。
カラーラバーの採用は思うように進まず率直に申し上げて失敗しています。
それにめげず、卓球関係者の頭の中にはほとんどなかった斬新な色使いでアピールする姿勢は評価したいと思います。
ピンクに慣れるよう選手への配慮も行われていて、試合の合間にちらっと映る練習場所の台も同じ色になっていました。
テレ東の放送について意見が割れたのは試合映像のアングルでした。
近年の傾向で横方向からの撮影を基本としています。
全体を俯瞰しているため一般の方には分かりやすい見せ方であるのは、悔しいですが事実として認めたいと思います。
しかし卓球競技者なら縦方向の映像にしてもらいたい人が多いと考えています。
いつもの卓球台に立っている感覚で、どういうやり取りをしているかが確認できるからです。
今回の映像は従来の横映像よりさらに高い位置からの撮影となっていました。
それも練習仲間の何名かの人にとっては違和感が高かったと不評でした。
ざっとまとめると、ピンクの台はOK、映像は縦アングルにして欲しいがちょっと無理かなという所です。
2025 .05.24
前々回はネットインについて書いてみました。
卓球ではネットインやエッジによる得点に対しては謝るのがマナーとなっています。
今回はそういった謝る場面について書いてみたいと思います。
──────────────────────
ネットエッジは失礼なのか
──────────────────────
ネットインやエッジの影響で得失点が決する事になった場合、得点した側が済まないという意思を示すこととなっています。
それは事実上の世界共通マナーです。
さてここで頭をまっさらにして考えてみることにします。
ネットインやエッジでラリーが終了しました。
その成り行きをごく自然に眺めると「あー、ぎりぎり入ったね」と解釈できるでしょう。
ボールのわずかな動きで得失点が左右する事象が発生したのです。
これを踏まえ得点できた側は、純粋に考えてラッキーだと感じるのが普通ではないでしょうか。
頭が卓球マナーに染まっていない初心者が試合をしていて、ネットインやエッジで得点すればガッツポーズを取っているのを目にします。
なので改めて考え直してみれば、ネットインやエッジで得点してもそれは喜ぶべき場面なのだと私は考えます。
ところがどうしようもない不可抗力による結果で得点できたことに対し、大人の配慮を見せる所作が自然発生的に広がったのでしょう。
「僕は幸運にも得点できたけど、紙一重で君は失点となったことに同情するよ」みたいな感じで。
そしてなんだか日本では手のひらを相手に向けて「済みません」と言う、動作+言葉がスタンダードになっています。
これを強いられる圧力は市民大会など巷の試合ほうが顕著で、トップ選手の試合はまだ控えめなように思えます。
ボールを拾いに行った相手が、台の前に戻ってきたそのタイミングまで待って謝るのが正式だと考えている厳格な人もいるとか。
もちろん何かに対して謝る場合は、相手に対し真摯に向き合う状態で行うのは当然です。
しかし別段無礼を働いたわけではなく、不可抗力に対する同情なのでそこまでの配慮は必要ありません。
海外選手のような人差し指を立てるだけの無言ゼスチャーでも構わないはずです。
厳格な人にそんなスカした(ように見える)ポーズをすると説教を食らうかもしれませんね。
卓球ではネットインやエッジによる得点に対しては謝るのがマナーとなっています。
今回はそういった謝る場面について書いてみたいと思います。
──────────────────────
ネットエッジは失礼なのか
──────────────────────
ネットインやエッジの影響で得失点が決する事になった場合、得点した側が済まないという意思を示すこととなっています。
それは事実上の世界共通マナーです。
さてここで頭をまっさらにして考えてみることにします。
ネットインやエッジでラリーが終了しました。
その成り行きをごく自然に眺めると「あー、ぎりぎり入ったね」と解釈できるでしょう。
ボールのわずかな動きで得失点が左右する事象が発生したのです。
これを踏まえ得点できた側は、純粋に考えてラッキーだと感じるのが普通ではないでしょうか。
頭が卓球マナーに染まっていない初心者が試合をしていて、ネットインやエッジで得点すればガッツポーズを取っているのを目にします。
なので改めて考え直してみれば、ネットインやエッジで得点してもそれは喜ぶべき場面なのだと私は考えます。
ところがどうしようもない不可抗力による結果で得点できたことに対し、大人の配慮を見せる所作が自然発生的に広がったのでしょう。
「僕は幸運にも得点できたけど、紙一重で君は失点となったことに同情するよ」みたいな感じで。
そしてなんだか日本では手のひらを相手に向けて「済みません」と言う、動作+言葉がスタンダードになっています。
これを強いられる圧力は市民大会など巷の試合ほうが顕著で、トップ選手の試合はまだ控えめなように思えます。
ボールを拾いに行った相手が、台の前に戻ってきたそのタイミングまで待って謝るのが正式だと考えている厳格な人もいるとか。
もちろん何かに対して謝る場合は、相手に対し真摯に向き合う状態で行うのは当然です。
しかし別段無礼を働いたわけではなく、不可抗力に対する同情なのでそこまでの配慮は必要ありません。
海外選手のような人差し指を立てるだけの無言ゼスチャーでも構わないはずです。
厳格な人にそんなスカした(ように見える)ポーズをすると説教を食らうかもしれませんね。
2025 .05.10
前回は諸行無常という言葉から始めましたがまさにその通り、オリンピック卓球競技の内容に関する変更が発表されました。
──────────────────────
種目変遷のおさらい
──────────────────────
2028年はアメリカのロサンゼルスで開催されます。
卓球の競技種目は、男女シングルス、混合ダブルスは従来通りですが、男女の団体戦がなくなり、代わりに男女のダブルスと混合の団体戦が追加されます。
ここでオリンピックの卓球競技について振り返ってみます。
卓球は1988年のソウル大会から正式種目として採用されました。
競技人口や競技者の世界的な分布を考えるとかなり遅めの採用でした。
最初は男女シングルス、男女ダブルスの4種目で、それが2004年のアテネ大会まで続きました。
2008年の北京大会から男女ダブルスがなくなり、代わりに男女の団体戦が行われるようになりました。
さらに2020年(開催は2021年)の東京大会で混合ダブルスが追加されました。
そして冒頭に述べた2028年の変更となります。
種目数としては1988~2016年までは4、2020~2024年までは5、2028年は6と少しずつ増えています。
──────────────────────
種目変遷のおさらい
──────────────────────
2028年はアメリカのロサンゼルスで開催されます。
卓球の競技種目は、男女シングルス、混合ダブルスは従来通りですが、男女の団体戦がなくなり、代わりに男女のダブルスと混合の団体戦が追加されます。
ここでオリンピックの卓球競技について振り返ってみます。
卓球は1988年のソウル大会から正式種目として採用されました。
競技人口や競技者の世界的な分布を考えるとかなり遅めの採用でした。
最初は男女シングルス、男女ダブルスの4種目で、それが2004年のアテネ大会まで続きました。
2008年の北京大会から男女ダブルスがなくなり、代わりに男女の団体戦が行われるようになりました。
さらに2020年(開催は2021年)の東京大会で混合ダブルスが追加されました。
そして冒頭に述べた2028年の変更となります。
種目数としては1988~2016年までは4、2020~2024年までは5、2028年は6と少しずつ増えています。
諸行無常という言葉があります。
この世のものは常に変化し続け、変わらないものはないという仏教の教えです。
いきなり何事かと思った方がいらっしゃるかもしれません。
ここでは卓球に関することを書いているので、つまり卓球のルールも無常(無情ではなく無常)だということをお話します。
過去に卓球のルールがどのように変わっていったか振り返ってみたことが何度かありました。
今回は将来におけるルール改正を予想してみたいと思います。
──────────────────────
他競技の動向
──────────────────────
もしかすると将来的にはサーブがネットに当たって相手コートに入ってもレットとはならず、そのまま競技継続となるかもしれません。
卓球以外にもネットでコートを区切り、それを境に双方に分かれて競技する形式のスポーツはいくつかあります。
知名度の高いものでは、バドミントン、バレーボール、テニスがあります。
それら競技でサービスがネットに接触した後、相手コートに入った場合の扱いが段階的に変更されています。
まずバドミントンはレットとはならずそのまま競技継続でした。
バレーボールは失点でしたが、1999年にそれをやめプレーを続けることに変わりました。
テニスは現状卓球と同様レットです。
しかしレットとはしないルールがメジャーではない大会で増えているのです。
そしていずれはウィンブルドンなどの主要大会でも採用されるのではという話が出ています。
つまりサーブのレットはなくしていく流れだと言えるでしょう。
ネットにほんのわずかに触れただけでほぼ影響はなさそうな場合が多いのに、全てやり直しとなるのは理解を得られにくいという考えがあります。
至近距離でギリギリの場所を狙っている卓球は、ボールがネットに触れる場面が多めです。
2度3度とレット(要するにプレーの中断)が続くと観戦者はプチストレスが蓄積してくるでしょう。
従ってサーブのネットインだけをレットとして特化せず、ラリー中にボールがネットに接触したときと同様、プレーを継続するでいいのかもしれません。
この世のものは常に変化し続け、変わらないものはないという仏教の教えです。
いきなり何事かと思った方がいらっしゃるかもしれません。
ここでは卓球に関することを書いているので、つまり卓球のルールも無常(無情ではなく無常)だということをお話します。
過去に卓球のルールがどのように変わっていったか振り返ってみたことが何度かありました。
今回は将来におけるルール改正を予想してみたいと思います。
──────────────────────
他競技の動向
──────────────────────
もしかすると将来的にはサーブがネットに当たって相手コートに入ってもレットとはならず、そのまま競技継続となるかもしれません。
卓球以外にもネットでコートを区切り、それを境に双方に分かれて競技する形式のスポーツはいくつかあります。
知名度の高いものでは、バドミントン、バレーボール、テニスがあります。
それら競技でサービスがネットに接触した後、相手コートに入った場合の扱いが段階的に変更されています。
まずバドミントンはレットとはならずそのまま競技継続でした。
バレーボールは失点でしたが、1999年にそれをやめプレーを続けることに変わりました。
テニスは現状卓球と同様レットです。
しかしレットとはしないルールがメジャーではない大会で増えているのです。
そしていずれはウィンブルドンなどの主要大会でも採用されるのではという話が出ています。
つまりサーブのレットはなくしていく流れだと言えるでしょう。
ネットにほんのわずかに触れただけでほぼ影響はなさそうな場合が多いのに、全てやり直しとなるのは理解を得られにくいという考えがあります。
至近距離でギリギリの場所を狙っている卓球は、ボールがネットに触れる場面が多めです。
2度3度とレット(要するにプレーの中断)が続くと観戦者はプチストレスが蓄積してくるでしょう。
従ってサーブのネットインだけをレットとして特化せず、ラリー中にボールがネットに接触したときと同様、プレーを継続するでいいのかもしれません。
スベってしまうことを恐れず、今回は旬のネタで勝負したいと思います。
いよいよ大阪・関西万博が開催されます。
練習後に居酒屋で雑談している時、万博に卓球パビリオンがあったらという話がポロッと出ました。
その際の内容をご紹介いたします。
──────────────────────
建物の外観
──────────────────────
最初は「あなたは見に行くんですか」という練習仲間それぞれへの問い掛けから始まりました。
その中でスポーツ関連の展示がないですねと意見が出ました。
そこで仮に卓球パビリオンがあったとしたらという妄想に発展しました。
真面目に検討を始めるなら、コンセプトや博覧会テーマとのすり合わせあたりから入るでしょう。
そういう計画性は必要無いので、いきなりパビリオンの形をどうするかについて意見が交わされました。
Aさんから屋根の上にピン球型オブジェを並べる案が出ました。
すると万博の下調べをしていたBさんが、そういうのはどこかにあったはずと答えました。
スマホで検索するとベルギー館がそんな感じでした。
水をイメージした白い球体や繭型の造形物が上部に配され、ピン球ぽく見えます。
出端をくじかれたAさんですが、恐らくリアルの万博でもあまりに似すぎたパビリオンは調整が入って被らないようにしているはずだと納得の意見が出ました。
結局ラケットを斜めに傾けて寝かせた形でいいじゃないと、かなり落ち着いた外観に決まりました。
ただしその傍らにはボールを模した球体のディスプレーがあり、来場者の目を引き付ける役目を担います。
ラスベガスにある巨大なやつのミニチュア版ですね。
いよいよ大阪・関西万博が開催されます。
練習後に居酒屋で雑談している時、万博に卓球パビリオンがあったらという話がポロッと出ました。
その際の内容をご紹介いたします。
──────────────────────
建物の外観
──────────────────────
最初は「あなたは見に行くんですか」という練習仲間それぞれへの問い掛けから始まりました。
その中でスポーツ関連の展示がないですねと意見が出ました。
そこで仮に卓球パビリオンがあったとしたらという妄想に発展しました。
真面目に検討を始めるなら、コンセプトや博覧会テーマとのすり合わせあたりから入るでしょう。
そういう計画性は必要無いので、いきなりパビリオンの形をどうするかについて意見が交わされました。
Aさんから屋根の上にピン球型オブジェを並べる案が出ました。
すると万博の下調べをしていたBさんが、そういうのはどこかにあったはずと答えました。
スマホで検索するとベルギー館がそんな感じでした。
水をイメージした白い球体や繭型の造形物が上部に配され、ピン球ぽく見えます。
出端をくじかれたAさんですが、恐らくリアルの万博でもあまりに似すぎたパビリオンは調整が入って被らないようにしているはずだと納得の意見が出ました。
結局ラケットを斜めに傾けて寝かせた形でいいじゃないと、かなり落ち着いた外観に決まりました。
ただしその傍らにはボールを模した球体のディスプレーがあり、来場者の目を引き付ける役目を担います。
ラスベガスにある巨大なやつのミニチュア版ですね。
運動をしているといろいろな方面にボディケアが必要になります。
今回は卓球に関する内容は少なめですが、お体に関することについて書いてみたいと思います。
──────────────────────
指のタコ
──────────────────────
今は大多数の人がシェークハンドであり、練習をやり込むと手のひらにマメができてくるはずです。
私は少数派のペンホルダーなので、手のひらはきれいなツルツル状態です。
ペンの人だと何も影響がないのかと言えばそうではなく、指でつまむため人差し指と中指に変化が生じます。
具体的には人差し指の場合だと、中指側の爪の横の皮膚が盛り上がり半透明の細長いタコが形成されます。
人差し指をグリップに巻き付ける形にした際、ブレード面に強く押し当てる部分になります。
これは日ペン(日本式ペンホルダー)でも中ペン(中国式ペンホルダー)でも変わりません。
冬場だと、このタコがカチカチになって割れ、あかぎれ状態となって痛みや出血を伴うことがあります。
定期的に爪切りで盛り上がった部分をカットし、ひび割れた際はお風呂上がりにクリームを塗ります。
中指の方も、人差し指側の爪の横に同じような半透明のタコができます。
ラケットの裏面を支える力と摩擦でできるものです。
こちらも高く盛り上がってきた場合爪切りで切り取っています。
ある日何気なくテレビを見ていたら、看護師さんがハンドクリームを塗っているシーンがありました。
2本の指をクリームの容器にズボッと差し込んで景気よくすくい、両手をヌルヌルの状態にしていました。
私はカサついた部分にだけ押し当てるように塗っていたので、使用量の違いに唖然としました。
今回は卓球に関する内容は少なめですが、お体に関することについて書いてみたいと思います。
──────────────────────
指のタコ
──────────────────────
今は大多数の人がシェークハンドであり、練習をやり込むと手のひらにマメができてくるはずです。
私は少数派のペンホルダーなので、手のひらはきれいなツルツル状態です。
ペンの人だと何も影響がないのかと言えばそうではなく、指でつまむため人差し指と中指に変化が生じます。
具体的には人差し指の場合だと、中指側の爪の横の皮膚が盛り上がり半透明の細長いタコが形成されます。
人差し指をグリップに巻き付ける形にした際、ブレード面に強く押し当てる部分になります。
これは日ペン(日本式ペンホルダー)でも中ペン(中国式ペンホルダー)でも変わりません。
冬場だと、このタコがカチカチになって割れ、あかぎれ状態となって痛みや出血を伴うことがあります。
定期的に爪切りで盛り上がった部分をカットし、ひび割れた際はお風呂上がりにクリームを塗ります。
中指の方も、人差し指側の爪の横に同じような半透明のタコができます。
ラケットの裏面を支える力と摩擦でできるものです。
こちらも高く盛り上がってきた場合爪切りで切り取っています。
ある日何気なくテレビを見ていたら、看護師さんがハンドクリームを塗っているシーンがありました。
2本の指をクリームの容器にズボッと差し込んで景気よくすくい、両手をヌルヌルの状態にしていました。
私はカサついた部分にだけ押し当てるように塗っていたので、使用量の違いに唖然としました。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。