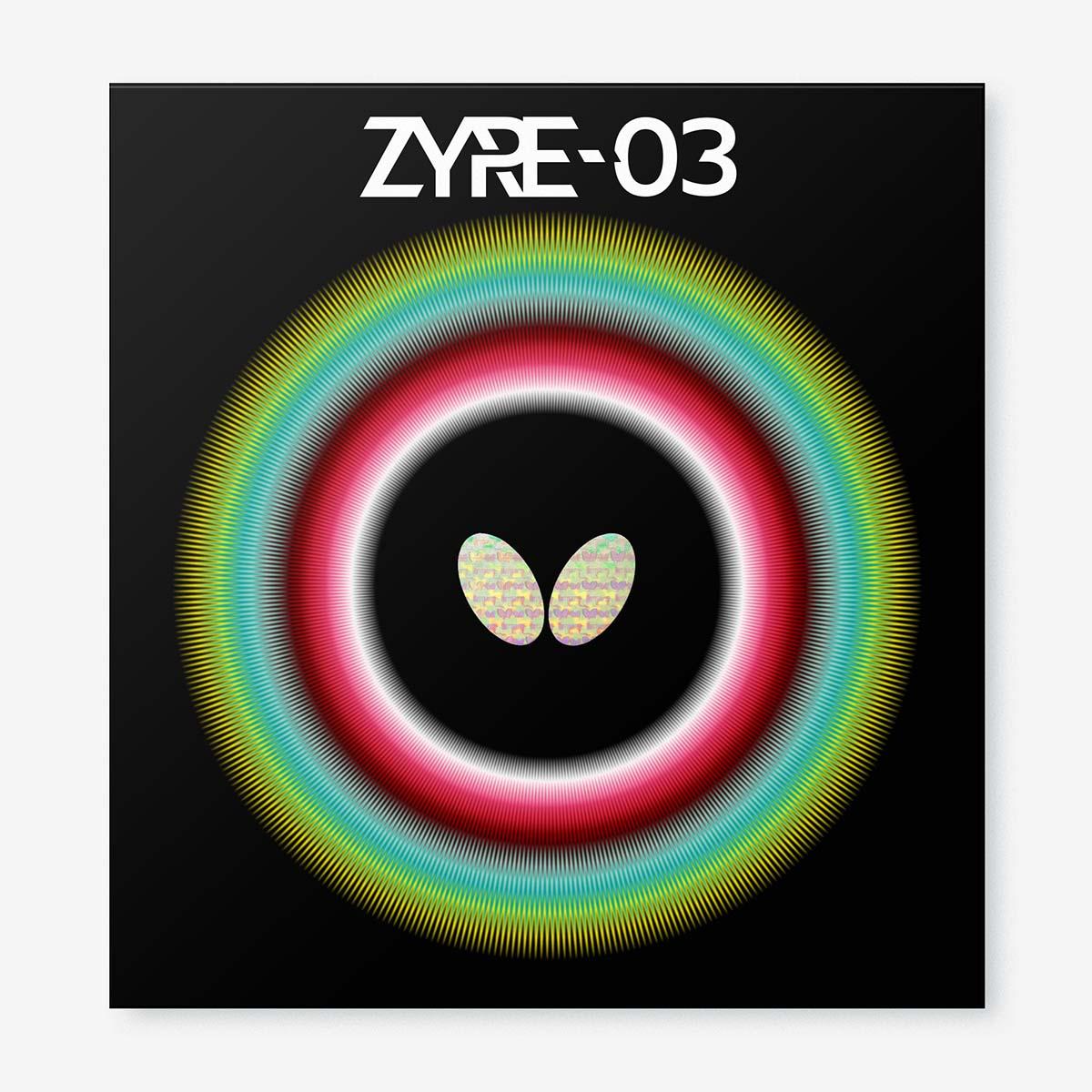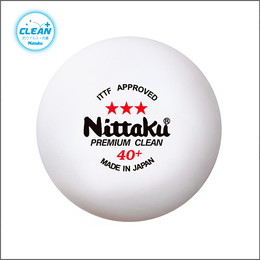今回はずっと前に1度だけお会いしたことのある方について、書きたいと思います。
お名前はわからないので、いつもの通り顔が似ている有名人の名前を使おうと思いました。
ところがその人にあまりよろしくない出来事があり、イニシャルだけにとどめMさんということにしておきます。
──────────────────────
打法の特徴
──────────────────────
Mさんは50代あたりと思われる男性です。
中ペン(中国式ペンホルダー)の両面に裏ソフトラバーを貼り、両ハンドでカウンターを狙う戦法です。
そのエグさと強烈さを感じ取ってもらえるよう、タイトルに往復ビンタという表現を使ってみました。
フォア面には謎めいた中国製の粘着ラバーを貼っていて、厚さはなぜか極薄です。
バック面はニッタクのファクティブというテンションラバーで、こちらの厚さは中でした。
ツッツキはオモテ面でしますが、フォアとバックは完全にそれぞれ個別の面で打つ王皓選手スタイルです。
とはいってもフォアが極薄というだけあって、ぎゅんぎゅんのドライブを打ってくるわけではなくミート打ち主体です。
バックは対ツッツキには強い回転をかけて返すものの、ラリーになるとフォア同様ミート打ちが基本でした。
なので感じとしては往復ビンタ的になります。
お名前はわからないので、いつもの通り顔が似ている有名人の名前を使おうと思いました。
ところがその人にあまりよろしくない出来事があり、イニシャルだけにとどめMさんということにしておきます。
──────────────────────
打法の特徴
──────────────────────
Mさんは50代あたりと思われる男性です。
中ペン(中国式ペンホルダー)の両面に裏ソフトラバーを貼り、両ハンドでカウンターを狙う戦法です。
そのエグさと強烈さを感じ取ってもらえるよう、タイトルに往復ビンタという表現を使ってみました。
フォア面には謎めいた中国製の粘着ラバーを貼っていて、厚さはなぜか極薄です。
バック面はニッタクのファクティブというテンションラバーで、こちらの厚さは中でした。
ツッツキはオモテ面でしますが、フォアとバックは完全にそれぞれ個別の面で打つ王皓選手スタイルです。
とはいってもフォアが極薄というだけあって、ぎゅんぎゅんのドライブを打ってくるわけではなくミート打ち主体です。
バックは対ツッツキには強い回転をかけて返すものの、ラリーになるとフォア同様ミート打ちが基本でした。
なので感じとしては往復ビンタ的になります。
今回は卓球競技者がラケットの選定にあたり、通常は対象から除外しているラバー貼りラケットを取り上げてみたいと思います。
現在国内の用具メーカーでラバー貼りラケットを取り扱っているのは、ニッタク、バタフライ、ヴィクタスの3社です。
それほど話題にはなりませんが、各社ともに新製品をタイムリーに投入しています。
──────────────────────
ニッタク
──────────────────────
ニッタクは「貼り上がりラケット」という呼称にしていて、伊藤美誠選手の名前を冠した製品を揃えています。
Mima S1500、S2000、S2500という3種類のシェークハンドラケットと、Mima P2000というペンホルダーが1種類あります。
末尾の数字は税抜きの希望小売価格を意味していて、数値が大きいほどグリップが凝った作りになっています。
細かい指摘をさせていただきますが、ニッタクのWebサイトを見ると¥1,500+税のような価格表示になっています。
今は総額表示が義務付けられているので、もうこの表示はアウトのはずです。
ニッタクさん、速やかに修正をしていただけたらと思います。
これらの製品には、伊藤選手のシルエットとサインをプリントしたプラスチックボールが2個付いています。
ペンホルダーは角丸形の日本式でコストを抑えるため、コルクの粒を集めて固めた圧搾(あっさく)コルクが使われています。
このMimaシリーズ以外にも、ラージボール用に表ソフトを貼ったラバー貼りラケットもシェークとペン1種類ずつが販売されています。
そちらにはボールは付いていません。
現在国内の用具メーカーでラバー貼りラケットを取り扱っているのは、ニッタク、バタフライ、ヴィクタスの3社です。
それほど話題にはなりませんが、各社ともに新製品をタイムリーに投入しています。
──────────────────────
ニッタク
──────────────────────
ニッタクは「貼り上がりラケット」という呼称にしていて、伊藤美誠選手の名前を冠した製品を揃えています。
Mima S1500、S2000、S2500という3種類のシェークハンドラケットと、Mima P2000というペンホルダーが1種類あります。
末尾の数字は税抜きの希望小売価格を意味していて、数値が大きいほどグリップが凝った作りになっています。
細かい指摘をさせていただきますが、ニッタクのWebサイトを見ると¥1,500+税のような価格表示になっています。
今は総額表示が義務付けられているので、もうこの表示はアウトのはずです。
ニッタクさん、速やかに修正をしていただけたらと思います。
これらの製品には、伊藤選手のシルエットとサインをプリントしたプラスチックボールが2個付いています。
ペンホルダーは角丸形の日本式でコストを抑えるため、コルクの粒を集めて固めた圧搾(あっさく)コルクが使われています。
このMimaシリーズ以外にも、ラージボール用に表ソフトを貼ったラバー貼りラケットもシェークとペン1種類ずつが販売されています。
そちらにはボールは付いていません。
いつもややクセ強の文章を書いていますが、それはメジャーな媒体とあまり重ならないようにしようかなという意識が働いた結果でもあります。
一応目指している方向としては、ちまたの愛好家で多数派を占める初級レベル向けの内容を意識しています。
今回はそれらの方のお悩みの一つであるレシーブについてお話しさせていただきます。
──────────────────────
表は裏よりレシーブしやすいか
──────────────────────
レシーブが下手なので、裏ソフトではなく回転の影響を受けにくい表ソフトに変えてみようかと考える人がいます。
裏と表ではスピン性能に差があるのは確かです。
でも過去にも触れたことがありますが、個人的には裏と表でレシーブの返しやすさにそれほど大きな差はないと考えています。
裏ソフトと表ソフトでは、ボールがラバーに当たってから離れるまでの物理的な形状変化が異なるため、単純比較はあまり適切ではないと思っているのです。
裏ソフトの場合、平らなシートにボールがペシッと接触した状態で凹みます。
下の層の粒が倒れスポンジも凹みます。
下回転であれ横回転であれ、猛烈に回転がかかったサーブを裏ソフトで面を合わせて返そうとすると、打球した瞬間的にシートがギュッと引っ張られるような感触があります。
表ソフトは粒の頭にボールが当たり、粒とスポンジが凹みます。
めちゃ切れのサーブは回転で引っ張られる感じがあることはあるのですが、裏ソフトほどではありません。
そのため滑らせて返すようなことができることもあります。
裏と表のレシーブを単純比較するのは疑問に思いつつ、それでもショートサーブに限って返しやすさはどうかと問われれば、表のほうが少し楽なのは認めたいと思います。
一応目指している方向としては、ちまたの愛好家で多数派を占める初級レベル向けの内容を意識しています。
今回はそれらの方のお悩みの一つであるレシーブについてお話しさせていただきます。
──────────────────────
表は裏よりレシーブしやすいか
──────────────────────
レシーブが下手なので、裏ソフトではなく回転の影響を受けにくい表ソフトに変えてみようかと考える人がいます。
裏と表ではスピン性能に差があるのは確かです。
でも過去にも触れたことがありますが、個人的には裏と表でレシーブの返しやすさにそれほど大きな差はないと考えています。
裏ソフトと表ソフトでは、ボールがラバーに当たってから離れるまでの物理的な形状変化が異なるため、単純比較はあまり適切ではないと思っているのです。
裏ソフトの場合、平らなシートにボールがペシッと接触した状態で凹みます。
下の層の粒が倒れスポンジも凹みます。
下回転であれ横回転であれ、猛烈に回転がかかったサーブを裏ソフトで面を合わせて返そうとすると、打球した瞬間的にシートがギュッと引っ張られるような感触があります。
表ソフトは粒の頭にボールが当たり、粒とスポンジが凹みます。
めちゃ切れのサーブは回転で引っ張られる感じがあることはあるのですが、裏ソフトほどではありません。
そのため滑らせて返すようなことができることもあります。
裏と表のレシーブを単純比較するのは疑問に思いつつ、それでもショートサーブに限って返しやすさはどうかと問われれば、表のほうが少し楽なのは認めたいと思います。
オリンピックの余韻もそろそろ収まりつつあるかもしれませんが、卓球界では来月にビッグイベントが控えています。
そうです。世界選手権です。
──────────────────────
混乱を極めた世界選手権
──────────────────────
例年であれば、オリンピックが開催される年の世界選手権は団体戦が行われます。
そして実施時期は、夏のオリンピック期間より数ヶ月前となる2~3月頃となっていました。
その慣例に従い、2020年3月に韓国の釜山で団体戦が行われる予定でした。
ところが新型コロナウイルスの世界的な蔓延により、オリンピックだけでなく世界選手権も実施時期を見直さざるを得ませんでした。
2020年3月→6月→9月→2021年2月と3度も見直しが行われ、結局中止となりました。
仕切り直しとなった2021年の世界選手権が、11月23~29日にアメリカのヒューストンで行われます。
試合は団体戦なのか個人戦なのか、議論があったことは想像に難くありません。
どちらであってもそれなりの理由は考えられます。
私の勝手な推測ですが、2024年のパリオリンピックを見据え、そこから逆に考えて今回は個人戦にしたのではないでしょうか。
コロナで一時的に乱れたものの、オリンピックと世界選手権の2つの流れをこれまで通りに戻したかったという考えです。
整理すると、
2020年の団体戦は中止になったので無し。
2021年は個人戦だったので、開催時期はズレたものの予定通り個人戦を行う。
2022年は当初計画通り春に中国の成都で団体戦を行う。
さて今回の開催地ヒューストンは南部のメキシコ湾に面した都市で、日本との時差は14時間あります。
大雑把に言えば日本と昼夜が真逆で、あちらの10時-19時は日本では0時-9時となります。
従って試合のライブ映像が見られたとしても、それは睡魔との戦いになります。
それから雑学的なこととなりますが、ヒューストンのスペルは「Houston」でちょっと注意が必要ですね。
そうです。世界選手権です。
──────────────────────
混乱を極めた世界選手権
──────────────────────
例年であれば、オリンピックが開催される年の世界選手権は団体戦が行われます。
そして実施時期は、夏のオリンピック期間より数ヶ月前となる2~3月頃となっていました。
その慣例に従い、2020年3月に韓国の釜山で団体戦が行われる予定でした。
ところが新型コロナウイルスの世界的な蔓延により、オリンピックだけでなく世界選手権も実施時期を見直さざるを得ませんでした。
2020年3月→6月→9月→2021年2月と3度も見直しが行われ、結局中止となりました。
仕切り直しとなった2021年の世界選手権が、11月23~29日にアメリカのヒューストンで行われます。
試合は団体戦なのか個人戦なのか、議論があったことは想像に難くありません。
どちらであってもそれなりの理由は考えられます。
私の勝手な推測ですが、2024年のパリオリンピックを見据え、そこから逆に考えて今回は個人戦にしたのではないでしょうか。
コロナで一時的に乱れたものの、オリンピックと世界選手権の2つの流れをこれまで通りに戻したかったという考えです。
整理すると、
2020年の団体戦は中止になったので無し。
2021年は個人戦だったので、開催時期はズレたものの予定通り個人戦を行う。
2022年は当初計画通り春に中国の成都で団体戦を行う。
さて今回の開催地ヒューストンは南部のメキシコ湾に面した都市で、日本との時差は14時間あります。
大雑把に言えば日本と昼夜が真逆で、あちらの10時-19時は日本では0時-9時となります。
従って試合のライブ映像が見られたとしても、それは睡魔との戦いになります。
それから雑学的なこととなりますが、ヒューストンのスペルは「Houston」でちょっと注意が必要ですね。
粘着ラバーと一般的な裏ソフトラバーを比較するため、試し打ちをしてみました。
今回はその際の感想をお話いたします。
──────────────────────
「粘着」の解釈は人によって異なる
──────────────────────
初級者の方にも分かりやすいよう、基本的なところからご説明いたします。
粘着ラバーとは名前の通り、平らなシートの表面がしっとりとして引っかかりが強い裏ソフトラバーを指します。
特にちまたで、あるいは用具マニアの間で「中国粘着」と呼ばれている製品は、粘着力だけでなくシートの形状にも特徴があります。
スポンジに接する粒が低く、太く、密集しています。
そしてシートの平らな部分は分厚くなっています。
よって一般的な裏ソフトを見慣れた方がこの手のラバーの断面を見ると、粒の存在がわからず、スポンジに平らなゴムシートだけが貼り付いたように見えてしまうかもしれません。
中国製の粘着ラバーの中には、粒が高く細く間隔が広いタイプも少数ながら存在します。
今回取り上げる粘着ラバーは、多数派である典型的な肉厚の中国粘着ラバーということにさせていただきます。
またそのへんの卓球愛好家レベルの実力でしかない私が使ってみた感想である、ということもご理解いただければと思います。
今回はその際の感想をお話いたします。
──────────────────────
「粘着」の解釈は人によって異なる
──────────────────────
初級者の方にも分かりやすいよう、基本的なところからご説明いたします。
粘着ラバーとは名前の通り、平らなシートの表面がしっとりとして引っかかりが強い裏ソフトラバーを指します。
特にちまたで、あるいは用具マニアの間で「中国粘着」と呼ばれている製品は、粘着力だけでなくシートの形状にも特徴があります。
スポンジに接する粒が低く、太く、密集しています。
そしてシートの平らな部分は分厚くなっています。
よって一般的な裏ソフトを見慣れた方がこの手のラバーの断面を見ると、粒の存在がわからず、スポンジに平らなゴムシートだけが貼り付いたように見えてしまうかもしれません。
中国製の粘着ラバーの中には、粒が高く細く間隔が広いタイプも少数ながら存在します。
今回取り上げる粘着ラバーは、多数派である典型的な肉厚の中国粘着ラバーということにさせていただきます。
またそのへんの卓球愛好家レベルの実力でしかない私が使ってみた感想である、ということもご理解いただければと思います。
2021 .10.02
今回は巷の卓球愛好家が年齢を重ねていくにつれ、どのような変化が生じるのかについて考えてみたいと思います。
──────────────────────
肩の痛み
──────────────────────
某卓球場でお会いした男性の例をご紹介いたします。
お名前はわからないので、ぱっと見で似ているお笑い芸人のお名前を拝借し、松本さんということにしておきます。
松本さんはご自身の年代では多数派である、片面だけに裏ソフトラバーを貼ったペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)です。
一緒に練習をさせてもらっている過程で感じたのは、フォアドライブを打つスイングがどことなくぎこちないことでした。
そして時々右肩だけをぐりぐり回したり、左手で右腕にマッサージを行っていました。
フォームにクセのある人はたくさんいらっしゃいます。
そして私は指導員でもないので、別段指摘するつもりもありませんでした。
休憩中、松本さんは自分から右肩のことについて語ってくれました。
肩が痛いため、以前のように自在にラケットを振ることができないそうです。
私も新型コロナのワクチンを打ちその際、腕に筋肉痛がありました。
その話を持ち出したのですが、松本さんはあれとは別物の痛みだと訴えます。
首を寝違えたり足を捻挫したときのような、筋がよれた感じがするのです。
──────────────────────
肩の痛み
──────────────────────
某卓球場でお会いした男性の例をご紹介いたします。
お名前はわからないので、ぱっと見で似ているお笑い芸人のお名前を拝借し、松本さんということにしておきます。
松本さんはご自身の年代では多数派である、片面だけに裏ソフトラバーを貼ったペンドラ(ペンホルダーのドライブマン)です。
一緒に練習をさせてもらっている過程で感じたのは、フォアドライブを打つスイングがどことなくぎこちないことでした。
そして時々右肩だけをぐりぐり回したり、左手で右腕にマッサージを行っていました。
フォームにクセのある人はたくさんいらっしゃいます。
そして私は指導員でもないので、別段指摘するつもりもありませんでした。
休憩中、松本さんは自分から右肩のことについて語ってくれました。
肩が痛いため、以前のように自在にラケットを振ることができないそうです。
私も新型コロナのワクチンを打ちその際、腕に筋肉痛がありました。
その話を持ち出したのですが、松本さんはあれとは別物の痛みだと訴えます。
首を寝違えたり足を捻挫したときのような、筋がよれた感じがするのです。
さていよいよ来月からラバーの新色が認められることになりました。
今回はそれについて触れてみたいと思います。
──────────────────────
適用条件と各社の状況
──────────────────────
追加される新色は、ピンク、青、緑、紫の4色です。
従来の黒と赤を合わせると全部で6色になりました。
ただし一方は黒でなければならないというルールもあります。
従って、黒+ピンクの組み合わせはOKですが、赤+青などはNGとなります。
私のような片面だけにラバーを貼ったオールドスタイルの選手は、裏面が黒く塗ってあれば青や緑のラバーを貼ることができるそうです。
逆に考えると黒いラバーを貼れば、裏面を紫に塗ることも可能なのでしょう。
このルール改正は10月1日から適用されます。
それでは各用具メーカー側の品揃えはどうなっているのでしょうか。
先日ざっと調べた範囲では、ヴィクタス、アンドロ、ティバーの3社が新色の製品を投入する発表をしています。
それらを順を追ってご紹介いたします。
今回はそれについて触れてみたいと思います。
──────────────────────
適用条件と各社の状況
──────────────────────
追加される新色は、ピンク、青、緑、紫の4色です。
従来の黒と赤を合わせると全部で6色になりました。
ただし一方は黒でなければならないというルールもあります。
従って、黒+ピンクの組み合わせはOKですが、赤+青などはNGとなります。
私のような片面だけにラバーを貼ったオールドスタイルの選手は、裏面が黒く塗ってあれば青や緑のラバーを貼ることができるそうです。
逆に考えると黒いラバーを貼れば、裏面を紫に塗ることも可能なのでしょう。
このルール改正は10月1日から適用されます。
それでは各用具メーカー側の品揃えはどうなっているのでしょうか。
先日ざっと調べた範囲では、ヴィクタス、アンドロ、ティバーの3社が新色の製品を投入する発表をしています。
それらを順を追ってご紹介いたします。
少し前に某練習場で試合をしました。
それぞれの参加者に指導員からアドバイスがありました。
私がいただいた内容で突き刺さったのが「決めにいかず、つなぐこと」でした。
──────────────────────
強打してしまう心理
──────────────────────
振り返ってみると、果敢に仕掛けていって打ちミスで失点している場面が多々ありました。
かなり強引だったなと思った展開や、一か八かのスマッシュを叩き込んだ時もありました。
自分でもそう思うことがあるので、他の方からみるとより荒っぽいプレーに見えたのでしょう。
そして本人もこれでいいとは思っておらず、忠告をしっかりと受け止めるべきとの考えに至りました。
さて、なぜリスキーな試合運びになってしまっているのでしょう。
まずこの行動心理を考えてみます。
思い当たるのは、週に一度の卓球であり、それは運動不足の解消と同時にストレス発散の場としている点です。
ボールをバシバシ叩く動作は心地よい刺激です。
この快感を欲しているため、強打を叩き込もうとしてしまっていそうです。
そしてできればドライブで打ち勝つ、あるいはスマッシュで決めるのが理想との思いがあります。
正義のヒーローが番組終了3分前に、いつもの必殺技で仕留めるパターンというと格好良すぎるでしょうか。
そんな派手さは求めず、相手を両サイドに大きく振って、がら空きのコートにペシッと入れてジ・エンドという展開もクールでカッコいいと理解すべきなのです。
それぞれの参加者に指導員からアドバイスがありました。
私がいただいた内容で突き刺さったのが「決めにいかず、つなぐこと」でした。
──────────────────────
強打してしまう心理
──────────────────────
振り返ってみると、果敢に仕掛けていって打ちミスで失点している場面が多々ありました。
かなり強引だったなと思った展開や、一か八かのスマッシュを叩き込んだ時もありました。
自分でもそう思うことがあるので、他の方からみるとより荒っぽいプレーに見えたのでしょう。
そして本人もこれでいいとは思っておらず、忠告をしっかりと受け止めるべきとの考えに至りました。
さて、なぜリスキーな試合運びになってしまっているのでしょう。
まずこの行動心理を考えてみます。
思い当たるのは、週に一度の卓球であり、それは運動不足の解消と同時にストレス発散の場としている点です。
ボールをバシバシ叩く動作は心地よい刺激です。
この快感を欲しているため、強打を叩き込もうとしてしまっていそうです。
そしてできればドライブで打ち勝つ、あるいはスマッシュで決めるのが理想との思いがあります。
正義のヒーローが番組終了3分前に、いつもの必殺技で仕留めるパターンというと格好良すぎるでしょうか。
そんな派手さは求めず、相手を両サイドに大きく振って、がら空きのコートにペシッと入れてジ・エンドという展開もクールでカッコいいと理解すべきなのです。
2021 .08.21
今回も前回に引き続き、東京オリンピックに関することをお話ししたいと思います。
──────────────────────
用具や選手の所作
──────────────────────
多くの選手をざざっと見ましたが、それまでは中国選手だけだった粘着ラバーが、他の国の選手にも広がっていることがわかりました。
しかも私が実際試してみて駄目だった、肉厚で短い粒が密集している中国製粘着ラバーです。
ファアにスポンジが青の黒ラバーというのはその典型的なスタイルで、これからも使用者は増えていくのでしょうか。
ブラジルのカルデラノ選手は、相手がサーブを出す直前にものすごく低い姿勢を取り、そこから上体を上げてレシーブの動作に入ります。
どれだけ低いかといえば、目が台の高さの所になる位置まで下げるのです。
これは私には真似のできない動作です。
私は脚はガバッと開いて構える一方、上体はすっと立てたまま台全体を俯瞰する感じでレシーブに入ります。
レシーブ直前で視点が変化するのは避けたいからです。
──────────────────────
用具や選手の所作
──────────────────────
多くの選手をざざっと見ましたが、それまでは中国選手だけだった粘着ラバーが、他の国の選手にも広がっていることがわかりました。
しかも私が実際試してみて駄目だった、肉厚で短い粒が密集している中国製粘着ラバーです。
ファアにスポンジが青の黒ラバーというのはその典型的なスタイルで、これからも使用者は増えていくのでしょうか。
ブラジルのカルデラノ選手は、相手がサーブを出す直前にものすごく低い姿勢を取り、そこから上体を上げてレシーブの動作に入ります。
どれだけ低いかといえば、目が台の高さの所になる位置まで下げるのです。
これは私には真似のできない動作です。
私は脚はガバッと開いて構える一方、上体はすっと立てたまま台全体を俯瞰する感じでレシーブに入ります。
レシーブ直前で視点が変化するのは避けたいからです。
2021 .08.07
連日猛暑が続く中、東京オリンピックの会場でも熱い戦いが繰り広げられています。
さて卓球競技においても、混合ダブルスの金メダルを始め、日本は複数のメダルを獲得することができました。
──────────────────────
理系的発想のメダル予想
──────────────────────
最初は混合ダブルスから始まり、これは下馬評通りになる確率がやや低めの種目でした。
そういう中でも卓球コラムニストの伊藤条太氏は、個性的な見解を出していました。
中国の許シン劉詩文ペアと、日本の水谷伊藤ペアの対戦予想をユニークな視点で語っていたのです。
直近の両ペアの対戦における獲得ゲーム数から、日本ペアが4ゲーム先取する確率を21%と算出したのです。
それは過去の3試合という限定的な試合数より導いたものです。
でも統計的に有意な母数となるほど対戦しまくるということは不可能です。
従ってその範囲から想像をたくましくした意見で構わないと考えています。
21%なら可能性は低いものの、望みは持てる値です。
こういう分析が新鮮に思えたのは、卓球を語る人で同じような話をしていた人が皆無だったからです。
さて卓球競技においても、混合ダブルスの金メダルを始め、日本は複数のメダルを獲得することができました。
──────────────────────
理系的発想のメダル予想
──────────────────────
最初は混合ダブルスから始まり、これは下馬評通りになる確率がやや低めの種目でした。
そういう中でも卓球コラムニストの伊藤条太氏は、個性的な見解を出していました。
中国の許シン劉詩文ペアと、日本の水谷伊藤ペアの対戦予想をユニークな視点で語っていたのです。
直近の両ペアの対戦における獲得ゲーム数から、日本ペアが4ゲーム先取する確率を21%と算出したのです。
それは過去の3試合という限定的な試合数より導いたものです。
でも統計的に有意な母数となるほど対戦しまくるということは不可能です。
従ってその範囲から想像をたくましくした意見で構わないと考えています。
21%なら可能性は低いものの、望みは持てる値です。
こういう分析が新鮮に思えたのは、卓球を語る人で同じような話をしていた人が皆無だったからです。
2021 .07.24
卓球をやっている中で、ちょっぴり「カッコ悪い」と思うこと、あるいはそのように見なされていそうなことがあります。
今回はそれについて考えてみます。
──────────────────────
ラケットに手を添えて反転させる
──────────────────────
シェークでラケットを反転させるのは簡単で、初級者でもラケットを立てた状態にして片手でくるくる回すことができます。
一方ペンの場合は練習をして慣れる必要があります。
反転式と呼ばれる両側に指を引っ掛ける突起がついたラケットか、中ペン(中国式ペンホルダー)の2つが反転できるペンホルダーラケットです。
どちらであってもラケットの形状と握り方の特性から、シェークのように片手で反転させるのは難しくなります。
世間にはなんなく反転させているペン使いの人は沢山います。
でもみなさん結構な時間をかけて、片手でなめらかに反転できるよう練習を重ねた結果なのです。
そのためその辺の卓球場だと、もう一方の手を添えて反転しているペン使いの人が結構いらっしゃいます。
別にそれで構わないと考えている人は一定数います。
一方でそう思っていない人も多数存在します。
後者の人は程度の差はあれ、いつか自分も片手で自在に反転できればと願っています。
ところが現実は、反転の練習にあまり時間を割くことができておらず、やむを得ず片手を添えて反転させる状態に甘んじています。
恐らく10回中9回は片手だけで反転できるレベルの人は、そこそこいらっしゃるはずです。
でも裏を返せば10回に1回の確率で回し損ないをしてしまうのです。
その成功率で試合に臨み反転を試みるとどうなるか、、、かなり悔いの残ることになりそうです。
従って情けないと思いながらも、片手を添えてラケットを反転させているのです。
今回はそれについて考えてみます。
──────────────────────
ラケットに手を添えて反転させる
──────────────────────
シェークでラケットを反転させるのは簡単で、初級者でもラケットを立てた状態にして片手でくるくる回すことができます。
一方ペンの場合は練習をして慣れる必要があります。
反転式と呼ばれる両側に指を引っ掛ける突起がついたラケットか、中ペン(中国式ペンホルダー)の2つが反転できるペンホルダーラケットです。
どちらであってもラケットの形状と握り方の特性から、シェークのように片手で反転させるのは難しくなります。
世間にはなんなく反転させているペン使いの人は沢山います。
でもみなさん結構な時間をかけて、片手でなめらかに反転できるよう練習を重ねた結果なのです。
そのためその辺の卓球場だと、もう一方の手を添えて反転しているペン使いの人が結構いらっしゃいます。
別にそれで構わないと考えている人は一定数います。
一方でそう思っていない人も多数存在します。
後者の人は程度の差はあれ、いつか自分も片手で自在に反転できればと願っています。
ところが現実は、反転の練習にあまり時間を割くことができておらず、やむを得ず片手を添えて反転させる状態に甘んじています。
恐らく10回中9回は片手だけで反転できるレベルの人は、そこそこいらっしゃるはずです。
でも裏を返せば10回に1回の確率で回し損ないをしてしまうのです。
その成功率で試合に臨み反転を試みるとどうなるか、、、かなり悔いの残ることになりそうです。
従って情けないと思いながらも、片手を添えてラケットを反転させているのです。
2021 .07.10
東京都に4回めの緊急事態宣言が発出され、オリンピックは一部会場を除いて無観客での開催が決まりました。
これについて皆さんはそれぞれのお考えをお持ちになったことだと思います。
それでも世の中は止まることなく動いており、決定されたことに従って進んでいくしかありません。
──────────────────────
広報活動のもどかしさ
──────────────────────
日本選手団の主将は陸上の山縣選手、そして副手主将は我らが卓球の石川選手に決まりました。
JOC(日本オリンピック委員会)のスポンサーであるアシックスは、同社の契約選手である石川選手の巨大モニュメント「ビッグ佳純」を制作し、PRの目玉にする予定でした。
とてもユニークな試みで、かなりのインパクトのある宣伝になると思いました。
しかしこれを多くの人の目に触れる場所に展示するのは、今避けなければならない密集を回避する方針に反します。
そのためアシックス本社前という露出やや控えめの場所に置かれ、せっかくのアイデアが十分に活かされない形となってしまいました。
これについて皆さんはそれぞれのお考えをお持ちになったことだと思います。
それでも世の中は止まることなく動いており、決定されたことに従って進んでいくしかありません。
──────────────────────
広報活動のもどかしさ
──────────────────────
日本選手団の主将は陸上の山縣選手、そして副手主将は我らが卓球の石川選手に決まりました。
JOC(日本オリンピック委員会)のスポンサーであるアシックスは、同社の契約選手である石川選手の巨大モニュメント「ビッグ佳純」を制作し、PRの目玉にする予定でした。
とてもユニークな試みで、かなりのインパクトのある宣伝になると思いました。
しかしこれを多くの人の目に触れる場所に展示するのは、今避けなければならない密集を回避する方針に反します。
そのためアシックス本社前という露出やや控えめの場所に置かれ、せっかくのアイデアが十分に活かされない形となってしまいました。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。