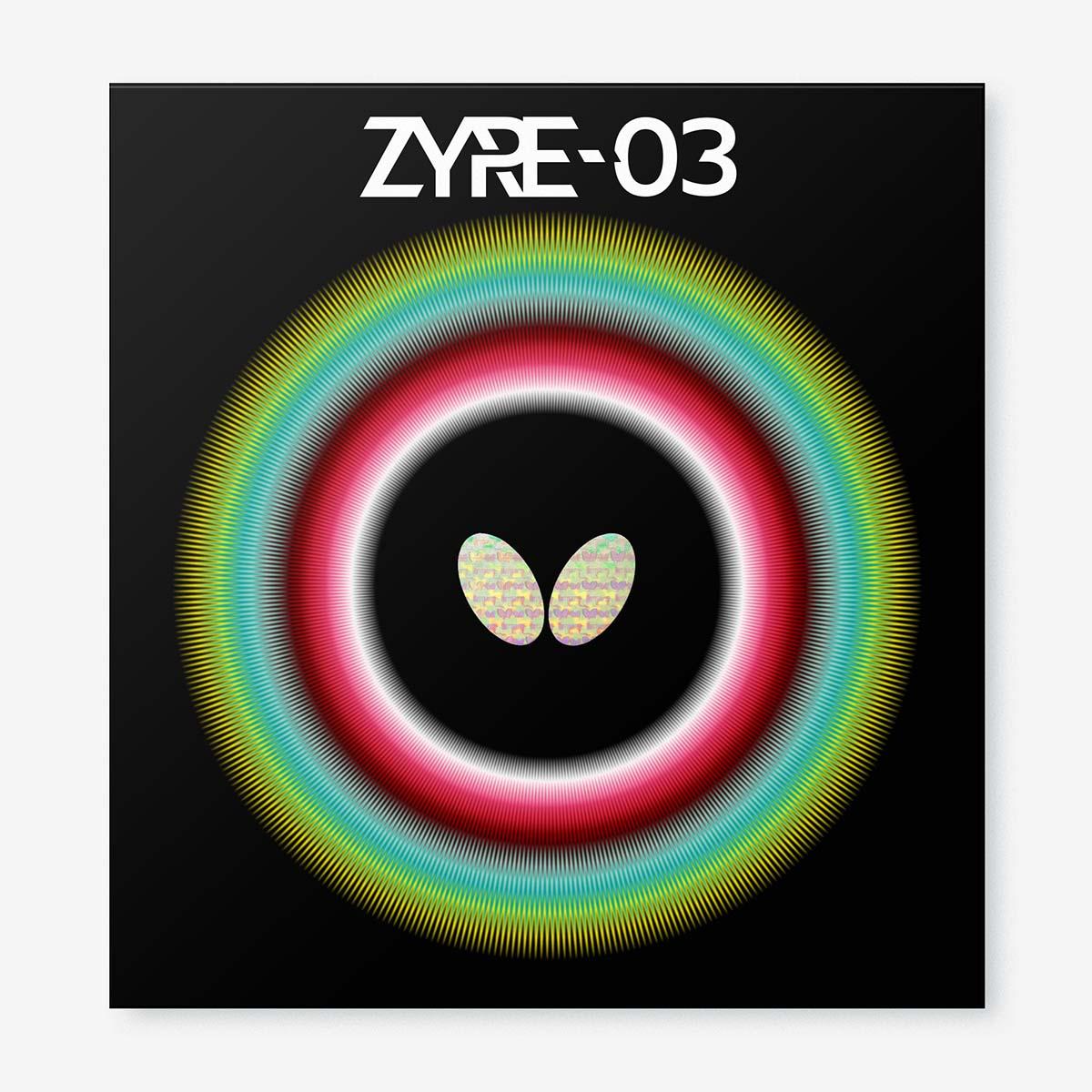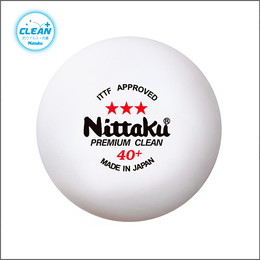ある卓球場におじゃますると、その日はリーグ戦をすることになっていました。
3つのリーグに分かれて試合が始まりました。
それほど厳格に試合運営はなされておらず、遅れてきた人は適宜どれかのリーグに入って試合をしていました。
私のリーグにも遅れてきたMさんが追加で入ることになりました。
当然ながらMさんは来たばかりで消化した試合数が0のため、優先的に次々と対戦をする運びとなりました。
Mさんは卓球場に来る途中、コンビニに寄ってパンとおにぎりを買っていました。
到着してからお腹を満たした後、卓球をする予定でした。
しかし急かされるようにコートに案内され、準備運動も全くしないまま最初の試合になりました。
Mさんは20代の男性なので故障する危険性は低そうではあります。
それでも到着するやいなや試合をするのは望ましくないことですね。
──────────────────────
まさかの凡ミス連発
──────────────────────
最初の対戦相手は私でした。
Mさんは伸びのあるドライブを両ハンドからブンブン振ってきます。
最初のゲームの4-4ぐらいの時点で、この人には勝てそうにないことが分かりました。
ところが点差は開かず、私が11-9で第1ゲームをものにしました
Mさんは打ちミスが多く、来たばかりでまだ調子が出ていないようでした。
第2ゲームはあっさり取られるだろうと思っていました。
Mさんは攻撃をしかけるものの、それが決まらず「あれっ」「うーん」と迷走状態に入っていました。
中盤から修正モードに切り替えたようで、7割ぐらいの力でとにかくボールをつないで入れる戦法になりました。
そうなると両者は五分五分となり、序盤のリード分の点差だけで2ゲーム目も私が取りました。
Mさんは、対戦相手の実力が自分より格下であることは分かっているはずです。
ウォーミングアップなしで空腹のまま、いきなり試合をさせられ、これじゃ仕方ないという思いもあるでしょう。
でもこんな奴に0-2で王手をかけられている現実があり、それをなんとか打開しようと考えているようでした。
3ゲーム目、Mさんは最初から確実に返球するプレーを基本とし、要所で積極的に決めにいく戦術のようでした。
しかし攻撃がなかなか決まらず、独り言のボヤキを連発します。
16-15までもつれましたが、最後はネットに当たって浮いたボールを私が叩き込みストレートで勝ってしまいました。
3つのリーグに分かれて試合が始まりました。
それほど厳格に試合運営はなされておらず、遅れてきた人は適宜どれかのリーグに入って試合をしていました。
私のリーグにも遅れてきたMさんが追加で入ることになりました。
当然ながらMさんは来たばかりで消化した試合数が0のため、優先的に次々と対戦をする運びとなりました。
Mさんは卓球場に来る途中、コンビニに寄ってパンとおにぎりを買っていました。
到着してからお腹を満たした後、卓球をする予定でした。
しかし急かされるようにコートに案内され、準備運動も全くしないまま最初の試合になりました。
Mさんは20代の男性なので故障する危険性は低そうではあります。
それでも到着するやいなや試合をするのは望ましくないことですね。
──────────────────────
まさかの凡ミス連発
──────────────────────
最初の対戦相手は私でした。
Mさんは伸びのあるドライブを両ハンドからブンブン振ってきます。
最初のゲームの4-4ぐらいの時点で、この人には勝てそうにないことが分かりました。
ところが点差は開かず、私が11-9で第1ゲームをものにしました
Mさんは打ちミスが多く、来たばかりでまだ調子が出ていないようでした。
第2ゲームはあっさり取られるだろうと思っていました。
Mさんは攻撃をしかけるものの、それが決まらず「あれっ」「うーん」と迷走状態に入っていました。
中盤から修正モードに切り替えたようで、7割ぐらいの力でとにかくボールをつないで入れる戦法になりました。
そうなると両者は五分五分となり、序盤のリード分の点差だけで2ゲーム目も私が取りました。
Mさんは、対戦相手の実力が自分より格下であることは分かっているはずです。
ウォーミングアップなしで空腹のまま、いきなり試合をさせられ、これじゃ仕方ないという思いもあるでしょう。
でもこんな奴に0-2で王手をかけられている現実があり、それをなんとか打開しようと考えているようでした。
3ゲーム目、Mさんは最初から確実に返球するプレーを基本とし、要所で積極的に決めにいく戦術のようでした。
しかし攻撃がなかなか決まらず、独り言のボヤキを連発します。
16-15までもつれましたが、最後はネットに当たって浮いたボールを私が叩き込みストレートで勝ってしまいました。
試合で得点に直結しやすく、多球練習との組み合わせで打つ機会が多いのがスマッシュです。
それぞれの選手の力や戦型に応じて、指導員がコースや間隔を調整しながら球出しをしてくれる所も多いと思います。
ある人にはフォア側だけ、別の人には全面に、そしてボールの長短や回転をかけたりとバリエーションを持たせ、実戦向きの練習と言えます。
──────────────────────
タイプ別スマッシュ練習
──────────────────────
初心者の方なら当てるだけになりますが、慣れてくるとフォア側は上体のひねりを入れて力強いボールを叩き込めるようになります。
一方のバック側は、腹筋と背筋を使ってボールをひっぱたけるようになります。
フォアとバック両ハンドから攻撃を行う選手なら台の中央に構えそれぞれの強打を、ペンで片面だけの選手ならバック側に構え、どこに来てもフォアハンドで動きまわるというのをよく見かけます。
練習の半分はフットワークも兼ねていて、特にペン片面でオールフォアの選手には重要です。
両ハンドを振れる選手にもこの動きは必要で、適宜フォアだけの練習を取り入れても良いと思います。
シェークでバックが粒高の人はフォアに1球送ってもらいスマッシュを、続いてバックに1球送ってもらい、ラケットを反転させ裏ソフトでバックハンドスマッシュというパターンがあります。
スマッシュを打ってバック側に返球されてしまっても、連続攻撃で畳み掛ける練習です。
ラケットを反転させるのはサーブを出す時だけにしている人もいて、そういう方はバック側も回りこんでフォアで連続スマッシュか、難しいですがバック面の粒高でスマッシュというのもあります。
粒高スマッシュはインパクト時にボールがぐらつくので精度に難がある反面、入れば相手は返しづらいというちょっぴりギャンブルな打法です。
それぞれの選手の力や戦型に応じて、指導員がコースや間隔を調整しながら球出しをしてくれる所も多いと思います。
ある人にはフォア側だけ、別の人には全面に、そしてボールの長短や回転をかけたりとバリエーションを持たせ、実戦向きの練習と言えます。
──────────────────────
タイプ別スマッシュ練習
──────────────────────
初心者の方なら当てるだけになりますが、慣れてくるとフォア側は上体のひねりを入れて力強いボールを叩き込めるようになります。
一方のバック側は、腹筋と背筋を使ってボールをひっぱたけるようになります。
フォアとバック両ハンドから攻撃を行う選手なら台の中央に構えそれぞれの強打を、ペンで片面だけの選手ならバック側に構え、どこに来てもフォアハンドで動きまわるというのをよく見かけます。
練習の半分はフットワークも兼ねていて、特にペン片面でオールフォアの選手には重要です。
両ハンドを振れる選手にもこの動きは必要で、適宜フォアだけの練習を取り入れても良いと思います。
シェークでバックが粒高の人はフォアに1球送ってもらいスマッシュを、続いてバックに1球送ってもらい、ラケットを反転させ裏ソフトでバックハンドスマッシュというパターンがあります。
スマッシュを打ってバック側に返球されてしまっても、連続攻撃で畳み掛ける練習です。
ラケットを反転させるのはサーブを出す時だけにしている人もいて、そういう方はバック側も回りこんでフォアで連続スマッシュか、難しいですがバック面の粒高でスマッシュというのもあります。
粒高スマッシュはインパクト時にボールがぐらつくので精度に難がある反面、入れば相手は返しづらいというちょっぴりギャンブルな打法です。
今、私の手元に3本のラケットがあります。
いずれも不要になった人からいただいたもので、今回はそれらについて書いてみたいと思います。
──────────────────────
100均で売られていたラケット
──────────────────────
3本の中で文句無しに最もしょぼいラケットです。
安物と言われるラバー貼りラケットより、さらに数段落ちるクオリティです。
ラケットの縁に相当する板の断面は、所々ガタガタになっています。
大本の板の作りが雑なのか、加工の際に使ったのこぎりの精度がイマイチなのか、あるいはその両方かもしれません。
グリップエンドの断面はどう見ても左右非対称のいびつな楕円形です。
あえて好意的に解釈すれば、右利きの人がフォアハンドドライブを打ちやすいよう、面をかぶせ気味に握れる作りになっています。
中国式ペンホルダー(中ペン)で、片面だけに表ソフトラバーが貼られています。
薄くて弾力性の低いスポンジに、同じく弾力性の乏しいゴムシートを貼り合わせたラバーです。
粒高ラバーと同程度に細く、それでいてノーマルな表ソフトの半分以下の高さの粒が「不規則」に並んでいます。
一応横目なのですが、ある列とある列は狭く、別の部分は間隔が広めになっています。
当然ITTFのマークはなく、ラバーのロゴもありません。
ラケット全体にニスが塗られていて、ラバーを貼る接着剤がはみ出した箇所がいたる所にあります。
とても軽く、片面にラバーが貼られた状態で88gです。
玉突きをしてみると、ラバーがあたかも衝撃吸収材のようなぱふぱふ感で、シートはカチカチ、そして回転はほとんど掛かりません。
あえて良い部分はないか探してみると、ラバーのフチはなめらかな処理で美しいカーブを描いていました。
恐らくラバーを貼った後で強引にヤスリがけをして、ならしたためだと思われます。
いずれも不要になった人からいただいたもので、今回はそれらについて書いてみたいと思います。
──────────────────────
100均で売られていたラケット
──────────────────────
3本の中で文句無しに最もしょぼいラケットです。
安物と言われるラバー貼りラケットより、さらに数段落ちるクオリティです。
ラケットの縁に相当する板の断面は、所々ガタガタになっています。
大本の板の作りが雑なのか、加工の際に使ったのこぎりの精度がイマイチなのか、あるいはその両方かもしれません。
グリップエンドの断面はどう見ても左右非対称のいびつな楕円形です。
あえて好意的に解釈すれば、右利きの人がフォアハンドドライブを打ちやすいよう、面をかぶせ気味に握れる作りになっています。
中国式ペンホルダー(中ペン)で、片面だけに表ソフトラバーが貼られています。
薄くて弾力性の低いスポンジに、同じく弾力性の乏しいゴムシートを貼り合わせたラバーです。
粒高ラバーと同程度に細く、それでいてノーマルな表ソフトの半分以下の高さの粒が「不規則」に並んでいます。
一応横目なのですが、ある列とある列は狭く、別の部分は間隔が広めになっています。
当然ITTFのマークはなく、ラバーのロゴもありません。
ラケット全体にニスが塗られていて、ラバーを貼る接着剤がはみ出した箇所がいたる所にあります。
とても軽く、片面にラバーが貼られた状態で88gです。
玉突きをしてみると、ラバーがあたかも衝撃吸収材のようなぱふぱふ感で、シートはカチカチ、そして回転はほとんど掛かりません。
あえて良い部分はないか探してみると、ラバーのフチはなめらかな処理で美しいカーブを描いていました。
恐らくラバーを貼った後で強引にヤスリがけをして、ならしたためだと思われます。
2016 .04.16
先日フリー参加形式の卓球場で、総当りの試合に参加しました。
居合わせたメンバーは、おおむね巷の皆さんの一般的な戦型を反映していました。
ペンホルダーは私1人だけ、左利きは1人だけ、残念ながらカットマンはいませんでした。
そのように把握していたのですが、審判をしながら対戦相手をチラ見していると、バック側が粒高ラバーの人が2人いることが分かりました。
今回は主にその2人についてお話します。
──────────────────────
粒高ラバーで相手を撹乱
──────────────────────
最初に対戦したAさんは、シェーク裏ソフト+粒高ラバーの選手によくあるタイプの方でした(カットマンは除外させてくださいね)。
台の真ん中近くに構え、バック側は粒高でブロックやプッシュをし、いやらしいボールで相手を翻弄します。
粒高は比較的レシーブがやりやすく、それなりに面を合わせるだけで相手コートへ入れることができます。
そういった利点もありAさんのような戦型は、シニアの方や立派な体格をお持ちの方が選択される傾向があります。
実際にAさんはどんな方だったかと言えば、ご想像にお任せしますということにしておきます。
こういう方にバックへ普通の下回転サーブを出すと、ナックルプッシュの餌食になります。
最もやってはいけないパターンです。
主にバックに出すのは、ナックルのロングサーブをコーナーめがけて出します。
それをショートで返球されてもボールのエグさはイマイチになり、3球目をミドル(利き腕のあたり)へ強打するのを得点パターンの1つにします。
ロングサーブはバックだけでなく、時折ミドルにも出してパターンを絞らせないようにします。
1本ぐらいは、自分のフォアサイドからストレートにロングサーブを出してみてもいいでしょう。
またロングサーブばかりでは駄目なので、フォア前に斜め下回転やナックルサーブも出します。
ショートサーブもフォア前に意識を集中させないよう、逆にバック側のサイドを切るような短い横回転も出してみます。
居合わせたメンバーは、おおむね巷の皆さんの一般的な戦型を反映していました。
ペンホルダーは私1人だけ、左利きは1人だけ、残念ながらカットマンはいませんでした。
そのように把握していたのですが、審判をしながら対戦相手をチラ見していると、バック側が粒高ラバーの人が2人いることが分かりました。
今回は主にその2人についてお話します。
──────────────────────
粒高ラバーで相手を撹乱
──────────────────────
最初に対戦したAさんは、シェーク裏ソフト+粒高ラバーの選手によくあるタイプの方でした(カットマンは除外させてくださいね)。
台の真ん中近くに構え、バック側は粒高でブロックやプッシュをし、いやらしいボールで相手を翻弄します。
粒高は比較的レシーブがやりやすく、それなりに面を合わせるだけで相手コートへ入れることができます。
そういった利点もありAさんのような戦型は、シニアの方や立派な体格をお持ちの方が選択される傾向があります。
実際にAさんはどんな方だったかと言えば、ご想像にお任せしますということにしておきます。
こういう方にバックへ普通の下回転サーブを出すと、ナックルプッシュの餌食になります。
最もやってはいけないパターンです。
主にバックに出すのは、ナックルのロングサーブをコーナーめがけて出します。
それをショートで返球されてもボールのエグさはイマイチになり、3球目をミドル(利き腕のあたり)へ強打するのを得点パターンの1つにします。
ロングサーブはバックだけでなく、時折ミドルにも出してパターンを絞らせないようにします。
1本ぐらいは、自分のフォアサイドからストレートにロングサーブを出してみてもいいでしょう。
またロングサーブばかりでは駄目なので、フォア前に斜め下回転やナックルサーブも出します。
ショートサーブもフォア前に意識を集中させないよう、逆にバック側のサイドを切るような短い横回転も出してみます。
2016 .04.09
時々お邪魔する練習場で、60代と思われる女性Yさんとお話をしていました。
Yさんはこれまでに出産などで何度かブランクがあったものの、ずっと卓球をやってきたそうです。
角丸型ペンホルダーの片面だけに裏ソフトラバーを貼り、昔からプレーしてきた人によくある戦型です。
長年頑なにマークVやスレイバーといったタイプのラバーを使っていたのですが、その日初めてハイテンションラバーに貼り替えて打つのだそうです。
──────────────────────
手に負えないじゃじゃ馬ラバー
──────────────────────
銘柄はバタフライのブライススピードでした。
ブライスシリーズなら、最新版のブライスハイスピードが話題になっています。
その影に隠れてしまい一時的に販売不振に陥ったためか、あるお店の特売品で売られていたのを買ったそうです。
30分ほど経ってふとベンチのほうを見ると、Yさんが浮かない顔をして座っています。
「どうしたんですか」と声をかけると「想像していたのと違いが大きくて戸惑っている」とのご意見でした。
かなり弾むだろうことは覚悟していて、止める系のボールは体全体を真綿のようにふわっとさせれば、捌(さば)ききれるはずと考えていたそうです。
独特の表現で、まあそれでもお考えはなんとなく伝わってきました。
それで真綿になったつもりでレシーブやツッツキをしてみたところ、いかんせんボールが吹っ飛んでしまって制御不能なんだそうです。
私のように使う用具が定まらず、あれもこれも試している人間ならもう少し控えめの感想だったかもしれません。
しかしほぼ同じカテゴリーの用具を、ひたすらウン十年使い続けていた人には衝撃だったのでしょう。
Yさんはこれまでに出産などで何度かブランクがあったものの、ずっと卓球をやってきたそうです。
角丸型ペンホルダーの片面だけに裏ソフトラバーを貼り、昔からプレーしてきた人によくある戦型です。
長年頑なにマークVやスレイバーといったタイプのラバーを使っていたのですが、その日初めてハイテンションラバーに貼り替えて打つのだそうです。
──────────────────────
手に負えないじゃじゃ馬ラバー
──────────────────────
銘柄はバタフライのブライススピードでした。
ブライスシリーズなら、最新版のブライスハイスピードが話題になっています。
その影に隠れてしまい一時的に販売不振に陥ったためか、あるお店の特売品で売られていたのを買ったそうです。
30分ほど経ってふとベンチのほうを見ると、Yさんが浮かない顔をして座っています。
「どうしたんですか」と声をかけると「想像していたのと違いが大きくて戸惑っている」とのご意見でした。
かなり弾むだろうことは覚悟していて、止める系のボールは体全体を真綿のようにふわっとさせれば、捌(さば)ききれるはずと考えていたそうです。
独特の表現で、まあそれでもお考えはなんとなく伝わってきました。
それで真綿になったつもりでレシーブやツッツキをしてみたところ、いかんせんボールが吹っ飛んでしまって制御不能なんだそうです。
私のように使う用具が定まらず、あれもこれも試している人間ならもう少し控えめの感想だったかもしれません。
しかしほぼ同じカテゴリーの用具を、ひたすらウン十年使い続けていた人には衝撃だったのでしょう。
某所にある卓球場の休憩場所には、かなりくたびれたテーブルが置いてあります。
どこかのフードコートで10年間使いこまれ、廃棄されたものをオーナーさんが拾ってきたようなブツです。
そのかたわらには、同じく凹みや汚れがあちこにちにあるカタログの陳列棚が置いてあり、雑誌やカタログが突っ込んであります。
ここの利用者が不要になったものを持ってきて、管理人さんが月一ぐらいで適当に整理しているようです。
それらをパラパラとめくったり、水分補給をしながら2人の方と雑談をしていました。
フリー参加の卓球場で、どちらも初めてお会いした方なのでお名前は分かりません。
1人は古舘伊知郎さんのように、眼鏡をかけていて軽快に話す人です。
もう1人は鈴木奈々さんのような(10倍ほど誇張しています)、明るく面白い人です。
──────────────────────
センスは良いが購入はためらわれる製品
──────────────────────
古舘さんはジュウイックのカタログを開き、コニヨールのラケットを見ていました。
ジュウイックは商社的な側面があり、コニヨールやノイバウアーといった海外メーカの製品も取り扱っています。
コニヨールはフランスの元世界チャンピオン、ガシアン選手モデルのラケットを販売しています。
どれもシックな色使いで高級そうに見えます。
実際お値段も一万円~二万円と高く、全般的に重量は重めです。
中には平均重量100gというのがあります。
また15枚合板というすごそうなのがあり、全ラインナップに中ペン(中国式ペンホルダー)が設定されています。
古舘さんは中ペンを使っているため、その部分を熱心に見ていました。
伏し目がちにため息をつき「こんなに重くて高いラケットはダメだね」と落胆した表情です。
両面に分厚いテンションラバーを貼っているので、下手をすると200g近くになるかもしれません。
中ペンはグリップが短い分、シェークより数グラム程度軽くなるはずですが、まあ気休めでしょうね。
どこかのフードコートで10年間使いこまれ、廃棄されたものをオーナーさんが拾ってきたようなブツです。
そのかたわらには、同じく凹みや汚れがあちこにちにあるカタログの陳列棚が置いてあり、雑誌やカタログが突っ込んであります。
ここの利用者が不要になったものを持ってきて、管理人さんが月一ぐらいで適当に整理しているようです。
それらをパラパラとめくったり、水分補給をしながら2人の方と雑談をしていました。
フリー参加の卓球場で、どちらも初めてお会いした方なのでお名前は分かりません。
1人は古舘伊知郎さんのように、眼鏡をかけていて軽快に話す人です。
もう1人は鈴木奈々さんのような(10倍ほど誇張しています)、明るく面白い人です。
──────────────────────
センスは良いが購入はためらわれる製品
──────────────────────
古舘さんはジュウイックのカタログを開き、コニヨールのラケットを見ていました。
ジュウイックは商社的な側面があり、コニヨールやノイバウアーといった海外メーカの製品も取り扱っています。
コニヨールはフランスの元世界チャンピオン、ガシアン選手モデルのラケットを販売しています。
どれもシックな色使いで高級そうに見えます。
実際お値段も一万円~二万円と高く、全般的に重量は重めです。
中には平均重量100gというのがあります。
また15枚合板というすごそうなのがあり、全ラインナップに中ペン(中国式ペンホルダー)が設定されています。
古舘さんは中ペンを使っているため、その部分を熱心に見ていました。
伏し目がちにため息をつき「こんなに重くて高いラケットはダメだね」と落胆した表情です。
両面に分厚いテンションラバーを貼っているので、下手をすると200g近くになるかもしれません。
中ペンはグリップが短い分、シェークより数グラム程度軽くなるはずですが、まあ気休めでしょうね。
先日、練習後に入った喫茶店でいつものように世間話をしていました。
その中で「自分が卓球ショップを経営するなら、どんなお店にするか」という話題が出ました。
居合わせたメンバーからさまざまな意見が出され、今回はそれらを紹介したいと思います。
──────────────────────
激しい勝負を挑むお店
──────────────────────
いきなり出たのが最も派手な営業スタイルのお店でした。
通販主体で激安価格に徹する方針のお店です。
積極的にネット広告を打ち、薄利多売で他社の追随を許さない戦略です。
いろんな経営スタイルのお店がありますが、最もリスク高めの営業だといえます。
店舗の内装や外装、従業員の身だしなみなどに気を使う必要はありません。
ネットでの受付のため、24時間365日の営業が可能です。
そういったアドバンテージで生まれた人やお金の余力を、システムの信頼性の維持、広告宣伝、値引きに充てます。
大変わかりやすいお店ですが、こういうタイプは競争が激しすぎ少数しか生き残れないのではないでしょうか。
また10年20年と安定した経営を続けるのも難しいように思えます。
卓球ショップに限らず、ネットの普及によりあらゆる業種で新業態のビジネスチャンスが生まれました。
ニュースや経済番組でそれらが取り上げられることはありますが、星のまばたきで終わったケースは成功例の何十倍にも上るはずです。
以上のような意見が次々と出され、やはりリアル店舗を構えた地域密着のお店が堅実だねという話に変わっていきました。
その中で「自分が卓球ショップを経営するなら、どんなお店にするか」という話題が出ました。
居合わせたメンバーからさまざまな意見が出され、今回はそれらを紹介したいと思います。
──────────────────────
激しい勝負を挑むお店
──────────────────────
いきなり出たのが最も派手な営業スタイルのお店でした。
通販主体で激安価格に徹する方針のお店です。
積極的にネット広告を打ち、薄利多売で他社の追随を許さない戦略です。
いろんな経営スタイルのお店がありますが、最もリスク高めの営業だといえます。
店舗の内装や外装、従業員の身だしなみなどに気を使う必要はありません。
ネットでの受付のため、24時間365日の営業が可能です。
そういったアドバンテージで生まれた人やお金の余力を、システムの信頼性の維持、広告宣伝、値引きに充てます。
大変わかりやすいお店ですが、こういうタイプは競争が激しすぎ少数しか生き残れないのではないでしょうか。
また10年20年と安定した経営を続けるのも難しいように思えます。
卓球ショップに限らず、ネットの普及によりあらゆる業種で新業態のビジネスチャンスが生まれました。
ニュースや経済番組でそれらが取り上げられることはありますが、星のまばたきで終わったケースは成功例の何十倍にも上るはずです。
以上のような意見が次々と出され、やはりリアル店舗を構えた地域密着のお店が堅実だねという話に変わっていきました。
2016 .03.19
今月行われた世界選手権では、最大8コートのライブ映像がITTF(国際卓球連盟)のWebサイトから同時配信されていました。
昔はこんなサービスはありませんでした。
全世界の卓球ファンを増やすため、今後もより一層の充実をお願いしたいと思います。
──────────────────────
ITTF様へのご要望
──────────────────────
一層の充実というのは映像クオリティであったり、Webサイトの見やすさの向上など様々な部分において強化ができる余地があり、それらをお願いしたい思いがあります。
私が特に重要度が高いと考えるのは、各言語ごとに表示を切り替えられる機能です。
サイトを訪れた人が、いろんな部分を見てみようかなと思う気持ちが起きるか失せるかは、母国語で案内されているかどうかで激しく差が出ます。
ITTFさん、どうか多言語対応は再優先で検討いただけるようお願いいたします。
英語だけでもそれなりに分かるからOKという人は、それぞれのコートで行われている試合をザッピングしたことと思います。
バタフライのかっこいい最新卓球台で行われている映像と、それより数ランク落ちるフレームむき出しの普通の卓球台で行われている映像がありました。
最初に見た普通の卓球台で行われていた試合は、映像の左下に得点表示があったりなかったりとバラバラで、ちょっと行き届いていない点がありました。
うーん、まあしょうがないかなと思い、次にフェンスの広告が自動的に変わり、スペシャル卓球台が鎮座している試合映像に切り替えました。
一見ちゃんとした内容に見えましたが、あれっ2試合目になっても1試合目の選手名のままです。
得点が0-0のままで変わらないのもあり、それなら一時的に得点表示を非表示にしてもらいたいです。
試合の模様は見ることができているので、我慢できるといえばできるレベルでした。
昔はこんなサービスはありませんでした。
全世界の卓球ファンを増やすため、今後もより一層の充実をお願いしたいと思います。
──────────────────────
ITTF様へのご要望
──────────────────────
一層の充実というのは映像クオリティであったり、Webサイトの見やすさの向上など様々な部分において強化ができる余地があり、それらをお願いしたい思いがあります。
私が特に重要度が高いと考えるのは、各言語ごとに表示を切り替えられる機能です。
サイトを訪れた人が、いろんな部分を見てみようかなと思う気持ちが起きるか失せるかは、母国語で案内されているかどうかで激しく差が出ます。
ITTFさん、どうか多言語対応は再優先で検討いただけるようお願いいたします。
英語だけでもそれなりに分かるからOKという人は、それぞれのコートで行われている試合をザッピングしたことと思います。
バタフライのかっこいい最新卓球台で行われている映像と、それより数ランク落ちるフレームむき出しの普通の卓球台で行われている映像がありました。
最初に見た普通の卓球台で行われていた試合は、映像の左下に得点表示があったりなかったりとバラバラで、ちょっと行き届いていない点がありました。
うーん、まあしょうがないかなと思い、次にフェンスの広告が自動的に変わり、スペシャル卓球台が鎮座している試合映像に切り替えました。
一見ちゃんとした内容に見えましたが、あれっ2試合目になっても1試合目の選手名のままです。
得点が0-0のままで変わらないのもあり、それなら一時的に得点表示を非表示にしてもらいたいです。
試合の模様は見ることができているので、我慢できるといえばできるレベルでした。
世界選手権の映像などを見て、トップ選手のプレーにため息をつき、思い立ったように自分もラケットを握る方はいらっしゃると思います。
ところがいざいつもの練習となると明確な課題も持たず、惰性でダラダラ続けるだけになってしまう人は多いのではないでしょうか。
これは私自身も戒めとして考えなければならないことです。
単調にならず中身の濃い練習にするにはどうすれば良いのでしょうか。
──────────────────────
最初の最初から集中する
──────────────────────
たとえば一番最初のフォア打ちから真剣に取り組むことを考えてみます。
まあ最初だからと単なる肩慣らしにするのはもったいないことです。
練習の最初の1分と最後の1分で長さが異なるわけではありません。
自分自身の集中の度合いで同じ密度の1分にすることは可能です。
しょっぱなの20回程度のラリーで、グリップやフォームのブレを補正し、全身の関節の動きを確認します。
集中力を高めるため、目を大きく開いたり細めたり、唇をギュッと結んだりゆるめたりするのも効果的です。
そうやってできるだけ早く自分をベストの状態に持っていくことです。
漫然とラリーを続けるのではなく、ボールを深く入れコーナーを狙いましょう。
速いドライブ、回転量の多いドライブ、台から若干距離をとって連続強打をする、とそれぞれ20回ずつ変えていくのも良いでしょう。
するとこれまでとは少なくとも2~3割程度は充実感がアップするはずです。
同様にバック側もプッシュ性ショートやドライブ、表ソフトの人ならナックル性ショートを混ぜてみます。
続けることが目的ではないので、プッシュの直後のナックル性ショートで相手はネットにかけやすいなど、いろいろパターンを試すという方法もあります。
ツッツキだと深い浅いを交互に繰り返したり、切る切らない、バウンド直後か少し待つか等を意識して使い分ける練習が考えられます。
ところがいざいつもの練習となると明確な課題も持たず、惰性でダラダラ続けるだけになってしまう人は多いのではないでしょうか。
これは私自身も戒めとして考えなければならないことです。
単調にならず中身の濃い練習にするにはどうすれば良いのでしょうか。
──────────────────────
最初の最初から集中する
──────────────────────
たとえば一番最初のフォア打ちから真剣に取り組むことを考えてみます。
まあ最初だからと単なる肩慣らしにするのはもったいないことです。
練習の最初の1分と最後の1分で長さが異なるわけではありません。
自分自身の集中の度合いで同じ密度の1分にすることは可能です。
しょっぱなの20回程度のラリーで、グリップやフォームのブレを補正し、全身の関節の動きを確認します。
集中力を高めるため、目を大きく開いたり細めたり、唇をギュッと結んだりゆるめたりするのも効果的です。
そうやってできるだけ早く自分をベストの状態に持っていくことです。
漫然とラリーを続けるのではなく、ボールを深く入れコーナーを狙いましょう。
速いドライブ、回転量の多いドライブ、台から若干距離をとって連続強打をする、とそれぞれ20回ずつ変えていくのも良いでしょう。
するとこれまでとは少なくとも2~3割程度は充実感がアップするはずです。
同様にバック側もプッシュ性ショートやドライブ、表ソフトの人ならナックル性ショートを混ぜてみます。
続けることが目的ではないので、プッシュの直後のナックル性ショートで相手はネットにかけやすいなど、いろいろパターンを試すという方法もあります。
ツッツキだと深い浅いを交互に繰り返したり、切る切らない、バウンド直後か少し待つか等を意識して使い分ける練習が考えられます。
2016 .03.05
私を含め大多数の卓球競技者は、そのへんのどこでも見かける一般庶民です。
そして現在行われている世界選手権のほとんどの視聴者も、そういった方々です。
そんな人たちが番組の翌日にどんな感想を口にしていたか、練習場で集めてみました。
──────────────────────
まずは美女軍団のご感想
──────────────────────
「世界選手権を見ましたか」と声をかけると、いきなりすごい返事が返ってきました。
「みうちゃんてずいぶん大きくなったのね」
えっ、平野美宇さんは今回出場していないはずですが・・・
どうやら浜本選手と勘違いしているようでした。
すかさず隣の女性からツッコミが入り「成長しすぎでしょ」と、浜本さんに対して失礼な意見が飛び出しました。
実況はテレビ東京の3名の男性アナウンサーが担当していました。
今回はその中に増田和也さんがいらっしゃいました。
「あの人、和風総本家のいじわるな人なのに、卓球の実況はまともなのね」
「あたりまえでしょ」と大爆笑が起こり、ご婦人方のパワーに圧倒されました。
他にも、ドイツの某選手は性格がキツそう(これは本当のようです)だとか、みまちゃんと同じピンクのアイフォン6が欲しいなどの話が次々と続きました。
結局私のネタ振りが格好のツカミになり、楽しい会話に発展していきました。
一人私は取り残されてしまいましたが、お役に立ててなによりです。
そして現在行われている世界選手権のほとんどの視聴者も、そういった方々です。
そんな人たちが番組の翌日にどんな感想を口にしていたか、練習場で集めてみました。
──────────────────────
まずは美女軍団のご感想
──────────────────────
「世界選手権を見ましたか」と声をかけると、いきなりすごい返事が返ってきました。
「みうちゃんてずいぶん大きくなったのね」
えっ、平野美宇さんは今回出場していないはずですが・・・
どうやら浜本選手と勘違いしているようでした。
すかさず隣の女性からツッコミが入り「成長しすぎでしょ」と、浜本さんに対して失礼な意見が飛び出しました。
実況はテレビ東京の3名の男性アナウンサーが担当していました。
今回はその中に増田和也さんがいらっしゃいました。
「あの人、和風総本家のいじわるな人なのに、卓球の実況はまともなのね」
「あたりまえでしょ」と大爆笑が起こり、ご婦人方のパワーに圧倒されました。
他にも、ドイツの某選手は性格がキツそう(これは本当のようです)だとか、みまちゃんと同じピンクのアイフォン6が欲しいなどの話が次々と続きました。
結局私のネタ振りが格好のツカミになり、楽しい会話に発展していきました。
一人私は取り残されてしまいましたが、お役に立ててなによりです。
2016 .02.27
少し前に1枚ラバーについてお話をしました。
そんな変わった製品を使う人はめったにいませんが、偶然にも先月1枚ラバーについて相談したいという方がいらっしゃいました。
大変長い前置きになりますが、相談に至るまでの経緯は以下の様なものでした。
──────────────────────
ほとんどの人には無縁の相談内容
──────────────────────
その方は長らくスポンジが極薄の表ソフトを使っていました。
スポンジが薄い分ボールの食い込みが少なく、相手のドライブをブロックしたりするのは難しい一方、ツッツキの変化のつけやすさやスマッシュした時の快感がたまらず使い続けていたそうです。
自分の今のスタイルをもっと極めたいと考え、それはすなわち1枚ラバーだろうという結論に至ったそうです。
お試しとして通販で激安の中国ラバーを買いました。
はやる気持ちを抑えつつ貼り替えてみると、打球感があまりにも違いすぎ愕然としました。
極薄のスポンジと1枚ラバーで、これほどの差があるとは夢にも思わなかったそうです。
カキンカキンすぎて、その人には受けつけられなかったのです。
スポンジが薄くなってくると、ほんのわずかな違いにも敏感になります。
一部のラバーに、薄、極薄、超極薄などのバリエーションがあるのは、そういう細かい要望に応えて製品化されているのです。
どうしようかと調べていると、1枚ラバーはゴムシート単体のものがほとんどですが、少数ながらシートの裏に布地がついた製品があります。
それは打球感が柔らかめになるということがわかりました。
以前ここでも紹介したヤサカのA-1・2というラバーなどが該当します。
早速買い求め試し打ちをしてみると、想像していたイメージに近い感触だったそうです。
満足できていたのもつかの間、ちょっぴり気になる問題がありました。
布地がついたラバーは反り返ってきて、縁のほうからめくれやすいのです。
練習中に何度も何度も浮き上がってきた箇所を指で押さえていると、イライラがつのってきました。
そう言えば似たようなことで神経質なのが、中国の張継科選手です。
彼はラバーの周囲にサイドテープをぐるっと貼っていますが、それがしっかり接着されているかを頻繁に押さえて確認しています。
そんな変わった製品を使う人はめったにいませんが、偶然にも先月1枚ラバーについて相談したいという方がいらっしゃいました。
大変長い前置きになりますが、相談に至るまでの経緯は以下の様なものでした。
──────────────────────
ほとんどの人には無縁の相談内容
──────────────────────
その方は長らくスポンジが極薄の表ソフトを使っていました。
スポンジが薄い分ボールの食い込みが少なく、相手のドライブをブロックしたりするのは難しい一方、ツッツキの変化のつけやすさやスマッシュした時の快感がたまらず使い続けていたそうです。
自分の今のスタイルをもっと極めたいと考え、それはすなわち1枚ラバーだろうという結論に至ったそうです。
お試しとして通販で激安の中国ラバーを買いました。
はやる気持ちを抑えつつ貼り替えてみると、打球感があまりにも違いすぎ愕然としました。
極薄のスポンジと1枚ラバーで、これほどの差があるとは夢にも思わなかったそうです。
カキンカキンすぎて、その人には受けつけられなかったのです。
スポンジが薄くなってくると、ほんのわずかな違いにも敏感になります。
一部のラバーに、薄、極薄、超極薄などのバリエーションがあるのは、そういう細かい要望に応えて製品化されているのです。
どうしようかと調べていると、1枚ラバーはゴムシート単体のものがほとんどですが、少数ながらシートの裏に布地がついた製品があります。
それは打球感が柔らかめになるということがわかりました。
以前ここでも紹介したヤサカのA-1・2というラバーなどが該当します。
早速買い求め試し打ちをしてみると、想像していたイメージに近い感触だったそうです。
満足できていたのもつかの間、ちょっぴり気になる問題がありました。
布地がついたラバーは反り返ってきて、縁のほうからめくれやすいのです。
練習中に何度も何度も浮き上がってきた箇所を指で押さえていると、イライラがつのってきました。
そう言えば似たようなことで神経質なのが、中国の張継科選手です。
彼はラバーの周囲にサイドテープをぐるっと貼っていますが、それがしっかり接着されているかを頻繁に押さえて確認しています。
2016 .02.20
バタフライのラバーは、統一されたデザインの新パッケージに変わりました。
現在はまだ新旧パッケージが混在しているお店があり、製造時期の違いがひと目で判別できます。
普段はスーパーでパック牛乳の製造日を目を皿のようにして見ているため、この便利さはとても助かります。
──────────────────────
実は考えぬかれたデザインだった
──────────────────────
テナジー05といった売れ筋ラバーなら、新パッケージへすぐに切り替わるでしょう。
しかしオーソドックスDXのような売れ筋ではなく長持ちしそうなラバーなら、長期間旧パッケージのまま陳列され続けそうです。
あの新デザインはネット上でボンカレーと呼ばれたりしています。
単純で分かりやすいという意見、個性がなくなりつまらないという意見、両方が交錯しています。
私はどこかのデザイン会社に発注して、ささっと決めたのだろうと思っていました。
ところが意外にも、以下の様に熟考に熟考を重ねた末のデザインだったそうです。
『このデザインが完成するまでに、 バタフライは長期にわたって試作と議論を重ねた』
『ボツになったデザインは数十案にも及ぶ』
『あるデザイン案はエネルギーを表現し切れていない、別のデザイン案は普遍性に欠けるなど、苦悩しながらイメージを固めるまでに半年以上、細部の仕上げを含めると1年以上の期間をかけた』
そんなにデザインをじっくり練ることができて羨ましい限りです。
過去に私は会社でパンフレット作る際、某社とやりとりをしたことがありました。
その某社は要求通りA案からD案まで4種類のデザインを提示してきました。
ところが誰が見てもA案しか選びようがなく、B案からD案まではあたかもA案を引き立てるかのようなガッカリ付け足し図案でした。
窓口担当になった私の人物像を見てなめられてしまったのでしょうか。
上司は苦々しい表情をして「時間も金もないからA案で進めろ」と吐き捨てるように私に指示しました。
その後某社の方と細部を詰めていると、どうやら私の上司が指定した納期と発注額が通常よりも厳しすぎ、こういう成果物しか出せなかったというのが真相のようでした。
現在はまだ新旧パッケージが混在しているお店があり、製造時期の違いがひと目で判別できます。
普段はスーパーでパック牛乳の製造日を目を皿のようにして見ているため、この便利さはとても助かります。
──────────────────────
実は考えぬかれたデザインだった
──────────────────────
テナジー05といった売れ筋ラバーなら、新パッケージへすぐに切り替わるでしょう。
しかしオーソドックスDXのような売れ筋ではなく長持ちしそうなラバーなら、長期間旧パッケージのまま陳列され続けそうです。
あの新デザインはネット上でボンカレーと呼ばれたりしています。
単純で分かりやすいという意見、個性がなくなりつまらないという意見、両方が交錯しています。
私はどこかのデザイン会社に発注して、ささっと決めたのだろうと思っていました。
ところが意外にも、以下の様に熟考に熟考を重ねた末のデザインだったそうです。
『このデザインが完成するまでに、 バタフライは長期にわたって試作と議論を重ねた』
『ボツになったデザインは数十案にも及ぶ』
『あるデザイン案はエネルギーを表現し切れていない、別のデザイン案は普遍性に欠けるなど、苦悩しながらイメージを固めるまでに半年以上、細部の仕上げを含めると1年以上の期間をかけた』
そんなにデザインをじっくり練ることができて羨ましい限りです。
過去に私は会社でパンフレット作る際、某社とやりとりをしたことがありました。
その某社は要求通りA案からD案まで4種類のデザインを提示してきました。
ところが誰が見てもA案しか選びようがなく、B案からD案まではあたかもA案を引き立てるかのようなガッカリ付け足し図案でした。
窓口担当になった私の人物像を見てなめられてしまったのでしょうか。
上司は苦々しい表情をして「時間も金もないからA案で進めろ」と吐き捨てるように私に指示しました。
その後某社の方と細部を詰めていると、どうやら私の上司が指定した納期と発注額が通常よりも厳しすぎ、こういう成果物しか出せなかったというのが真相のようでした。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。