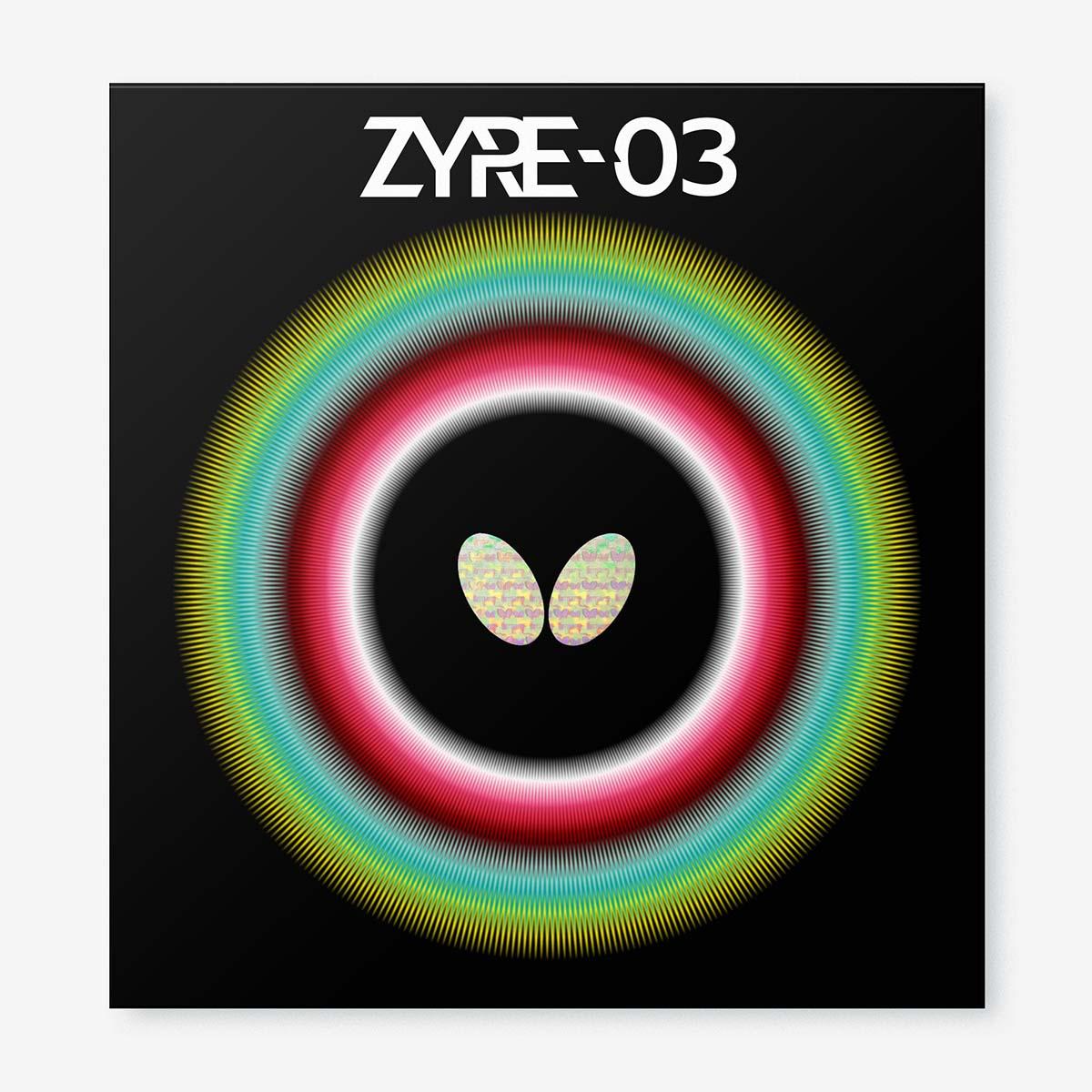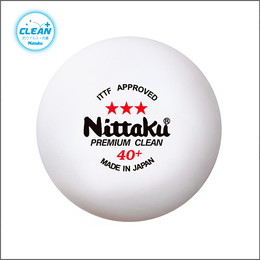練習場で交わされる会話には様々な相談事もあります。
これまでに話を持ちかけられた中から2件をご紹介します。
──────────────────────
製品の特徴が伝わらなかった例
──────────────────────
ペンホルダーグリップの付け根部分を、私はマイ用語で「水かき」と呼んでいます。
私はその水かきが無いほうが好きで、曲線を描いてなだらかにグリップに接する部分をカッターやヤスリで削り2本の線がぶつかるような形に加工しています。
10年以上前にバタフライは裏面打法がやりやすいペンホルダーのラケットとして、クリテリオンとバックフェイスという2種類の製品を販売していました。
どういう点でやりやすいかというと、オモテ面の親指が当たる水かき部分が通常のペンのラケットよりもぐぐっと出っ張っていて、裏面打法をするときに安定して角度を出せるようになっています。
このラケットのグリップは反転式ペンのように、グリップエンド側が平坦になった形です。
といっても反転させて使うわけではありません。
反転させてしまうと、今度は人差し指側の水かきが出っ張った状態になってしまいとても使いづらくなってしまうからです。
こういうグリップにしたのは左右どちらの手で握っても使えるようにしているためで、こうやって文字で説明すると分かりにくいと思いますので、気になる人は暇なときに絵を書いてご確認いただければと思います。
これまでに話を持ちかけられた中から2件をご紹介します。
──────────────────────
製品の特徴が伝わらなかった例
──────────────────────
ペンホルダーグリップの付け根部分を、私はマイ用語で「水かき」と呼んでいます。
私はその水かきが無いほうが好きで、曲線を描いてなだらかにグリップに接する部分をカッターやヤスリで削り2本の線がぶつかるような形に加工しています。
10年以上前にバタフライは裏面打法がやりやすいペンホルダーのラケットとして、クリテリオンとバックフェイスという2種類の製品を販売していました。
どういう点でやりやすいかというと、オモテ面の親指が当たる水かき部分が通常のペンのラケットよりもぐぐっと出っ張っていて、裏面打法をするときに安定して角度を出せるようになっています。
このラケットのグリップは反転式ペンのように、グリップエンド側が平坦になった形です。
といっても反転させて使うわけではありません。
反転させてしまうと、今度は人差し指側の水かきが出っ張った状態になってしまいとても使いづらくなってしまうからです。
こういうグリップにしたのは左右どちらの手で握っても使えるようにしているためで、こうやって文字で説明すると分かりにくいと思いますので、気になる人は暇なときに絵を書いてご確認いただければと思います。
2015 .08.29
バタフライは2014年から製品のラインアップを抑え始めました。
2014年後半に出たカタログは部分的な商品の紹介に留まっていました。
それは次のタイミングでかなりの製品が変わりそうだというきざしであり、期待と不安が渦巻いていました。
年が明けると春のカタログを待たずにテナジーの大幅値上げが行われ、その混乱が続く中で新製品の発表がありました。
ラケットやラバーに関し、従来との大きな違いは以下の2点でした。
・ラインアップの縮小
・オープン価格
──────────────────────
ラインアップの縮小
──────────────────────
ラインアップの縮小は良かったのではないかと考えています。
昔のようにあれだけたくさんの品揃えがあると、企画している側でさえ全てを詳細に把握できていなかったと思います。
販売店側も説明に困り、面倒くさいので定番のものを勧めることにしていたところもあったはずです。
いろいろな選択肢があるのはうれしいことなのですが、種類が多すぎると途方に暮れてしまい逆効果になります。
今回軌道修正したバタフライさんには拍手を送りたいと思います。
さてその一方でトップメーカーを追随する2番手3番手のメーカは、負けじと似たような戦略を取ることが多くなります。
ニッタクは以前のバタフライそのもので、TSPも製品の種類を拡大する方向です。
バタフライの方針変更を受けて2社はどうなるのでしょう。
ラインアップの集約は後追いと批判されても構わないので同調して欲しいと思います。
そして少しだけですが独自色を出し、バタフライが大幅に削減したペンホルダーとカットマンラケットを補完してくれればうれしいです。
2014年後半に出たカタログは部分的な商品の紹介に留まっていました。
それは次のタイミングでかなりの製品が変わりそうだというきざしであり、期待と不安が渦巻いていました。
年が明けると春のカタログを待たずにテナジーの大幅値上げが行われ、その混乱が続く中で新製品の発表がありました。
ラケットやラバーに関し、従来との大きな違いは以下の2点でした。
・ラインアップの縮小
・オープン価格
──────────────────────
ラインアップの縮小
──────────────────────
ラインアップの縮小は良かったのではないかと考えています。
昔のようにあれだけたくさんの品揃えがあると、企画している側でさえ全てを詳細に把握できていなかったと思います。
販売店側も説明に困り、面倒くさいので定番のものを勧めることにしていたところもあったはずです。
いろいろな選択肢があるのはうれしいことなのですが、種類が多すぎると途方に暮れてしまい逆効果になります。
今回軌道修正したバタフライさんには拍手を送りたいと思います。
さてその一方でトップメーカーを追随する2番手3番手のメーカは、負けじと似たような戦略を取ることが多くなります。
ニッタクは以前のバタフライそのもので、TSPも製品の種類を拡大する方向です。
バタフライの方針変更を受けて2社はどうなるのでしょう。
ラインアップの集約は後追いと批判されても構わないので同調して欲しいと思います。
そして少しだけですが独自色を出し、バタフライが大幅に削減したペンホルダーとカットマンラケットを補完してくれればうれしいです。
2015 .08.22
自分で何かを試みようとしたとき「そんなことをやっても無駄」と言われることがあります。
その一方で「やってもいないくせに」と正反対の言葉を返されることもあります。
要はケースバイケースになると思いますが、卓球の場合なら広く浅く試してみればいいのではというのが私の考えです。
これまでにもいくつかのラバーやラケット、そしてプレースタイルにチャレンジしてみました。
試してみるときは先入観を捨てるのではなく、巷の人が持っている先入観を前向きに分析しながらやってみることが多いです。
また相手をしてくれる人は奇妙に感じることがあり、必ずざっと説明してからやるようにしています。
前置きが長くなりましたが、今回試してみたのはペンホルダーのカットマンです。
──────────────────────
想像と現実のギャップ
──────────────────────
使用したラケットは、以前シェークのカットマンを試した時に使ったのと同じものでした。
フォア側に薄い裏ソフトを貼り、バック側はペラペラスポンジの粒高ラバーです。
これをペン持ちし、フォアカットは裏ソフトで、バックカットは裏面の粒高ラバーで打つスタイルです。
通常はペンホルダーを使っているので、シェークのカットマンをやった時のようにペンとシェークの慣れの差による、ツッツキ等のもどかしさはありませんでした。
そして普通に球出ししてもらうボールなら、フォアカットでそこそこ返球できます。
問題はバックカットでした。
シェークのカットマンのときよりも輪をかけてひどい有様で、まともに返すことができません。
その一方で「やってもいないくせに」と正反対の言葉を返されることもあります。
要はケースバイケースになると思いますが、卓球の場合なら広く浅く試してみればいいのではというのが私の考えです。
これまでにもいくつかのラバーやラケット、そしてプレースタイルにチャレンジしてみました。
試してみるときは先入観を捨てるのではなく、巷の人が持っている先入観を前向きに分析しながらやってみることが多いです。
また相手をしてくれる人は奇妙に感じることがあり、必ずざっと説明してからやるようにしています。
前置きが長くなりましたが、今回試してみたのはペンホルダーのカットマンです。
──────────────────────
想像と現実のギャップ
──────────────────────
使用したラケットは、以前シェークのカットマンを試した時に使ったのと同じものでした。
フォア側に薄い裏ソフトを貼り、バック側はペラペラスポンジの粒高ラバーです。
これをペン持ちし、フォアカットは裏ソフトで、バックカットは裏面の粒高ラバーで打つスタイルです。
通常はペンホルダーを使っているので、シェークのカットマンをやった時のようにペンとシェークの慣れの差による、ツッツキ等のもどかしさはありませんでした。
そして普通に球出ししてもらうボールなら、フォアカットでそこそこ返球できます。
問題はバックカットでした。
シェークのカットマンのときよりも輪をかけてひどい有様で、まともに返すことができません。
2015 .08.15
今回も前回に引き続き、買っておけばよかったと思うラケットのお話をします。
練習場で時々お会いするTさんにも気になっていた廃番ラケットがあります。
前回私が選んだ3本の内、ヨーラのボムエクストリームは同じご意見でした。
Tさんも高反発ラケットが好きで、その中でも打球感がハードで手にビンビン響くタイプが比較的好みなのだそうです。
──────────────────────
バタフライのシュラガー
──────────────────────
中国人以外の最後のシングルス世界チャンピオンと言われているシュラガー選手のモデルです。
YGサーブから一撃必殺ドライブを叩き込むスタイルで、フォームだけ見ていると体の使い方が少しぎこちなく、柔軟体操が苦手な人のように見えてしまいます。
このラケットは性能チャートの最も右上に長期間君臨していたフラッグシップモデルです。
座標の上にいくほどよく弾み、右にいくほどハードな打球感です。
特殊素材にカーボンだけを使い、かっ飛びラケットの代名詞のように話の引き合いに出されていました。
チャート上ではすぐそばにプリモラッツカーボンもあり、それも十分ぶっ飛びでカキンカキンのラケットでした。
でもやはりみなさんは一番右上のものに目がいってしまい、ほんの少しの差でこのラケットに注目が集まりました。
こういうケースでは「2位じゃだめなんです」ということが分かります。
現行製品だとガレイディアT5000が位置する場所で、このラケットもカーボンだけを使ったモデルです。
練習場で時々お会いするTさんにも気になっていた廃番ラケットがあります。
前回私が選んだ3本の内、ヨーラのボムエクストリームは同じご意見でした。
Tさんも高反発ラケットが好きで、その中でも打球感がハードで手にビンビン響くタイプが比較的好みなのだそうです。
──────────────────────
バタフライのシュラガー
──────────────────────
中国人以外の最後のシングルス世界チャンピオンと言われているシュラガー選手のモデルです。
YGサーブから一撃必殺ドライブを叩き込むスタイルで、フォームだけ見ていると体の使い方が少しぎこちなく、柔軟体操が苦手な人のように見えてしまいます。
このラケットは性能チャートの最も右上に長期間君臨していたフラッグシップモデルです。
座標の上にいくほどよく弾み、右にいくほどハードな打球感です。
特殊素材にカーボンだけを使い、かっ飛びラケットの代名詞のように話の引き合いに出されていました。
チャート上ではすぐそばにプリモラッツカーボンもあり、それも十分ぶっ飛びでカキンカキンのラケットでした。
でもやはりみなさんは一番右上のものに目がいってしまい、ほんの少しの差でこのラケットに注目が集まりました。
こういうケースでは「2位じゃだめなんです」ということが分かります。
現行製品だとガレイディアT5000が位置する場所で、このラケットもカーボンだけを使ったモデルです。
2015 .08.08
メーカは同じ製品をずっと作り続けることはなく、かなりのものは数年程度で販売を終了させます。
ラバーは比較的ロングセラーが多いですが、ユニフォームやシューズは総じて短命でラケットも7~8年続けば長い方ではないでしょうか。
昔のカタログを眺めながら、そういえばこの製品を買っておけばよかったかなと思うことがたまにあります。
ラケットについて私が未練のある廃番製品を挙げるとしたら、以下の3つになります。
──────────────────────
アンドロのキネティックCFカーボンOFF+
──────────────────────
ブレードの両面は黒で側面(断面)は赤になっています。
グリップには黄色い5本の縞模様があり、スズメバチかクモのような危険な生き物をイメージさせます。
高反発のカーボンラケットに攻撃的な印象のデザインを施し、総合的な完成度が非常に高いラケットでした。
ラケットの色なんてどうでもいいと考えている人もいるでしょう。
でもブレードが灰色や黒といった暗い色だと、白木のままより高性能かつ高級に見えます。
ラバーを貼れば大部分は隠れてしまいますが、購入前のお客さんが目にするのはラバーがまだ貼られていないブレード単体であり、またその状態のカタログ写真なのです。
そこにサイドの赤いラインが加われば、かっ飛びラケットの妄想が膨らみます。
アクセントとしての赤いラインを入れるのは車も同様で、フォルクスワーゲンゴルフのGTIやスズキアルトのターボ車といった高性能タイプに使われています。
そしてこのラケットは、キネティックシリーズに共通のシャカシャカ音が鳴る仕組みも気に入っていました。
余計だったのはもれなくラケットケースがついていて、その費用が含まれている高い価格と他の製品よりも二回り大きいパッケージサイズがちょっと残念でした。
ラバーは比較的ロングセラーが多いですが、ユニフォームやシューズは総じて短命でラケットも7~8年続けば長い方ではないでしょうか。
昔のカタログを眺めながら、そういえばこの製品を買っておけばよかったかなと思うことがたまにあります。
ラケットについて私が未練のある廃番製品を挙げるとしたら、以下の3つになります。
──────────────────────
アンドロのキネティックCFカーボンOFF+
──────────────────────
ブレードの両面は黒で側面(断面)は赤になっています。
グリップには黄色い5本の縞模様があり、スズメバチかクモのような危険な生き物をイメージさせます。
高反発のカーボンラケットに攻撃的な印象のデザインを施し、総合的な完成度が非常に高いラケットでした。
ラケットの色なんてどうでもいいと考えている人もいるでしょう。
でもブレードが灰色や黒といった暗い色だと、白木のままより高性能かつ高級に見えます。
ラバーを貼れば大部分は隠れてしまいますが、購入前のお客さんが目にするのはラバーがまだ貼られていないブレード単体であり、またその状態のカタログ写真なのです。
そこにサイドの赤いラインが加われば、かっ飛びラケットの妄想が膨らみます。
アクセントとしての赤いラインを入れるのは車も同様で、フォルクスワーゲンゴルフのGTIやスズキアルトのターボ車といった高性能タイプに使われています。
そしてこのラケットは、キネティックシリーズに共通のシャカシャカ音が鳴る仕組みも気に入っていました。
余計だったのはもれなくラケットケースがついていて、その費用が含まれている高い価格と他の製品よりも二回り大きいパッケージサイズがちょっと残念でした。
2015 .08.01
2回にわたりジャパン・オープンの話をお届けし、それで終わりとする予定でした。
ところが観戦に出かけた特派員X氏と先日喫茶店に入った際、再び熱い話を饒舌に語ってくれました。
いろいろと面白かったので、内容の一部をパート3としてご紹介いたします。
──────────────────────
あえぎ声
──────────────────────
力を込めて打つ時は瞬間的に息を止め、打球後のフォロースルーで吐き出します。
息を止める直前にノドの部分を絞るので、声帯が圧迫されて声が出ることがあります。
福原選手がバック前にきたチャンスボールを「ふんっ!」とうなりながらひっぱたくのを時折目にすることがあります。
その手の声が連続して聞こえてくるのが、カットマンと対戦中のドライブマンです。
水谷選手は韓国のチュセヒュク選手との試合で、苦しそうなうめき声を上げながらドライブを打ち続けていました。
こういう声にも選手ごとに個性があり、X氏的には水谷選手の声は普通っぽいのだそうです。
ジャパン・オープンには出場していませんでしたが、ドイツのオフチャロフ選手はその大柄な体格とは反対の、か弱そうな?うめき声を出します。
見た目と声にギャップがあり有名なのはクロアチアのベテラン、プリモラッツ選手です。
もだえているような声にも聞こえ、カット打ちの映像なしで音声だけだと気持ち悪さ満点です。
これら選手と一線を画するのがクールな丹羽選手です。
村松選手との対戦で同じく苦しそうにカットを持ち上げていました。
しかし力を入れるため大きく息を吸い込む時、彼の声帯は震えず無音なのです。
打球し終えた直後の荒い呼気だけが観客席に聞こえてきます。
なんだか電車やバスの「プハー」という停止音を思わせ、人間ぽくありません。
ところが観戦に出かけた特派員X氏と先日喫茶店に入った際、再び熱い話を饒舌に語ってくれました。
いろいろと面白かったので、内容の一部をパート3としてご紹介いたします。
──────────────────────
あえぎ声
──────────────────────
力を込めて打つ時は瞬間的に息を止め、打球後のフォロースルーで吐き出します。
息を止める直前にノドの部分を絞るので、声帯が圧迫されて声が出ることがあります。
福原選手がバック前にきたチャンスボールを「ふんっ!」とうなりながらひっぱたくのを時折目にすることがあります。
その手の声が連続して聞こえてくるのが、カットマンと対戦中のドライブマンです。
水谷選手は韓国のチュセヒュク選手との試合で、苦しそうなうめき声を上げながらドライブを打ち続けていました。
こういう声にも選手ごとに個性があり、X氏的には水谷選手の声は普通っぽいのだそうです。
ジャパン・オープンには出場していませんでしたが、ドイツのオフチャロフ選手はその大柄な体格とは反対の、か弱そうな?うめき声を出します。
見た目と声にギャップがあり有名なのはクロアチアのベテラン、プリモラッツ選手です。
もだえているような声にも聞こえ、カット打ちの映像なしで音声だけだと気持ち悪さ満点です。
これら選手と一線を画するのがクールな丹羽選手です。
村松選手との対戦で同じく苦しそうにカットを持ち上げていました。
しかし力を入れるため大きく息を吸い込む時、彼の声帯は震えず無音なのです。
打球し終えた直後の荒い呼気だけが観客席に聞こえてきます。
なんだか電車やバスの「プハー」という停止音を思わせ、人間ぽくありません。
2015 .07.25
少し前に私が理想とするラケットの仕様について述べさせてもらいました。
今回はそのシューズ版になります。
シューズはラケットほどこだわりがないため、最初はそんなにあれやこれやと要望はないと思っていました。
まあそれでも2つ3つくらいはあるかなと、そばにあったレシートの裏側にボールペンで書き出しているとスペースが足りなくなるほど出てきました。
──────────────────────
安くて長持ち
──────────────────────
基本コンセプトは質実剛健であり、ナイキの最新モデルのような派手さやイケてる感はなくて構いません。
価格も重要な要素で五千円程度に抑えるべきです。
いろいろある耐久性を高めるポイントの中で、最も重視して欲しいのはソールとアッパーの接合です。
以前にも触れたことがありますが、昔履いていたヨネックスのバドミントンシューズはこの点がダメダメでした。
接着剤だけで貼り合わせているので剥離しやすく、右足のほうは360度全方向に隙間ができてしまいました。
そういう状態では踏ん張る際にブレるような感触があり、接着剤を購入し貼り合わせてみましたがうまく行きませんでした。
仕方なく今は外履きの靴として余生を送っていて、靴底が摩耗しつくしたら捨てる予定です。
従ってソールとアッパーの接合は接着剤だけでなく、ステッチで周囲をガッチリ縫製すべきです。
インナーソールは均一の素材ではなく、指やかかとの部分は強度を上げます。
特にすり減りやすい親指部分は耐久性を持たせます。
履き口の縁もすり切れやすい箇所です。
表面の素材が破れると、中に詰めているスポンジはふわふわなのですぐにちぎれてなくなってしまいます。
素人の考えですが、この部分はスポンジではなく布を重ね合わせるなど、少しくらい硬くなってもよいので脆さを克服してはどうかと思います。
(そんな作りにすると硬すぎて靴ずれしたりすることになるのでしょうか?)
今回はそのシューズ版になります。
シューズはラケットほどこだわりがないため、最初はそんなにあれやこれやと要望はないと思っていました。
まあそれでも2つ3つくらいはあるかなと、そばにあったレシートの裏側にボールペンで書き出しているとスペースが足りなくなるほど出てきました。
──────────────────────
安くて長持ち
──────────────────────
基本コンセプトは質実剛健であり、ナイキの最新モデルのような派手さやイケてる感はなくて構いません。
価格も重要な要素で五千円程度に抑えるべきです。
いろいろある耐久性を高めるポイントの中で、最も重視して欲しいのはソールとアッパーの接合です。
以前にも触れたことがありますが、昔履いていたヨネックスのバドミントンシューズはこの点がダメダメでした。
接着剤だけで貼り合わせているので剥離しやすく、右足のほうは360度全方向に隙間ができてしまいました。
そういう状態では踏ん張る際にブレるような感触があり、接着剤を購入し貼り合わせてみましたがうまく行きませんでした。
仕方なく今は外履きの靴として余生を送っていて、靴底が摩耗しつくしたら捨てる予定です。
従ってソールとアッパーの接合は接着剤だけでなく、ステッチで周囲をガッチリ縫製すべきです。
インナーソールは均一の素材ではなく、指やかかとの部分は強度を上げます。
特にすり減りやすい親指部分は耐久性を持たせます。
履き口の縁もすり切れやすい箇所です。
表面の素材が破れると、中に詰めているスポンジはふわふわなのですぐにちぎれてなくなってしまいます。
素人の考えですが、この部分はスポンジではなく布を重ね合わせるなど、少しくらい硬くなってもよいので脆さを克服してはどうかと思います。
(そんな作りにすると硬すぎて靴ずれしたりすることになるのでしょうか?)
いつだったか、挫折してやめていた裏面打法に再チャレンジしましたと書いたような記憶があります。
まあ別にそういうのは選挙公約などとは異なり、誰に責任を負うものでもありません。
ヘタレで才能がないことをしみじみと噛みしめた上で、現在は片面ペンのスタイルに戻っています。
──────────────────────
ラバーがあった場所の処理
──────────────────────
裏面のラバーが不要になると、そんな重くて邪魔なものはただちにひっぺがすことになります。
普通ならその跡地に、すべり止めのスポンジなりコルクシートを貼ったりする人がいるでしょう。
しかしラケットを保護する溶液+ラバーの接着剤を塗った裏面はネバネバで、指の当たる部分にのみすべり止めを貼っても、その他の部分を放置しておくわけにはいきません。
こういった方面に詳しい方なら、何か別の薬品でネバネバを除去する方法もあるはずです。
でもラケットにあれやこれやといろんな溶液を塗るのは板に優しくなさそうで、加えて粘着物質を取る薬品もそこそこいいお値段がしそうです。
ここはやはり一番お手軽な、用具メーカが販売している裏面シートを貼ってみようと考えました。
裏面シートはバタフライ、ニッタク、ジュウイックが販売しています。
バタフライは裏面の半円コルクがあることを前提にした形状になっています。
裏面打法に使っていたラケットは半円コルクのない中国式ペンホルダーだったため、バタフライは選定対象とはなりませんでした。
次の練習の日まであまり日にちがなく、所用の途中で立ち寄ったお店で買うことにしました。
ニッタクの黒いシートを選び代金を払おうとすると¥270とのことでした。
たぶん2割引きかなと予想していたため、希望小売価格+消費税そのままを告げられたことに少し驚きました。
まあ別にそういうのは選挙公約などとは異なり、誰に責任を負うものでもありません。
ヘタレで才能がないことをしみじみと噛みしめた上で、現在は片面ペンのスタイルに戻っています。
──────────────────────
ラバーがあった場所の処理
──────────────────────
裏面のラバーが不要になると、そんな重くて邪魔なものはただちにひっぺがすことになります。
普通ならその跡地に、すべり止めのスポンジなりコルクシートを貼ったりする人がいるでしょう。
しかしラケットを保護する溶液+ラバーの接着剤を塗った裏面はネバネバで、指の当たる部分にのみすべり止めを貼っても、その他の部分を放置しておくわけにはいきません。
こういった方面に詳しい方なら、何か別の薬品でネバネバを除去する方法もあるはずです。
でもラケットにあれやこれやといろんな溶液を塗るのは板に優しくなさそうで、加えて粘着物質を取る薬品もそこそこいいお値段がしそうです。
ここはやはり一番お手軽な、用具メーカが販売している裏面シートを貼ってみようと考えました。
裏面シートはバタフライ、ニッタク、ジュウイックが販売しています。
バタフライは裏面の半円コルクがあることを前提にした形状になっています。
裏面打法に使っていたラケットは半円コルクのない中国式ペンホルダーだったため、バタフライは選定対象とはなりませんでした。
次の練習の日まであまり日にちがなく、所用の途中で立ち寄ったお店で買うことにしました。
ニッタクの黒いシートを選び代金を払おうとすると¥270とのことでした。
たぶん2割引きかなと予想していたため、希望小売価格+消費税そのままを告げられたことに少し驚きました。
2015 .07.11
前回に引き続き、ジャパン・オープン大会3日目の観戦に出かけた特派員X氏のリポートをお届けします。
──────────────────────
遠慮せず最前列に進もう
──────────────────────
複数コートに分散して同時スタートする状況では、お目当ての試合ごとに席を移動することで、ベストポジションでの観戦を続けることができます。
そのためには少しだけ思いやりと積極性が必要になります。
来場したのは平日でありそれほど混んでいませんでした。
しかしながら会場全体としては席に余裕があっても、観客の皆さんはコートに一番近い場所を中心に偏って座ります。
最前列はびっしり埋まっているかといえばそうでもなく、まばらに1席だけ空いていたりカバンが置いてある場合もあります。
大抵の場合は「済みません」「そこ空いていますか」といったクッション言葉とともに空き席に滑り込めば問題ないはずです。
一段階ハードルは上がりますが、荷物が置いてある席も戻ってくる誰かの為に置いているのか確認してみるべきです。
どけてもらえればさわやかなお礼の言葉を添えて、ありがたく座りましょう。
お金を払って見に来ているのですし、それ以上にめったに無い機会は最大限に活かすべきだからです。
一列前で見れば数%見応えもアップします。
こんな状況で変に遠慮する必要はありません。
──────────────────────
遠慮せず最前列に進もう
──────────────────────
複数コートに分散して同時スタートする状況では、お目当ての試合ごとに席を移動することで、ベストポジションでの観戦を続けることができます。
そのためには少しだけ思いやりと積極性が必要になります。
来場したのは平日でありそれほど混んでいませんでした。
しかしながら会場全体としては席に余裕があっても、観客の皆さんはコートに一番近い場所を中心に偏って座ります。
最前列はびっしり埋まっているかといえばそうでもなく、まばらに1席だけ空いていたりカバンが置いてある場合もあります。
大抵の場合は「済みません」「そこ空いていますか」といったクッション言葉とともに空き席に滑り込めば問題ないはずです。
一段階ハードルは上がりますが、荷物が置いてある席も戻ってくる誰かの為に置いているのか確認してみるべきです。
どけてもらえればさわやかなお礼の言葉を添えて、ありがたく座りましょう。
お金を払って見に来ているのですし、それ以上にめったに無い機会は最大限に活かすべきだからです。
一列前で見れば数%見応えもアップします。
こんな状況で変に遠慮する必要はありません。
2015 .07.04
先月下旬にジャパン・オープンが神戸で開催されました。
2008年まで中国はトップ選手が参加していたのですが、それ以降若手選手の参加にとどまっていました。
今回は久々に中国代表レギュラー陣が来日するとあって、日本の卓球愛好家は例年にはない期待を寄せていたはずです。
そういったファンの1人として知人のX氏がいます。
大会3日目に観戦し、先日その模様を怒涛の勢いで語ってくれました。
普通の内容は卓球王国のサイトなどで紹介されていますので、それ以外の情報をお伝えしたいと思います。
──────────────────────
大会3日目を選んだ理由
──────────────────────
日程が進むにつれ試合で使われるコート数が少なくなってきます。
3日目はコート数がまだ多く、シード選手も登場してくる日です。
いろんな選手を見たい思いと強豪選手を見たい思いの両方が満たされます。
加えて平日のため観戦料は大変お得になっています。
平日は席の区分がなく全て自由席(¥1,000)の扱いです。
土日になると自由席(¥2,000)、スタンド席(¥3,000)、特別設置されるフロア席(¥4,000)の3つに区分されます。
決勝戦をフェンスの真横のフロア席で見ていた人は¥4,000も払っているんですね。
※なお前売りチケットが入手できればどの席も20%引きになります。
X氏は日本選手の応援にはほとんど、いや全く関心はなく、少数派の戦型(カットマンやペンホルダー)を中心に会場内を忙しく回っていました。
真ん中に設営されたメインコートはフェンスや台の装飾も他より凝っていて、カメラマンが取り囲んでいます。
しかしその中で行われた福原選手の試合すらチラ見程度だったそうです。
脇のコートで行われている外国選手同士の試合をつぶさに観察するX氏は、真の卓球マニアと言っても差し支えないでしょう。
2008年まで中国はトップ選手が参加していたのですが、それ以降若手選手の参加にとどまっていました。
今回は久々に中国代表レギュラー陣が来日するとあって、日本の卓球愛好家は例年にはない期待を寄せていたはずです。
そういったファンの1人として知人のX氏がいます。
大会3日目に観戦し、先日その模様を怒涛の勢いで語ってくれました。
普通の内容は卓球王国のサイトなどで紹介されていますので、それ以外の情報をお伝えしたいと思います。
──────────────────────
大会3日目を選んだ理由
──────────────────────
日程が進むにつれ試合で使われるコート数が少なくなってきます。
3日目はコート数がまだ多く、シード選手も登場してくる日です。
いろんな選手を見たい思いと強豪選手を見たい思いの両方が満たされます。
加えて平日のため観戦料は大変お得になっています。
平日は席の区分がなく全て自由席(¥1,000)の扱いです。
土日になると自由席(¥2,000)、スタンド席(¥3,000)、特別設置されるフロア席(¥4,000)の3つに区分されます。
決勝戦をフェンスの真横のフロア席で見ていた人は¥4,000も払っているんですね。
※なお前売りチケットが入手できればどの席も20%引きになります。
X氏は日本選手の応援にはほとんど、いや全く関心はなく、少数派の戦型(カットマンやペンホルダー)を中心に会場内を忙しく回っていました。
真ん中に設営されたメインコートはフェンスや台の装飾も他より凝っていて、カメラマンが取り囲んでいます。
しかしその中で行われた福原選手の試合すらチラ見程度だったそうです。
脇のコートで行われている外国選手同士の試合をつぶさに観察するX氏は、真の卓球マニアと言っても差し支えないでしょう。
某所で初対面のある方と練習をご一緒させてもらいました。
右利きのシェークでフォア裏ソフトバック表ソフトの中年男性でした。
お互い名乗る必要もないのでお名前は分かりません。
その方を仮にAさんということにします。
──────────────────────
電話で中断した時の判断
──────────────────────
Aさんは多忙なのか幅広い人脈があるのか詳細は不明ですが、練習中に頻繁に電話がかかってきます。
練習場の中は結構音が反響しており、片方の耳の穴を押さえながら早口で話していました。
3回目に電話がかかってきた時は「ちょっと待ってね」と私にではなく、電話の相手に告げて話がしやすい外に出て行きました。
台が空くのを待っている人がいるので、周囲の無言の圧力を感じながら早く戻ってこないかなと1人で立っていました。
約2分後に現れたのでほっとしましたが、長引いた場合はどうするか難しい判断が求められます。
電話中の人が帰ってくるまで打ちましょうかと別の誰かを誘い、20秒後に戻って来られたら申し訳ないですし、早めに台を明け渡してしまうとそれはそれで最初の相手の気分を害するかもしれません。
後で思い返せば、2分ぐらい経った時点で電話中の人を呼びに行きますと周囲に宣言し、台を明け渡してもいいですかと同意をもらうのがベストだったのでしょう。
このように思わぬ場面で気を使うことがあります。
右利きのシェークでフォア裏ソフトバック表ソフトの中年男性でした。
お互い名乗る必要もないのでお名前は分かりません。
その方を仮にAさんということにします。
──────────────────────
電話で中断した時の判断
──────────────────────
Aさんは多忙なのか幅広い人脈があるのか詳細は不明ですが、練習中に頻繁に電話がかかってきます。
練習場の中は結構音が反響しており、片方の耳の穴を押さえながら早口で話していました。
3回目に電話がかかってきた時は「ちょっと待ってね」と私にではなく、電話の相手に告げて話がしやすい外に出て行きました。
台が空くのを待っている人がいるので、周囲の無言の圧力を感じながら早く戻ってこないかなと1人で立っていました。
約2分後に現れたのでほっとしましたが、長引いた場合はどうするか難しい判断が求められます。
電話中の人が帰ってくるまで打ちましょうかと別の誰かを誘い、20秒後に戻って来られたら申し訳ないですし、早めに台を明け渡してしまうとそれはそれで最初の相手の気分を害するかもしれません。
後で思い返せば、2分ぐらい経った時点で電話中の人を呼びに行きますと周囲に宣言し、台を明け渡してもいいですかと同意をもらうのがベストだったのでしょう。
このように思わぬ場面で気を使うことがあります。
いろいろな方とお話しをすると、新しい発見や気付きがあって楽しいことがあります。
先日もある方と仕事の打ち合わせが終わり、近くのファミリーレストランで一緒に夕食を食べていた時のことです。
──────────────────────
競技による概念の違い
──────────────────────
お互いの趣味の話になり、相手の方は長年ボウリングをやっているとのことでした。
当然のことながらマイボールを何個も持っていて、ボウリング場に保管しているボールや、自宅から持参するボールがあるそうです。
「持参する」とさらりと言われたのですが、平均で3個(えっ!)持って行くことが多く、キャスター付きの専用大型バッグを使っているのだそうです。
びっくりする私とは対照的に、ボウリング愛好家なら普通のことと涼しい顔です。
私に対しては「マイラケットを持っているんですか」と質問があり、競技は違えど同じですねということでそこそこ盛り上がりました。
その日の夜、布団に入ってからあることを考えていました。
ボウリングのマイボールと、卓球のマイラケットは同じ位置づけなのか?
巷の卓球場に準備されているラバー貼りラケットは、私がたまにボウリング場に行って使うボールと同等だと思います。
しかしお店でラバーとブレードを個別に買うのに相当することが、ボウリングにはなさそうです。
ボウリングのマイボールは、穴の開け方など競技者の細やかな好みに合わせて作るオーダーメイド品で、卓球で言うと特注ラケットに該当しそうです。
先日もある方と仕事の打ち合わせが終わり、近くのファミリーレストランで一緒に夕食を食べていた時のことです。
──────────────────────
競技による概念の違い
──────────────────────
お互いの趣味の話になり、相手の方は長年ボウリングをやっているとのことでした。
当然のことながらマイボールを何個も持っていて、ボウリング場に保管しているボールや、自宅から持参するボールがあるそうです。
「持参する」とさらりと言われたのですが、平均で3個(えっ!)持って行くことが多く、キャスター付きの専用大型バッグを使っているのだそうです。
びっくりする私とは対照的に、ボウリング愛好家なら普通のことと涼しい顔です。
私に対しては「マイラケットを持っているんですか」と質問があり、競技は違えど同じですねということでそこそこ盛り上がりました。
その日の夜、布団に入ってからあることを考えていました。
ボウリングのマイボールと、卓球のマイラケットは同じ位置づけなのか?
巷の卓球場に準備されているラバー貼りラケットは、私がたまにボウリング場に行って使うボールと同等だと思います。
しかしお店でラバーとブレードを個別に買うのに相当することが、ボウリングにはなさそうです。
ボウリングのマイボールは、穴の開け方など競技者の細やかな好みに合わせて作るオーダーメイド品で、卓球で言うと特注ラケットに該当しそうです。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。