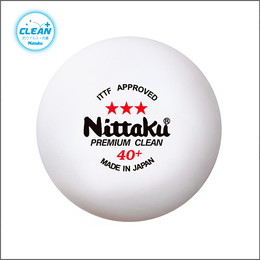2024 .08.03
前回に引き続き今回も新色ラバーについてお話しする予定でした。
しかしながらオリンピック開催中ということで練習仲間の間でいろいろな会話が交わされました。
そのためラバーの話は延期し、パリ五輪の内容に変更することにします。
いつものことながら試合結果や識者の分析など、普通の内容については大手メディアのほうを参照いただければと思います。
──────────────────────
演出効果
──────────────────────
練習場の雑談で出た意見としては、試合映像の合間に挿入される各種情報についてイイネとダメの評価がありました。
まずは悪い方から挙げると、卓球台を模したCGでどの位置にボールがバウンドしたかをドットをつけて分布図のように見せていました。
カメラ映像から瞬時に位置を割り出し、それをわかりやすく見せる今風のハイテク演出なのは理解できます。
普段卓球をしない一般の方なら、これは重要なデータでなんとなく凄そうと思うかもしれません。
しかしゲームの合間にあれを数秒間チラ見させただけでは、卓球競技者であってもそこから何かを読み取るのは困難です。
他にも何やら一覧表で表示されますが、同じく不要との厳しい意見がありました。
一方好意的な意見としては映画マトリックス風の3Dリプレイや、ボールの回転数表示を挙げた人がいました。
私としてはネットにかかったボールがギュルギュル回転している状態をズームアップ再生してくれたら、一般の方にも凄さが伝わるかなと思っています。
しかしながらオリンピック開催中ということで練習仲間の間でいろいろな会話が交わされました。
そのためラバーの話は延期し、パリ五輪の内容に変更することにします。
いつものことながら試合結果や識者の分析など、普通の内容については大手メディアのほうを参照いただければと思います。
──────────────────────
演出効果
──────────────────────
練習場の雑談で出た意見としては、試合映像の合間に挿入される各種情報についてイイネとダメの評価がありました。
まずは悪い方から挙げると、卓球台を模したCGでどの位置にボールがバウンドしたかをドットをつけて分布図のように見せていました。
カメラ映像から瞬時に位置を割り出し、それをわかりやすく見せる今風のハイテク演出なのは理解できます。
普段卓球をしない一般の方なら、これは重要なデータでなんとなく凄そうと思うかもしれません。
しかしゲームの合間にあれを数秒間チラ見させただけでは、卓球競技者であってもそこから何かを読み取るのは困難です。
他にも何やら一覧表で表示されますが、同じく不要との厳しい意見がありました。
一方好意的な意見としては映画マトリックス風の3Dリプレイや、ボールの回転数表示を挙げた人がいました。
私としてはネットにかかったボールがギュルギュル回転している状態をズームアップ再生してくれたら、一般の方にも凄さが伝わるかなと思っています。
2024 .03.16
今回は今年の夏に開かれるパリオリンピックについてお話ししたいと思います。
東京五輪が1年延期されたため、なんだもう次のオリンピックなのかと感じている方が多いかもしれませんね。
──────────────────────
うれしい放送時間
──────────────────────
大会全体の開催期間は7月26日~8月12日です。
その中で卓球競技は7月27日~8月10日にかけて行われます。
フランスのパリと日本の時差は8時間。
そのため自宅で録画しておいた映像の視聴が多くなりそうです。
映像を見る前に、さまざまな媒体より漏れ聞こえてくる試合結果を遮断するのはかなり難しいと予想されます。
と思っていた所、その心配はあまりなさそうということが分かりました。
山場を迎えた試合はいずれも視聴しやすい時間帯に行われるからです。
メダル獲得がかかった試合の開始時刻は以下の通りです(日本時間)。
7/30(火)混合ダブルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/3(土)女子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/4(日)男子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/9(金)男子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
8/10(土)女子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
おぉっ、なんてナイスな時間なんでしょうか!
東京五輪が1年延期されたため、なんだもう次のオリンピックなのかと感じている方が多いかもしれませんね。
──────────────────────
うれしい放送時間
──────────────────────
大会全体の開催期間は7月26日~8月12日です。
その中で卓球競技は7月27日~8月10日にかけて行われます。
フランスのパリと日本の時差は8時間。
そのため自宅で録画しておいた映像の視聴が多くなりそうです。
映像を見る前に、さまざまな媒体より漏れ聞こえてくる試合結果を遮断するのはかなり難しいと予想されます。
と思っていた所、その心配はあまりなさそうということが分かりました。
山場を迎えた試合はいずれも視聴しやすい時間帯に行われるからです。
メダル獲得がかかった試合の開始時刻は以下の通りです(日本時間)。
7/30(火)混合ダブルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/3(土)女子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/4(日)男子シングルス3位決定戦:20時30分、決勝:21時30分
8/9(金)男子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
8/10(土)女子団体3位決定戦:17時00分、決勝:22時00分
おぉっ、なんてナイスな時間なんでしょうか!
今回は世界卓球選手権についてお話しします。
各種メディアで報道がなされており、スケジュールや試合結果など一般的な情報はそちらご確認いただければと思います。
──────────────────────
紆余曲折を辿った開催
──────────────────────
開催場所はお隣韓国のプサン(釜山)です。
首都のソウルも飛行機ですぐに着くのですが、プサンはさらに距離が近いため福岡から船で訪れるコースも人気です。
プサンのアルファベット表記はBusanでPusanではありません。
最初の文字がBだと読みはP、日本語で言うところのパ行になるようです。
冬のソナタでお馴染みのヨン様ことペ・ヨンジュンさんも名字はBaeです。
他にも韓国のアルファベット表記は、最初の文字がRやLだと読み飛ばすなど少しややこしいです。
本来は2020年にプサンで世界選手権が行われる予定でした。
ところがその年の最初に全世界でコロナショックが巻き起こりました。
延期に次ぐ延期が発表され、結局開催見送りとなった経緯があります。
今回は満を持しての仕切り直し開催という意味もあるでしょう。
今年はオリンピックイヤーとなるため、世界選手権は通常の開催時期よりも早めに行われます。
ビッグイベントが短期間で連続しないようにしています。
私だけではないでしょうが、もうオリンピックなんだという不思議な感じがあります。
それは東京オリンピックが1年延期されたことが影響しています。
コロナは別に収束したわけではなく、変異を続けながら感染者は世界中で引き続き出ています。
しかし重篤化する危険性が下がったことや、ウイズコロナの考えが広まり以前の日常がほぼ戻ってきました。
私も昨年後半に感染してしまいました。
幸いにも大事に至ることはなく、市販の風邪薬を服用しながら1週間大人しく過ごすことで治りました。
各種メディアで報道がなされており、スケジュールや試合結果など一般的な情報はそちらご確認いただければと思います。
──────────────────────
紆余曲折を辿った開催
──────────────────────
開催場所はお隣韓国のプサン(釜山)です。
首都のソウルも飛行機ですぐに着くのですが、プサンはさらに距離が近いため福岡から船で訪れるコースも人気です。
プサンのアルファベット表記はBusanでPusanではありません。
最初の文字がBだと読みはP、日本語で言うところのパ行になるようです。
冬のソナタでお馴染みのヨン様ことペ・ヨンジュンさんも名字はBaeです。
他にも韓国のアルファベット表記は、最初の文字がRやLだと読み飛ばすなど少しややこしいです。
本来は2020年にプサンで世界選手権が行われる予定でした。
ところがその年の最初に全世界でコロナショックが巻き起こりました。
延期に次ぐ延期が発表され、結局開催見送りとなった経緯があります。
今回は満を持しての仕切り直し開催という意味もあるでしょう。
今年はオリンピックイヤーとなるため、世界選手権は通常の開催時期よりも早めに行われます。
ビッグイベントが短期間で連続しないようにしています。
私だけではないでしょうが、もうオリンピックなんだという不思議な感じがあります。
それは東京オリンピックが1年延期されたことが影響しています。
コロナは別に収束したわけではなく、変異を続けながら感染者は世界中で引き続き出ています。
しかし重篤化する危険性が下がったことや、ウイズコロナの考えが広まり以前の日常がほぼ戻ってきました。
私も昨年後半に感染してしまいました。
幸いにも大事に至ることはなく、市販の風邪薬を服用しながら1週間大人しく過ごすことで治りました。
2024 .02.03
先月の1月22日から28日までの日程で全日本選手権が開催されました。
試合結果などについては大手メディアを参照いただければと思います。
私が練習をご一緒する方々との雑談で出た意見をご紹介いたします。
──────────────────────
分散開催、TV放送
──────────────────────
最初にいただいたのは、従来通りの大会は今回が最後だねというお話でした。
来年はシングルスとダブルスが分離開催されます。
2025年1月21日~26日に東京体育館でシングルスが行われ、続いて1月30日から2月2日にかけて愛知県のスカイホール豊田でダブルスが行われます。
2つに分かれるとそれぞれの大会規模が縮小され、話題性もやや下がるのではないかと思われます。
しかしこれは選手ファーストの観点からすれば改善であり、妥当ではないでしょうか。
全日本ではありませんが、昔の世界選手権は団体戦と個人戦を1回の大会で行っていたという、かなり無茶な運営がありました。
ある1人の選手が物理的に出場可能なのは、団体、シングルス、男女どちらかのダブルス、混合ダブルスの計4種目でしょうが、全てにエントリーすると多忙すぎて倒れてしまうでしょう。
他には今回の全日本は開催時期が1週間早かったら良かったのにというご意見がありました。
いつものようにNHKは全日本を放送してはくれたのですが、大相撲と重なってしまったのでNHK的には相撲の方をメインに取り上げざるを得ない事情がありました。
テレビの映像は最近の世界選手権のような横方向ではなく、縦方向のアングルにほぼ固定されており、そのほうがいいねという感想が多数出ました。
ただし放送中にNHK総合のサブチャンネルとの切り替わりがあり、その影響を受けた方がいました。
録画機器が追従できなかったり、サブチャンネルは画質が落ちていたケースがあったようです。
試合結果などについては大手メディアを参照いただければと思います。
私が練習をご一緒する方々との雑談で出た意見をご紹介いたします。
──────────────────────
分散開催、TV放送
──────────────────────
最初にいただいたのは、従来通りの大会は今回が最後だねというお話でした。
来年はシングルスとダブルスが分離開催されます。
2025年1月21日~26日に東京体育館でシングルスが行われ、続いて1月30日から2月2日にかけて愛知県のスカイホール豊田でダブルスが行われます。
2つに分かれるとそれぞれの大会規模が縮小され、話題性もやや下がるのではないかと思われます。
しかしこれは選手ファーストの観点からすれば改善であり、妥当ではないでしょうか。
全日本ではありませんが、昔の世界選手権は団体戦と個人戦を1回の大会で行っていたという、かなり無茶な運営がありました。
ある1人の選手が物理的に出場可能なのは、団体、シングルス、男女どちらかのダブルス、混合ダブルスの計4種目でしょうが、全てにエントリーすると多忙すぎて倒れてしまうでしょう。
他には今回の全日本は開催時期が1週間早かったら良かったのにというご意見がありました。
いつものようにNHKは全日本を放送してはくれたのですが、大相撲と重なってしまったのでNHK的には相撲の方をメインに取り上げざるを得ない事情がありました。
テレビの映像は最近の世界選手権のような横方向ではなく、縦方向のアングルにほぼ固定されており、そのほうがいいねという感想が多数出ました。
ただし放送中にNHK総合のサブチャンネルとの切り替わりがあり、その影響を受けた方がいました。
録画機器が追従できなかったり、サブチャンネルは画質が落ちていたケースがあったようです。
2024 .01.06
全国津々浦々、各地の卓球場では試合が行われています。
私が普段お邪魔している所でも練習に続いて試合という流れで進みます。
今回はその試合中に感じたことをお話ししたいと思います。
──────────────────────
バックハンドで打つべし
──────────────────────
ネット上にある上級者の試合動画を見ると、フォア前に出されたサーブをすすっとフォア側に動き鮮やかにバックハンドで払う場面があります。
お手本のようなバックハンド攻撃で、片面だけにラバーを貼ったペンの私にはできない芸当です。
過去に裏面打法を試みて挫折した苦い思い出がふとよみがえることもあります。
そんなことは綺麗さっぱり忘れなさいと自分に言い聞かせると同時に、両面にラバーを貼っている皆さんには頑張って欲しいという思いがあります。
試合の審判をしていると、シェーク裏裏同士の対戦なのにやたらとバックのツッツキ合いが続くことがあります。
打ち込んでいくとそれなりの確率でミスってしまうため、慎重になっているのは分かります。
それでも流石にバウンド後のボールが明らかに台から出る長さなら、バックハンドを振って欲しいと見ていてイライラがつのります。
私ならとうの昔にフォアで回り込んで攻撃を仕掛けています。
片面にしかラバーを貼っていないので自分はこれしかないという決意があり、強引な回り込みが多いのは自分でも認識しています。
かなり差し込まれた返球でバック側サイドを切るボールを気合で回り込んで打つと、中高生などからスゲーと言われます。
そんな私からすれば、せっかくラバーを2枚貼っているんだからもっとバックから攻撃して欲しいぞと心のなかで叫んでいます。
私が普段お邪魔している所でも練習に続いて試合という流れで進みます。
今回はその試合中に感じたことをお話ししたいと思います。
──────────────────────
バックハンドで打つべし
──────────────────────
ネット上にある上級者の試合動画を見ると、フォア前に出されたサーブをすすっとフォア側に動き鮮やかにバックハンドで払う場面があります。
お手本のようなバックハンド攻撃で、片面だけにラバーを貼ったペンの私にはできない芸当です。
過去に裏面打法を試みて挫折した苦い思い出がふとよみがえることもあります。
そんなことは綺麗さっぱり忘れなさいと自分に言い聞かせると同時に、両面にラバーを貼っている皆さんには頑張って欲しいという思いがあります。
試合の審判をしていると、シェーク裏裏同士の対戦なのにやたらとバックのツッツキ合いが続くことがあります。
打ち込んでいくとそれなりの確率でミスってしまうため、慎重になっているのは分かります。
それでも流石にバウンド後のボールが明らかに台から出る長さなら、バックハンドを振って欲しいと見ていてイライラがつのります。
私ならとうの昔にフォアで回り込んで攻撃を仕掛けています。
片面にしかラバーを貼っていないので自分はこれしかないという決意があり、強引な回り込みが多いのは自分でも認識しています。
かなり差し込まれた返球でバック側サイドを切るボールを気合で回り込んで打つと、中高生などからスゲーと言われます。
そんな私からすれば、せっかくラバーを2枚貼っているんだからもっとバックから攻撃して欲しいぞと心のなかで叫んでいます。
私は部活で卓球をしていた頃は万年補欠だったので勝率はかなり低めでした。
その後は初級者との対戦も増え、ある程度はマシになりました。
それでも負け試合は多く、振り返った時の感想を述べてみます。
──────────────────────
良い負け試合
──────────────────────
ここで言う「良い」という表現は、客観的・合理的に良いという意味ではありません。
私の気持ちとして「負けたけれど納得できる試合だった」と思えた試合のことです。
そういうのはやはり数回以上のラリーが何度も続いた試合です。
一般的な卓球の試合でイメージするボールの往復があると充実感が満たされます。
さらに適度に競った場合、満足度がより高くなります。
ドラマチック効果なのかもしれません。
相手が格上の場合ならどんな展開でそう思えるでしょうか。
エースボールをブロックできた、裏を掻いた一打が決まったなど自分が一矢報いた場面があった時はそう感じます。
やられてしまった時も絶妙の流し打ちや、ネットインをカーブロングで返されたりすると、自分に対しこんな離れ業を披露してくれるのかと一瞬感謝したくなります。
その後は初級者との対戦も増え、ある程度はマシになりました。
それでも負け試合は多く、振り返った時の感想を述べてみます。
──────────────────────
良い負け試合
──────────────────────
ここで言う「良い」という表現は、客観的・合理的に良いという意味ではありません。
私の気持ちとして「負けたけれど納得できる試合だった」と思えた試合のことです。
そういうのはやはり数回以上のラリーが何度も続いた試合です。
一般的な卓球の試合でイメージするボールの往復があると充実感が満たされます。
さらに適度に競った場合、満足度がより高くなります。
ドラマチック効果なのかもしれません。
相手が格上の場合ならどんな展開でそう思えるでしょうか。
エースボールをブロックできた、裏を掻いた一打が決まったなど自分が一矢報いた場面があった時はそう感じます。
やられてしまった時も絶妙の流し打ちや、ネットインをカーブロングで返されたりすると、自分に対しこんな離れ業を披露してくれるのかと一瞬感謝したくなります。
ずっと前に卓球における修正力や対応力に関し書いたことがあります。
今回はそれと似たようなお話をしたいと思います。
──────────────────────
カット=守備型ではない
──────────────────────
某所で団体戦に参加していた時のことです。
初戦は全員カットマンの高校生ぽいチームでした。
私と同じチームの大江さん(仮名)はシニアの男性で、漠然としたドライブマン対カットマンの試合イメージを持っていました。
連続するドライブ対カットのラリーです。
しかしながらそういう場面は思っているよりも少なく、この試合を経験して非常に困惑していました。
現代卓球ではカットマンも攻撃を増やさなければならず、フォアにテナジーなどのテンションラバーを貼っているのは当たり前です。
相手のヤングカットマン達は、時々カットもする6割攻撃選手のようなA君、フォア側は全部打ってくる左側だけカットマンのB君など、大江さんの常識を覆す面々でした。
いつもの練習場にそんなニュータイプはおらず、やり場のないいらだちを私にボヤくことでぶつけてきました。
今回はそれと似たようなお話をしたいと思います。
──────────────────────
カット=守備型ではない
──────────────────────
某所で団体戦に参加していた時のことです。
初戦は全員カットマンの高校生ぽいチームでした。
私と同じチームの大江さん(仮名)はシニアの男性で、漠然としたドライブマン対カットマンの試合イメージを持っていました。
連続するドライブ対カットのラリーです。
しかしながらそういう場面は思っているよりも少なく、この試合を経験して非常に困惑していました。
現代卓球ではカットマンも攻撃を増やさなければならず、フォアにテナジーなどのテンションラバーを貼っているのは当たり前です。
相手のヤングカットマン達は、時々カットもする6割攻撃選手のようなA君、フォア側は全部打ってくる左側だけカットマンのB君など、大江さんの常識を覆す面々でした。
いつもの練習場にそんなニュータイプはおらず、やり場のないいらだちを私にボヤくことでぶつけてきました。
2023 .08.19
少し前に某所で個人戦の大会が開かれ参加しました。
今回はその時に見たこと感じたことを思いつくまま書いてみました。
──────────────────────
新たなレシーブを実験
──────────────────────
前回、斜め上回転のサーブを出してもバックスピンを掛けて返してくる人のことをお話ししました。
それと同じ真似はできませんが似た技術として、台上でカットをするようなレシーブを自分も取り入れようと考えていました。
具体的にどういうことかと言うと、ツッツキで返す場合、通常ならコースと長さを重視ししがちです。
相手コートの特定の位置にボールを置きにいく感じがある返球です。
カットマンの人がストップをされた時、そういった置きにいくツッツキで返す場合もありますが、短いボールであってもカットと同じようにボールに逆回転を与えることを重視した返球の場合もあります。
私が新たなレパートリーとしたいのはその後者の返球です。
台上のボールの下側を鋭くしゃくるようにして、カットと同じように失速してふわりと着地するような弾道です。
このカットレシーブが実戦で使えるのか試してみたかったのです。
結果としてはまあまあという感じでした。
全くダメダメでとんでもないオーバーミスという場合もありました。
幸い7割程度はそこそこいい感じの低さで返すことができました。
そして相手も3球目を決めづらいように見えました。
絶妙のぶつ切りカットで返せたときは、弾道が最後にストンと落ちバウンドも短いので、相手が驚いてつんのめったことがありました。
有効な小技になりそうで今後はもっと精度を高めようと考えています。
今回はその時に見たこと感じたことを思いつくまま書いてみました。
──────────────────────
新たなレシーブを実験
──────────────────────
前回、斜め上回転のサーブを出してもバックスピンを掛けて返してくる人のことをお話ししました。
それと同じ真似はできませんが似た技術として、台上でカットをするようなレシーブを自分も取り入れようと考えていました。
具体的にどういうことかと言うと、ツッツキで返す場合、通常ならコースと長さを重視ししがちです。
相手コートの特定の位置にボールを置きにいく感じがある返球です。
カットマンの人がストップをされた時、そういった置きにいくツッツキで返す場合もありますが、短いボールであってもカットと同じようにボールに逆回転を与えることを重視した返球の場合もあります。
私が新たなレパートリーとしたいのはその後者の返球です。
台上のボールの下側を鋭くしゃくるようにして、カットと同じように失速してふわりと着地するような弾道です。
このカットレシーブが実戦で使えるのか試してみたかったのです。
結果としてはまあまあという感じでした。
全くダメダメでとんでもないオーバーミスという場合もありました。
幸い7割程度はそこそこいい感じの低さで返すことができました。
そして相手も3球目を決めづらいように見えました。
絶妙のぶつ切りカットで返せたときは、弾道が最後にストンと落ちバウンドも短いので、相手が驚いてつんのめったことがありました。
有効な小技になりそうで今後はもっと精度を高めようと考えています。
現在卓球の世界選手権(個人戦)が開催中で、連日熱い試合が繰り広げられています。
主要な情報は大手メディアなどに譲り、それ以外のことや私個人の感想などについて書いてみたいと思います。
──────────────────────
開催地や放送の概要
──────────────────────
開催地は南アフリカ共和国のダーバンという都市です。
アフリカ大陸南端から少しだけ西側にあります。
アフリカだから熱帯雨林をイメージしがちですが、緯度が高いので気候区分は温帯になります。
ただし日本のように寒暖差は大きくなく、年間を通じて穏やかで今は雨が少なく過ごしやすい場所です。
日本からは中東などからの乗り継ぎにより、ほぼ丸一日かけての移動となります。
体力もお金もかけて皆さん参加されていてご苦労さまです。
卓球台は南アフリカ共和国の国旗にちなんだ色が使われているようです。
6色中、緑と黄色を台の土台部分に配し天板は黒となっています。
黒い台は大昔はよくあったそうで、逆に今では少し珍しく感じます。
テレビ東京での放送に加えネットでの動画も視聴できます。
ネット動画は放映権の関係で特定の試合は視聴不可ということが過去にありました。
今回はそういうことはなく、あえて言えば定期的にCM映像が挿入される程度です。
ゲームごとの境目などではなく突然入りますが、この程度のCMで済むなら十分納得できます。
テレ東で放送されなかった試合もネットにはあるので、お気に入りの選手のプレーを見れるのはいいことです。
主要な情報は大手メディアなどに譲り、それ以外のことや私個人の感想などについて書いてみたいと思います。
──────────────────────
開催地や放送の概要
──────────────────────
開催地は南アフリカ共和国のダーバンという都市です。
アフリカ大陸南端から少しだけ西側にあります。
アフリカだから熱帯雨林をイメージしがちですが、緯度が高いので気候区分は温帯になります。
ただし日本のように寒暖差は大きくなく、年間を通じて穏やかで今は雨が少なく過ごしやすい場所です。
日本からは中東などからの乗り継ぎにより、ほぼ丸一日かけての移動となります。
体力もお金もかけて皆さん参加されていてご苦労さまです。
卓球台は南アフリカ共和国の国旗にちなんだ色が使われているようです。
6色中、緑と黄色を台の土台部分に配し天板は黒となっています。
黒い台は大昔はよくあったそうで、逆に今では少し珍しく感じます。
テレビ東京での放送に加えネットでの動画も視聴できます。
ネット動画は放映権の関係で特定の試合は視聴不可ということが過去にありました。
今回はそういうことはなく、あえて言えば定期的にCM映像が挿入される程度です。
ゲームごとの境目などではなく突然入りますが、この程度のCMで済むなら十分納得できます。
テレ東で放送されなかった試合もネットにはあるので、お気に入りの選手のプレーを見れるのはいいことです。
連続でお話してきました卓球の不文律ですが、今回の第3回では私の周りであった事例をご紹介します。
不文律とはルールでは定められていませんが、一般にそうすべきだと考えられている暗黙の掟のようなものです。
──────────────────────
不文律なので解釈は人それぞれ
──────────────────────
卓球の不文律で代表的なのがネットやエッジにかすって得点した場合、得点が入った側の競技者が相手に対し済まないという意思表示をするケースです。
卓球をやっている人の間ではほぼ合意が取られている行いです。
しかしそれは人によって意思表示の度合に濃淡があることを感じます。
世界選手権の映像などを見ていると、人差し指だけを上に向けて立てる、あるいは手のひらを相手に見せての無言パターンが多いと思います。
それは選手間で話す言葉が異なることや、そういうシンプルな意思表示で必要十分だという考えに基づいているのでしょう。
ですから日本人同士かつ、その辺のありふれた試合でも同様の無言ポーズは見られます。
またそういう場所での試合であれば「すみません」「ゴメン」といった言葉を返す場合もよくあります。
不文律なので明確な定義などないのですが、概ねそんな感じでいいと理解されています。
少し厄介なのは、この不文律を独自に発展解釈された方がたまにいらっしゃるようです。
そういう人物に該当しそうなのがX氏です。
不文律とはルールでは定められていませんが、一般にそうすべきだと考えられている暗黙の掟のようなものです。
──────────────────────
不文律なので解釈は人それぞれ
──────────────────────
卓球の不文律で代表的なのがネットやエッジにかすって得点した場合、得点が入った側の競技者が相手に対し済まないという意思表示をするケースです。
卓球をやっている人の間ではほぼ合意が取られている行いです。
しかしそれは人によって意思表示の度合に濃淡があることを感じます。
世界選手権の映像などを見ていると、人差し指だけを上に向けて立てる、あるいは手のひらを相手に見せての無言パターンが多いと思います。
それは選手間で話す言葉が異なることや、そういうシンプルな意思表示で必要十分だという考えに基づいているのでしょう。
ですから日本人同士かつ、その辺のありふれた試合でも同様の無言ポーズは見られます。
またそういう場所での試合であれば「すみません」「ゴメン」といった言葉を返す場合もよくあります。
不文律なので明確な定義などないのですが、概ねそんな感じでいいと理解されています。
少し厄介なのは、この不文律を独自に発展解釈された方がたまにいらっしゃるようです。
そういう人物に該当しそうなのがX氏です。
前回は卓球の不文律についてお話しをしました。
不文律とはルールでは定められていませんが、競技者が暗黙のルールとして守っているものです。
ネットインで得点したら済まなかったという意思表示をするのが代表的な例です。
今回は他の競技との比較で考えてみたいと思います。
──────────────────────
叫び声は控えてほしい
──────────────────────
不文律はどの競技にも多寡の差はあれ存在します。
Wikipediaには野球に関する不文律が独立した項目で存在します。
野球における不文律が意識されるようになった背景には、1)相手に対する敬意、2)勝敗が(実質的に)確定した後はガツガツしない、の2つがあります。
イチロー選手がバッターボックスに立ったときバットを立てるあの動作は、威嚇と受け取られる可能性があったそうです。
メジャーリーグでのプレー前にある日本人選手がやらないほうがいいのではと助言していたそうです。
卓球ではH選手がサーブを出す前に、ルーチンとして必ずガンを飛ばすというのがありました。
それくらいは構いませんが、得点後にも相手に向かって拳を突き出し奇声を発っしていたのでイエローカードを出されたことがありました。
個人的には日本人選手は声を張り上げすぎだと思います。
それは大昔から容認されていて、ダブルスのO選手とA選手が得点する度に「ヨッシャー」と大声を張り上げて2人でくるくる円を描いていたという話を聞き、ちょっとどうかなと思ってしまいました。
不文律とはルールでは定められていませんが、競技者が暗黙のルールとして守っているものです。
ネットインで得点したら済まなかったという意思表示をするのが代表的な例です。
今回は他の競技との比較で考えてみたいと思います。
──────────────────────
叫び声は控えてほしい
──────────────────────
不文律はどの競技にも多寡の差はあれ存在します。
Wikipediaには野球に関する不文律が独立した項目で存在します。
野球における不文律が意識されるようになった背景には、1)相手に対する敬意、2)勝敗が(実質的に)確定した後はガツガツしない、の2つがあります。
イチロー選手がバッターボックスに立ったときバットを立てるあの動作は、威嚇と受け取られる可能性があったそうです。
メジャーリーグでのプレー前にある日本人選手がやらないほうがいいのではと助言していたそうです。
卓球ではH選手がサーブを出す前に、ルーチンとして必ずガンを飛ばすというのがありました。
それくらいは構いませんが、得点後にも相手に向かって拳を突き出し奇声を発っしていたのでイエローカードを出されたことがありました。
個人的には日本人選手は声を張り上げすぎだと思います。
それは大昔から容認されていて、ダブルスのO選手とA選手が得点する度に「ヨッシャー」と大声を張り上げて2人でくるくる円を描いていたという話を聞き、ちょっとどうかなと思ってしまいました。
今回は不文律についてお話ししたいと思います。
ここで言う不文律とは、ルールには定められていないものの、そうすべきだと考えられている暗黙の掟です。
──────────────────────
ネットイン、エッジ
──────────────────────
卓球の不文律として真っ先に思い浮かぶのは、自分が打ったボールがネットやエッジに触れて得点した際、済まなかったという意思表示をすることです。
相手に手のひらを見せたり、日本人同士なら「すみません」と声をかけたりします。
他の競技のバレーボールなどでもボールがネットに当たり、予期せぬ軌道に変化することはあります。
いずれも相手を陥れようと悪意を持って持ってそうしているわけではありません。
ただ卓球ではその不可抗力に対し、同情を示す仕草をするのが好ましいこととなっています。
卓球をやり始めた人がネットインをして「ラッキー」と喜んでいます。
それは自然な感情であると思います。
私はもうすっかり卓球脳になってしまっているため、今一度それをリセットして考えてみました。
ネットに激しく当たりぼてぼてのスローボールが相手側へポロッと落ちるケースは、客観的にわかりやすいどうしようもなさ感が漂います。
ラリー中、わずかにネットをかすったボールも相手の予測を狂わせ返球を困難にさせます。
私の推測ですが、前者のポトリ事例はバレーボールやテニスと比較すると卓球は顕著ではないかと思います。
見ていて本当になすすべなし、という表現がピッタリにポトンと落ちてラリー終了です。
これは流石に厳しいねということで同情を示すようになり、それが後者のわずかにネットに触れた場合にも広がったのではないかと考えています。
エッジボールも同じく、弾道が完璧にあさっての方向に飛んでしまうエッジと、コッとかするだけのエッジもあります。
でもそれらを区別せずネットインと同じように見なすようになったのだと思います。
ここで言う不文律とは、ルールには定められていないものの、そうすべきだと考えられている暗黙の掟です。
──────────────────────
ネットイン、エッジ
──────────────────────
卓球の不文律として真っ先に思い浮かぶのは、自分が打ったボールがネットやエッジに触れて得点した際、済まなかったという意思表示をすることです。
相手に手のひらを見せたり、日本人同士なら「すみません」と声をかけたりします。
他の競技のバレーボールなどでもボールがネットに当たり、予期せぬ軌道に変化することはあります。
いずれも相手を陥れようと悪意を持って持ってそうしているわけではありません。
ただ卓球ではその不可抗力に対し、同情を示す仕草をするのが好ましいこととなっています。
卓球をやり始めた人がネットインをして「ラッキー」と喜んでいます。
それは自然な感情であると思います。
私はもうすっかり卓球脳になってしまっているため、今一度それをリセットして考えてみました。
ネットに激しく当たりぼてぼてのスローボールが相手側へポロッと落ちるケースは、客観的にわかりやすいどうしようもなさ感が漂います。
ラリー中、わずかにネットをかすったボールも相手の予測を狂わせ返球を困難にさせます。
私の推測ですが、前者のポトリ事例はバレーボールやテニスと比較すると卓球は顕著ではないかと思います。
見ていて本当になすすべなし、という表現がピッタリにポトンと落ちてラリー終了です。
これは流石に厳しいねということで同情を示すようになり、それが後者のわずかにネットに触れた場合にも広がったのではないかと考えています。
エッジボールも同じく、弾道が完璧にあさっての方向に飛んでしまうエッジと、コッとかするだけのエッジもあります。
でもそれらを区別せずネットインと同じように見なすようになったのだと思います。
Amazon.co.jpアソシエイトは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。